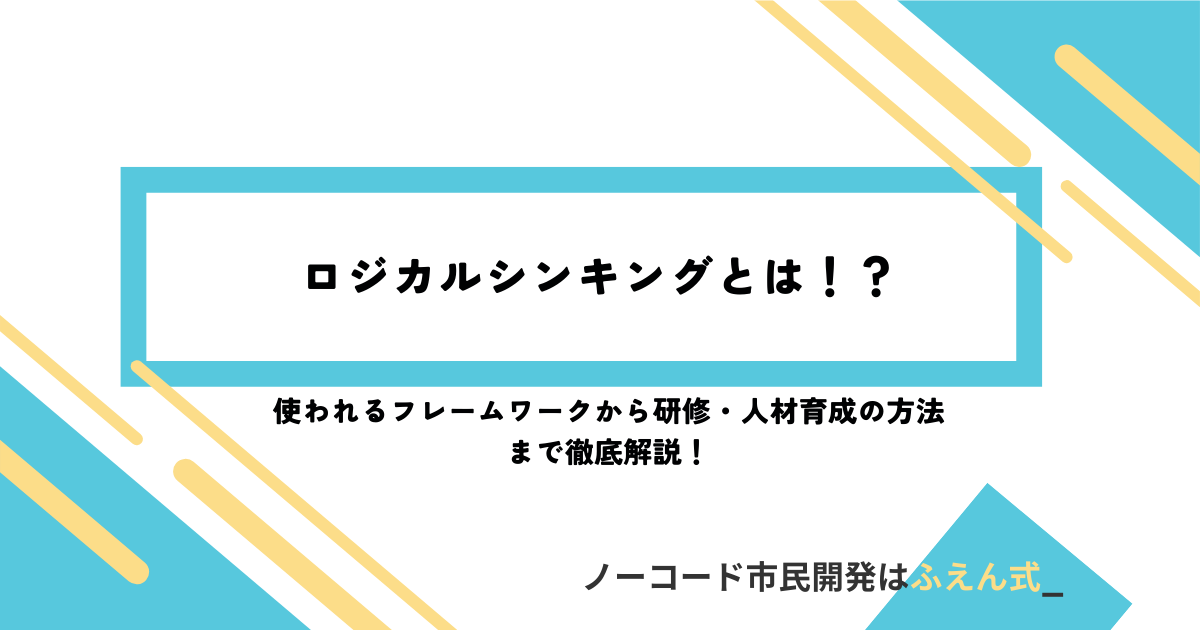ロジカルシンキングには、様々なフレームワークや思考法があり、それらを使うことで、問題解決やコミュニケーション、プレゼンテーションなどのスキルを向上させることができます。
しかし、ロジカルシンキングは一朝一夕に身につくものではありません。継続的な研修や人材育成が必要です。
この記事では、ロジカルシンキングとは何か、どのようなフレームワークがあるのか、どのように研修や人材育成を行うのかについて詳しく解説します。
それでは早速、ロジカルシンキングとは何か、について見ていきましょう。
ロジカルシンキングとは?

ロジカルシンキングとは、端的に表現すると、論理的に考えることです。
しかし、論理的に考えるというのは、どういうことでしょうか?一般的に、ロジカルシンキングには以下のような要素が含まれます。
- 目的:何のために考えるのか、明確にすること。
- 仮説:目的に沿って、考えられる解決策や答えを仮定すること。
- 根拠:仮説を支える、事実やデータ、情報を構造化すること。
- 検証:根拠をもとに、仮説が正しいかどうかを検証すること。
- 結論:検証の結果をもとに、最終的な解決策や答えを導くこと。
ロジカルシンキングは、このようなプロセスを通して、問題や課題に対して、合理的で効果的な解決策や答えを見つけることを目指します。
ロジカルシンキングは、ビジネスや学問、日常生活のあらゆる場面で役立ちますが、特に以下のような場合に重要になります。
- 問題が複雑で多岐にわたる場合:ロジカルシンキングを使うことで、問題を分解し、優先順位をつけ、解決策を絞り込むことができます。
- 情報が多くて整理しきれない場合:ロジカルシンキングを使うことで、情報を分類し、必要なものと不要なものを区別し、重要なポイントを抽出することができます。
- 相手に自分の考えを伝える必要がある場合:ロジカルシンキングを使うことで、自分の考えを明確にし、相手にわかりやすく説明し、説得力を持たせることができます。
ロジカルシンキングには、さらに具体的な思考法やフレームワークがあります。
それらを知ることで、ロジカルシンキングの実践力を高めることができます。
次の章では、ロジカルシンキングの前提となる基本の思考法について見ていきましょう。
[参考リンク-コンセプチュアルスキルとは!?ヒューマンスキルとの違いや、研修の方法についてわかりやすく解説します!]
ロジカルシンキングの前提となる基本の思考法
ロジカルシンキングを実践するには、まず、その前提となる基本の思考法を理解する必要があります。ここでは、ロジカルシンキングにおいてよく使われる、以下の4つの思考法について説明します。
MECE
MECEとは、Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略で、日本語では相互排他的かつ網羅的と訳されます。
よく聞く言葉ですと「モレなくダブりなく」と表現されることが多いです。
MECEとは、ある問題や課題に対して、その要素や要因を分解するときに、以下の2つの条件を満たすようにすることです。
- 相互排他的(ダブリなく):分解した要素や要因が、重複しないこと。
- 網羅的(モレなく):分解した要素や要因が、全体をカバーすること。
MECEにすることで、問題や課題を明確にし、無駄な情報や重複を排除し、漏れや抜けを防ぐことができます。MECEにするためには、以下のようなステップを踏みます。
- 問題や課題を定義する:何を解決したいのか、何が目的なのか、を明確にすること。
- 分解の軸を決める:問題や課題を分解するときに、どのような観点や基準で分けるのか、を決めること。
- 分解のレベルを決める:問題や課題を分解するときに、どの程度の細かさや深さで分けるのか、を決めること。
- 分解の結果をチェックする:分解した要素や要因が、MECEの条件を満たしているかどうか、をチェックすること。
MECEは、ロジカルシンキングの基本中の基本です。
MECEの考え方をマスターすることで、問題や課題を効率的に分析することができます。
演繹法
演繹法とは、一般的な原理や法則から、個別的な事実や現象を導き出す思考法です。
演繹法は、以下のような構造を持ちます。
- 前提:一般的な原理や法則、既知の事実などを示す文。
- 推論:前提から導かれる論理的な結論を示す文。
- 結論:推論によって得られる個別的な事実や現象を示す文。
演繹法の例を挙げてみましょう。
- 前提:すべての人間は死ぬ。
- 推論:ソクラテスは人間である。
- 結論:ソクラテスは死ぬ。
演繹法は、前提が正しいと仮定したときに、結論が必ず正しいとなる思考法です。演繹法を使うことで、自分の仮説や主張に対して、論理的な根拠を与えることができます。
演繹法は、特に、自分の考えを相手に伝えるときに有効です。
帰納法
帰納法とは、個別的な事実や現象から、一般的な原理や法則を導き出す思考法です。
帰納法は、以下のような構造を持ちます。
- 観察:個別的な事実や現象を観察し、記録すること。
- 分類:観察した事実や現象を共通点や相違点によって分類すること。
- 仮説:分類した事実や現象から、一般的な原理や法則を仮定すること。
- 検証:仮説を他の事実や現象に適用して、正しいかどうかを検証すること。
帰納法の例を挙げてみましょう。
- 観察:水を沸騰させると、気体になる。
- 分類:水以外の液体も沸騰させると、気体になる。
- 仮説:すべての液体は沸騰させると、気体になる。
- 検証:他の液体についても、沸騰させると気体になるかどうかを確認する。
帰納法は、観察した事実や現象から、新しい知識や発見を得ることができる思考法です。帰納法を使うことで、自分の仮説や主張に対して、実証的な根拠を与えることができます。帰納法は、特に、問題解決や研究開発などの場面で有効です。
雨傘雲
雨傘雲とは、ある事象や現象に対して、その原因や影響を考えるときに使う思考法です。雨傘雲は、以下のような図で表されます。
- 雲が黒っぽいことから「事実」を確認し、
- 雨が降りそうだという「解釈」をし、
- 傘を持っていこうという「アクション」する
というように「事実」「解釈」「アクション」をしっかりと区別し、物事を論理的に考えるロジカルシンキングの基本的なフレームワークになります。
雨傘雲を使うことで、問題や課題の本質を把握し、効果的な対策や改善策を考えることができます。
雨傘雲は、特に、問題分析や改善提案などの場面で有効です。
これらの思考法は、ロジカルシンキングの前提となる基本のものですが、フレームワークはこれらだけではありません。
次の章では、ロジカルシンキングに使われるフレームワークについて見ていきましょう。
ロジカルシンキングに使われるフレームワークとは何か?
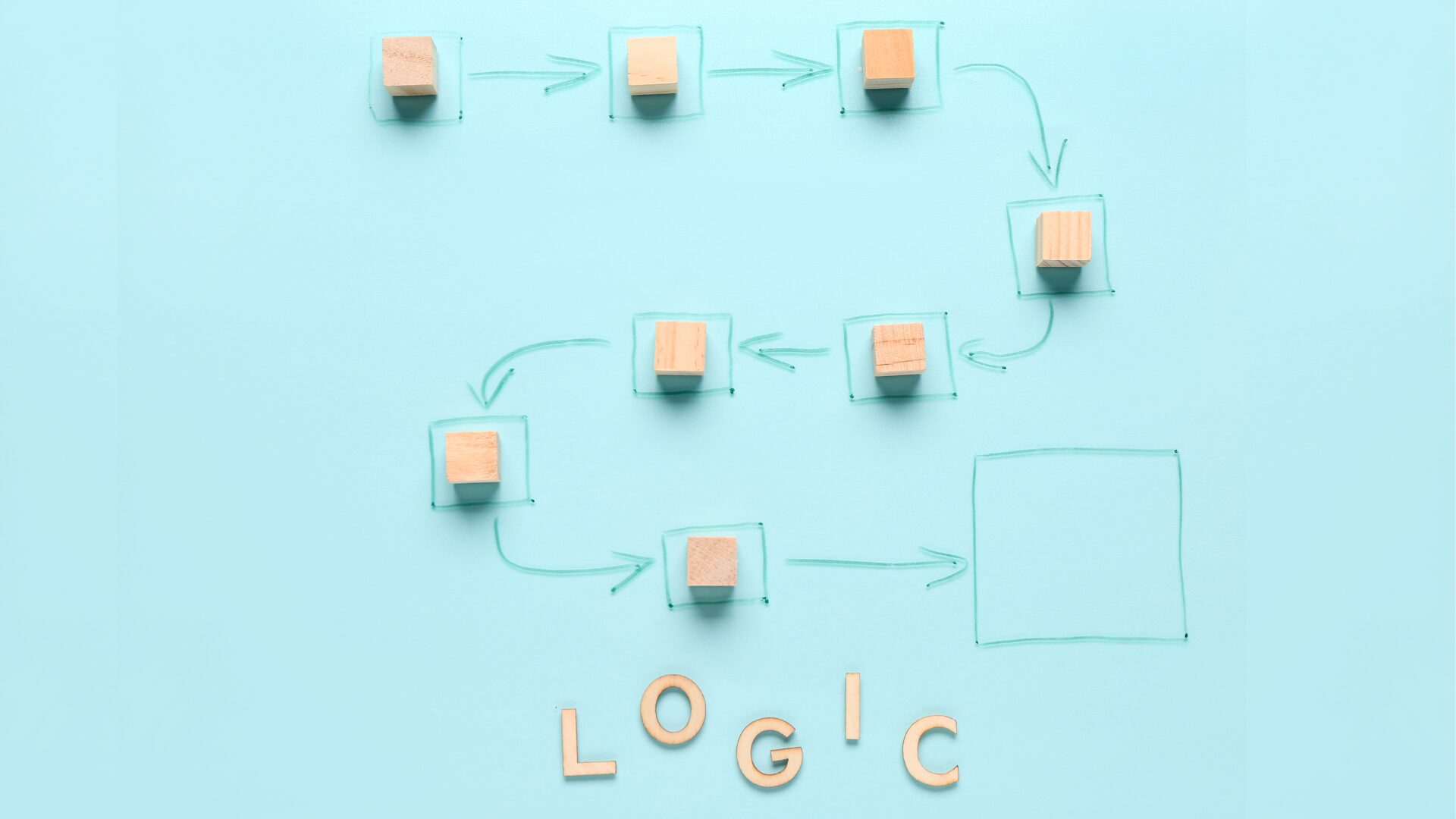
ロジカルシンキングには、前章で説明した基本の思考法のほかに、応用的なフレームワークがあります。
フレームワークとは、ある問題や課題に対して、考え方や手順を示す枠組みのことです。
フレームワークを使うことで、ロジカルシンキングをより効果的に実践することができます。
ここでは、ロジカルシンキングにおいてよく使われる、以下の5つのフレームワークについて説明します。
ピラミッドストラクチャー
ピラミッドストラクチャーとは、自分の考えや主張を、最も重要なメッセージから順に、階層的に整理するフレームワークです。
ピラミッドストラクチャーは、メインメッセージを中心にして、その左側にメッセージ1とメッセージ2を、右側にメッセージ3とメッセージ4を並べることで、その関係性を可視化することができます。
ピラミッドストラクチャーを使うことで、自分の考えや主張を、相手にわかりやすく伝えることができます。ピラミッドストラクチャーは、特に、プレゼンテーションやレポートなどの場面で有効です。
ロジックツリー
ロジックツリーとは、ある問題や課題を、MECEに従って、論理的に分解するフレームワークです。
ロジックツリーは、問題や目標を中心にして、その左側に要因を、右側に解決策を並べることで、その関係性を可視化することができます。
ロジックツリーを使うことで、問題や課題の本質を把握し、効果的な対策や改善策を考えることができます。
ロジックツリーは、特に、問題分析や改善提案などの場面で有効です。
PDCA
PDCAとは、Plan, Do, Check, Actの略で、日本語では計画、実行、評価、改善と訳されます。PDCAは、ある目標や課題に対して、以下の4つのステップを繰り返すことで、継続的に改善するフレームワークです。
- Plan:目標や課題を明確にし、解決策や実施計画を立てること。
- Do:計画に沿って、解決策や実施計画を実行すること。
- Check:実行した結果を評価し、目標や課題に対して効果があったかどうかを検証すること。
- Act:評価した結果をもとに、解決策や実施計画を改善すること。
PDCAを使うことで、目標や課題に対して、効率的に改善することができます。PDCAは、特に、業務改善や品質管理などの場面で有効です。
ASIS/TOBE
ASIS/TOBEとは、現状(AS IS)と目標(TO BE)のギャップを分析するフレームワークです。
ASIS/TOBEは、現状と目標を中心にして、その左側に現状の要素や要因を、右側に目標の要素や要因を並べることで、その関係性を可視化することができます。
ASIS/TOBEを使うことで、現状と目標のギャップを明確にし、その原因や影響を分析することができます。
ASIS/TOBEは、特に、業務改善やイノベーションの創出などの場面で有効です。
SMARTの法則
SMARTの法則とは、目標を設定するときに、以下の5つの要素を満たすようにするフレームワークです。
- Specific:目標が具体的で明確であること。
- Measurable:目標が測定可能であること。
- Achievable:目標が達成可能であること。
- Relevant:目標が関連性があること。
- Time-bound:目標が期限があること。
SMARTの法則を使うことで、目標を効果的に設定することができます。SMARTの法則は、特に、目標管理やパフォーマンス評価などの場面で有効です。
ロジカルシンキングの研修・人材育成の方法は?

ロジカルシンキングは、前章までで説明したように、様々な思考法やフレームワークがあります。しかし、それらを知っているだけでは、ロジカルシンキングを身につけることはできません。
ロジカルシンキングは、実践的なスキルです。
そのため、実際に問題や課題に取り組んで、ロジカルシンキングを使って考えることで、ロジカルシンキングの力を養う必要があります。
ロジカルシンキングの研修や人材育成には、様々な方法がありますが、ここでは、代表的な2つの方法について紹介します。
Eラーニング
Eラーニングとは、インターネット上にある動画コンテンツ等を使って学習する方法です。
Eラーニングを使ってできるロジカルシンキングの研修は主にインプットを中心とすると良いでしょう。
Eラーニングを使うことで、ロジカルシンキングの研修や人材育成に以下のようなメリットがあります。
- 時間や場所に制約されない:Eラーニングは、自分の都合に合わせて、好きな時間や場所で学習することができます。また、繰り返し学習することもできます。
- コストや労力を節約できる:Eラーニングは、講師や教材などの費用や手間をかけることなく、学習することができます。また、学習の進捗や成果を管理しやすくなります。
Eラーニングは、ロジカルシンキングの研修や人材育成において、効率的で便利な方法です。しかし、Eラーニングには、以下のようなデメリットもあります。
- 自己管理やモチベーションが必要:Eラーニングは、自分で学習計画や目標を立てて、実行することが必要です。また、学習に対するモチベーションを維持することも必要です。これらができないと、学習が中断したり、効果が低下したりする可能性があります。
- 実践的な内容が不足する:Eラーニングは、自分で学習することが多いため、実践的な内容が不足することがあります。例えば、自分のロジカルシンキングのレベルや課題を客観的に評価してもらったり、他の人とロジカルシンキングに関する意見交換やディスカッションをしたりすることが難しい場合があります。
Eラーニングは、ロジカルシンキングの研修や人材育成において、有効な方法ですが、完璧な方法ではありません。Eラーニングを使うときには、これらのメリットとデメリットを考慮して、自分に合った学習方法を選ぶことが大切です。
ワークショップ
ワークショップとは、複数の人が集まって、あるテーマや課題について、実践的に学習する方法です。
ワークショップを使ってできるロジカルシンキングの研修は、アウトプットをメインにした研修にすると良いでしょう。
ワークショップを使うことで、ロジカルシンキングの研修や人材育成に以下のようなメリットがあります。
- 実践的な研修ができる:ワークショップは、他の人と一緒に学習することができます。そのため、自分のロジカルシンキングのレベルや課題を客観的に評価してもらったり、他の人とロジカルシンキングに関する意見交換やディスカッションをしたりすることができます。これらは、ロジカルシンキングの力を高めるために重要な要素です。
- 多様な視点や知識を得ることができる:ワークショップは、様々なバックグラウンドや経験を持つ人が参加することができます。そのため、自分では気づかなかった視点や知識を得ることができます。これらは、ロジカルシンキングの幅や深さを広げるために有用です。
ワークショップは、ロジカルシンキングの研修や人材育成において、効果的で楽しい方法です。
しかし、ワークショップには、以下のようなデメリットもあります。
- 時間や場所に制約される:ワークショップは、複数の人が集まって行うことが前提です。そのため、参加者や講師の都合に合わせて、時間や場所を決める必要があります。また、繰り返し学習することも難しい場合があります。
- コストや労力がかかる:ワークショップは、講師や教材などの費用や手間をかけることが多いです。また、学習の進捗や成果を管理することも大変な場合があります。
ワークショップは、ロジカルシンキングの研修や人材育成において、有効な方法ですが、簡単な方法ではありません。
ワークショップを使うときには、これらのメリットとデメリットを考慮して、自分に合った学習方法を選ぶことが大切です。
[参考リンク-ブレンディットラーニングとは!?DX人材育成への活用やメリットについて解説!]
まとめ
この記事では、ロジカルシンキングとは何か、どのような思考法やフレームワークがあるのか、どのように研修や人材育成を行うのか、について詳しく解説しました。
ロジカルシンキングは、ビジネスや学問、日常生活のあらゆる場面で役立つスキルであり、またDXにも必須のスキルです。
ロジカルシンキングを身につけることで、問題解決やコミュニケーション、プレゼンテーションなどの能力を向上させることができます。
しかし、ロジカルシンキングは一朝一夕に身につくものではありません。継続的な研修や人材育成が必要です。
この記事では、ロジカルシンキングの研修や人材育成において、Eラーニングとワークショップという2つの方法を紹介しました。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分に合った学習方法を選ぶことが大切です。
[参考リンク-ラテラルシンキングとは!?具体例や活用の方法から研修の仕方までわかりやすく解説します!]
[参考リンク-問題解決に必要なクリティカルシンキングとは!?ロジカルシンキングとの違いや効果的な研修の方法について解説します!]
[参考リンク-デザインシンキングとは!?問題定義のためのフレームワークからメリットデメリット、研修の方法まで徹底解説します!]