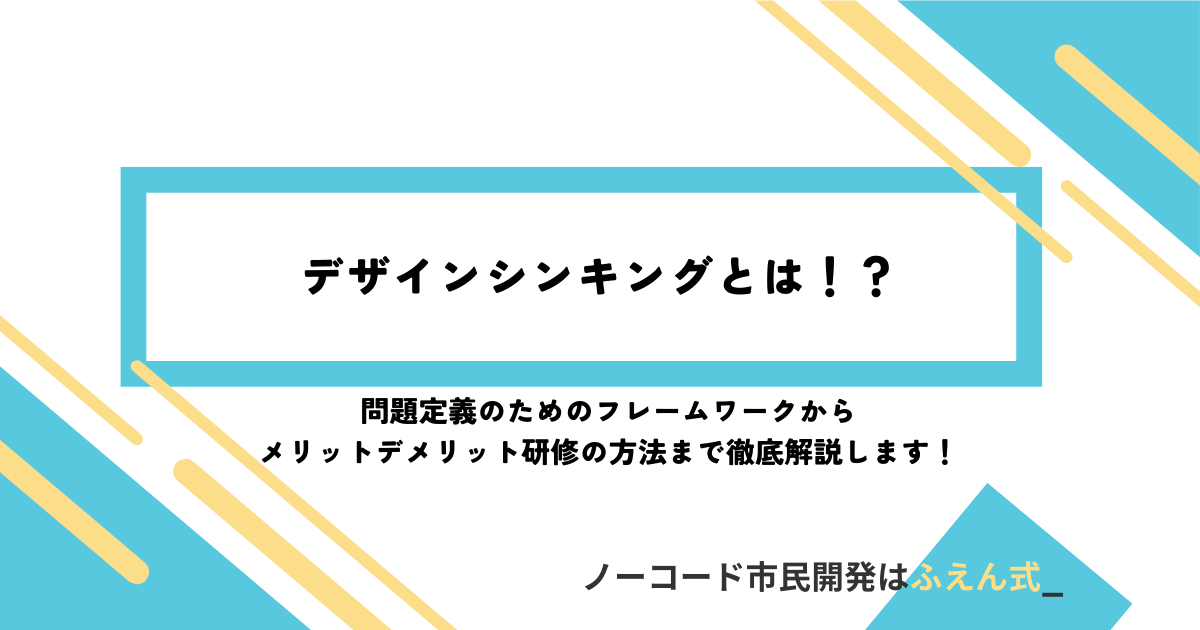デザインシンキングという言葉を研修や日常の情報収集の中で耳にすることがあるのではないでしょうか。
デザインシンキングとは、ユーザーのニーズや感情に共感しながら、問題を定義し、アイデアを発想し、プロトタイプを作り、テストを行うという、問題解決プロセスのことで、イノベーション創出に役立つ思考法や手法のことです。
この記事では、デザインシンキングの概念やステップ、メリットやフレームワーク、研修の方法などを詳しく解説していきます。
DXやオープンイノベーションはもとより、ビジネスパーソンとして非常に重要な思考法ですので、ぜひ最後までお読みください。
デザインシンキングとは?

この章では、デザインシンキングの概要やデザインとの違いについて解説します。
デザインシンキングとは
デザインシンキングとは、ユーザーの視点に立って、問題を発見し、解決することを意味し、ユーザーのニーズや感情を理解し、それに応えることが重要という考え方です。
デザインシンキングは、既存の枠組みや制約にとらわれず、多様な視点やアイデアを持ち寄り、試行錯誤を繰り返しながら、最適な解決策を探求することを特徴とする考え方です。
デザインシンキングの歴史
デザインシンキングの概念は、1970年代にスタンフォード大学のデザイン教育者であるロバート・マッキムによって提唱されました。
マッキムは、デザイン思考を「人間の能力の一つ」として捉え、誰もがデザイン思考を学び、実践できると主張しました。その後、デザインシンキングは、スタンフォード大学のデザインスクール(d.school)やアイデオ社などのデザインコンサルティング会社によって発展し、具体的な手法やフレームワークが開発されました。
現在では、デザインシンキングは、グーグルやアップルなどのイノベーティブな企業や、国連や世界銀行などの国際機関など、さまざまな組織で導入されています。
デザインとデザインシンキングの違い
デザインとデザインシンキングは、包含関係にあります。
デザインとは、ユーザーのニーズや感情に応えるために、形や機能を創造することです。
デザインシンキングとは、デザインをする際のユーザーのニーズや感情に応える、という部分を思考法として確立したものです。
デザインシンキングの5つのステップ

デザインシンキングのプロセスは、5つのステップに分けられます。それぞれのステップには、特定の目的や方法があります。
デザインシンキングのステップは、線形ではなく、反復的です。つまり、前のステップに戻ったり、複数のステップを同時に行ったりすることができます。
この章では、デザインシンキングの5つのステップについて解説します。
観察・共感(Empathize)
観察・共感とは、ユーザーのニーズや感情を理解するために、ユーザーの観察やインタビューなどの調査を行うステップです。
観察・共感の目的は、ユーザーの視点に立って、問題を発見することです。
観察・共感の方法は、以下のようなものがあります。
- ユーザーの行動や環境を観察する
- ユーザーに直接ヒアリングをする
- ユーザーの体験や感情を表現するフレームワークを使い、可視化する
(例:ペルソナ、ジャーニーマップ、共感マップなど)
- ユーザーの立場になって体験する
観察・共感のステップでは、ユーザーの声やデータだけでなく、ユーザーの背景や動機、価値観なども考慮する必要があります。
観察・共感のステップで得られた情報は、次のステップである定義に活用します。
定義(Define)
定義とは、観察・共感で得られた情報を分析し、問題を明確に定義するステップです。
定義の目的は、ユーザーのニーズや感情に応えるために、解決すべき問題を特定することです。
定義の方法は、以下のようなものがあります。
- 観察・共感で得られた情報を整理する(例:アフィニティ図法、KJ法など)
- 問題の本質や原因を探る(例:5W1H法、なぜなぜ分析など)
- 問題を明確に表現する(例:ASIS/TOBE、ポイント・オブ・ビューなど)
- 問題に対する仮説や目標を設定する
定義のステップでは、問題を具体的かつユーザー中心に定義します。
定義のステップで得られた問題の定義は、次のステップである着想に活用します。
着想(Ideate)
着想とは、問題の定義に基づいて、多くのアイデアを発想するステップです。
着想の目的は、問題を解決するために、創造的なアイデアを生み出すことです。
着想の方法は、以下のようなものがあります。
- アイデアを自由に発散する(例:ブレインストーミング、ブレインライティングなど)
- アイデアを他者と共有する(例:シェアアウト、ピッチなど)
- アイデアを評価や選択する(例:ドット投票、NUFテストなど)
- アイデアを組み合わせたり、改善したりする
着想のステップでは、アイデアの量や質を高めることを目指します。
着想のステップで得られたアイデアは、次のステップである試作に活用します。
試作(Prototype)
試作とは、着想で得られたアイデアを具体的な形にするステップです。
試作の目的は、アイデアを実際に検証するために、低コストで高速にプロトタイプを作ることです。試作の方法は、以下のようなものがあります。
- アイデアを紙や画材などで表現する(例:ペーパープロトタイプ、ストーリーボードなど)
- アイデアを物やツールなどで実現する(例:ワイヤーフレーム、モックアップなど)
- アイデアをロールプレイやシミュレーションなどで演出する(例:ボディストーミング、サービスサファリなど)
- アイデアを最小限の機能や要素に絞る(例:MVP、MMFなど)
試作のステップでは、プロトタイプの完成度や美しさよりも、プロトタイプの機能やフィードバックを重視します。
試作のステップで得られたプロトタイプは、次のステップであるテストに活用します。
[参考リンク-MPV開発とは!?アジャイル開発との違いや、具体的な進め方、DX推進におけるメリットデメリットまで徹底解説!]
テスト(Test)
テストとは、試作で得られたプロトタイプをユーザーに評価してもらうステップです。
テストの目的は、プロトタイプの効果や改善点を検証することです。テストの方法は、以下のようなものがあります。
- ユーザーにプロトタイプを使ってもらう(例:ユーザーテスト、ユーザビリティテストなど)
- ユーザーの反応や感想を観察や聞き取りする(例:インタビュー、アンケートなど)
- ユーザーのフィードバックを分析や整理する(例:SWOT分析、プラス・デルタなど)
- ユーザーのフィードバックを反映してプロトタイプを改善する
テストのステップでは、ユーザーのニーズや感情に応えることを最優先にします。
テストのステップで得られたフィードバックは、前のステップに戻ってプロセスを繰り返すことで、解決策や価値を高めていきます。
デザインシンキングを活用するメリット

デザインシンキングを活用することで、どのような効果や価値が得られるのでしょうか?
この章ではデザインシンキングを活用するメリットについて解説します。
問題解決の役割
デザインシンキングは、問題解決において、非常に有効な思考法です。
デザインシンキングでは、ユーザーのニーズや感情に共感しながら、問題を定義し、アイデアを発想し、プロトタイプを作り、テストを行うという、創造的なプロセスを経て、より良い解決策を生み出します。
デザインシンキングは、既存の枠組みや制約にとらわれず、多様な視点やアイデアを持ち寄り、試行錯誤を繰り返しながら、最適な解決策を探求するため、問題の本質や原因を見抜き、ユーザーの満足度や忠誠度を高めることができるのです。
イノベーションの創出
デザインシンキングは、イノベーション創出において、非常に有効な思考法です。
デザインシンキングでは、ユーザーのニーズや感情に応えるだけでなく、ユーザーの期待を超えるような、新しい価値やサービスを提供することを目指します。
デザインシンキングは、競合他社との差別化や市場のニッチ化を図ることができるため、社会的な課題や未来の変化にも対応できるような、持続可能で革新的なイノベーションを生み出すことができます。
新規事業や組織への貢献
デザインシンキングは、新規事業や組織において、非常に有効な思考法です。
デザインシンキングでは、ユーザーの視点に立って、ビジネスの課題や目標を設定し、解決策や価値を提案するため、新規事業の成長や収益性を高めることができ、ビジネスモデルや戦略、組織や文化など、ビジネスのあらゆる側面に影響を与えることができます。
DX推進に対する影響
デザインシンキングは、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進において、非常に有効な思考法です。
デザインシンキングでは、デジタル技術やデータを活用しながら、ユーザーのニーズや感情に応えるような、デジタルな価値やサービスを提供することを考える土台となります。
デザインシンキングを活用することで、デジタル化に伴う変化やチャンスに対応できるような、柔軟でスピーディーなDXを推進することができ、DXの成功に必要な、ユーザー中心の思考や行動を促進することができます。
[参考リンク-経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは!?DXとの関連や対策方法までわかりやすく解説します!]
デザインシンキングで活用されるフレームワーク

デザインシンキングで活用されるフレームワークは、問題の定義やアイデアの発想、プロトタイプの作成など、デザインシンキングの各ステップにおいて、効率的かつ効果的に作業を進めることができます。
この章ではそんなデザインシンキングで活用されるフレームワークについて解説します。
デザインスプリント
デザインスプリントとは、グーグルが開発した、デザインシンキングのプロセスを短期間で実施するフレームワークです。
デザインスプリントでは、5日間という限られた時間の中で、問題の定義からプロトタイプのテストまでを行います。デザインスプリントの特徴は、以下の4つです。
- チームで協働することで、多様な視点やスキルを活かす
- ファシリテーターがチームをリードし、作業の流れや時間を管理する
- 決定事項やアイデアをビジュアル化し、共有する
- プロトタイプを作成し、実際のユーザーにフィードバックを得る
デザインスプリントは、新しいプロダクトやサービスの開発や改善において、高い効果を発揮します。
デザインスプリントは、本質的な開発が進まなかったり、各論にこだわってしまって事業が進まないといったリスクを低減し、開発スピードを上げることができます。
バリュープロポジションキャンバス
バリュープロポジションキャンバスとは、ビジネスモデルキャンバスの開発者であるアレクサンダー・オスターワルダーが提唱した、ユーザーのニーズと価値提案の適合性を検証するフレームワークです。
バリュープロポジションキャンバスでは、ユーザーのプロファイルと価値の地図の二つの要素を使って、ユーザーのジョブ(やりたいこと)、ペイン(困っていること)、ゲイン(得たいこと)と、価値の提案の内容や効果、差別化を整理します。
バリュープロポジションキャンバスの特徴は、以下の3つです。
- ユーザーの視点に立って、ユーザーのニーズや感情を深く理解する
- 価値の提案がユーザーのジョブを支援し、ペインを解消し、ゲインを創出することを確認する
- 価値の提案が競合他社と比較して、どのように優れているかを明確にする
バリュープロポジションキャンバスは、ユーザーにとって魅力的で、競争力のある価値の提案を作成するのに役立ちます。
バリュープロポジションキャンバスは、ビジネスモデルキャンバスと連携して、ビジネスモデルの構築や検証にも活用できるため、新規事業開発などに効果的です。
ビジネスモデルキャンバス
ビジネスモデルキャンバスとは、アレクサンダー・オスターワルダーが提唱した、ビジネスモデルを一枚のキャンバスに表現するフレームワークです。
ビジネスモデルキャンバスでは、価値の提案、顧客セグメント、チャネル、顧客関係、収益の流れ、キーリソース、キーアクティビティ、キーパートナー、コスト構造の9つの要素を使って、ビジネスの仕組みや戦略を整理します。
ビジネスモデルキャンバスの特徴は、以下の3つです。
- ビジネスの全体像を一目で把握することができる
- ビジネスの強みや弱み、機会や脅威を分析することができる
- ビジネスの仮説や検証を繰り返すことができる
ビジネスモデルキャンバスは、新しいビジネスモデルの開発や既存のビジネスモデルの改善において、高い効果を発揮します。
ビジネスモデルキャンバスは、バリュープロポジションキャンバスと連携して、ユーザーのニーズと価値の提案の適合性を検証することもできます。
共感マップ(エンパシーマップ)
共感マップとは、ユーザーの感情や思考をビジュアル化するフレームワークです。
共感マップでは、ユーザーの顔写真や名前、役割などを中心に、ユーザーが見るもの、聞くもの、言う・するもの、考える・感じるものの4つの要素を書き出します。
共感マップの特徴は、以下の3つです。
- ユーザーの視点に立って、ユーザーの体験や感情を深く理解する
- ユーザーのニーズやペインポイント、インサイトを発見する
- ユーザーのペルソナやジャーニーマップなどの他のツールと連携する
共感マップは、観察・共感や定義のステップにおいて、ユーザーのニーズや感情に共感することに役立ちます。
共感マップは、ユーザーの声やデータだけでなく、ユーザーの背景や動機、価値観なども考慮することができるようになります。
デザインシンキングの効果的な研修

デザインシンキングの効果的な研修は、デザインシンキングのインプット、アウトプットの2つの要素に分けられます。
この章では、その2つの研修とそれを組み合わせたおすすめの研修方法について解説していきます。
デザインシンキングのインプット
デザインシンキングのインプットとは、デザインシンキングの概念やステップ、メリットやフレームワークなどの知識を入手することです。
デザインシンキングのインプットでは、以下のようなことを行います。
- デザインシンキングの本や動画などの教材やEラーニングを活用する
- デザインシンキングの事例や成功事例を学ぶ
デザインシンキングのインプットの段階では、デザインシンキングの基礎や理論を理解することが重要です。
デザインシンキングのアウトプット
デザインシンキングのアウトプットとは、デザインシンキングの知識を実際の問題解決やイノベーション創出に適用することです。
デザインシンキングのアウトプットでは、以下のようなことを行います。
- デザインシンキングのステップに沿って、自分の関心や課題に取り組む
- デザインシンキングのフレームワークを使って、問題の定義やアイデアの発想などを行う
- デザインシンキングの手法やツールを使って、プロトタイプの作成やテストなどを行う
デザインシンキングのアウトプットの段階では、デザインシンキングの実践や体験を重視することが重要です。
プロトタイプを作るまでのPBLがおすすめ
まず、PBLとは、プロジェクトベースドラーニングの略で、プロジェクトを実行していく中で学習をしたり、学習を定着させることです。
プロトタイプを作るまでのPBLとは、クイックプロトタイピングといった、プロトタイプを作るまでのデザインシンキングの一連の流れを学習することです。
研修方法は以下のような流れがおすすめです。
- Eラーニングによるデザインシンキングのインプット
- 観察・共感のためのペルソナ・共感マップを活用し、現場や市場の課題を特定するワークショップ
- 定義と着想のアウトプットとして、新規事業や業務改善のアイディエーションや企画立案を行うワークショップ
- 試作を実施するために、ノーコードツールを活用したクイックプロトタイピングのを実施
- テストとして、顧客や現場部門にツールを活用したフィードバックを得るフィールドワーク・ラーニングジャーニーを実施
プロトタイプを作るまでのPBLの段階では、チームワークやコミュニケーションを重視することが重要です。
プロトタイプを作るまでのPBLの段階で得られた成果や学びは、自分の仕事や今後のプロジェクトに役立てることができます。
[参考リンク-プロジェクトベースドラーニングとは!?DX人材育成やその研修に必要な概念を理解しよう!]
まとめ
この記事では、デザインシンキングの基本から、研修の方法まで解説しました。
デザインシンキングは問題解決力を高めながら、新規事業や業務改善の根本を支える考え方にもなるので、DX人材育成にとても重要な要素です。
ぜひデザインシンキングを人材育成やDXに取り入れて見てください。