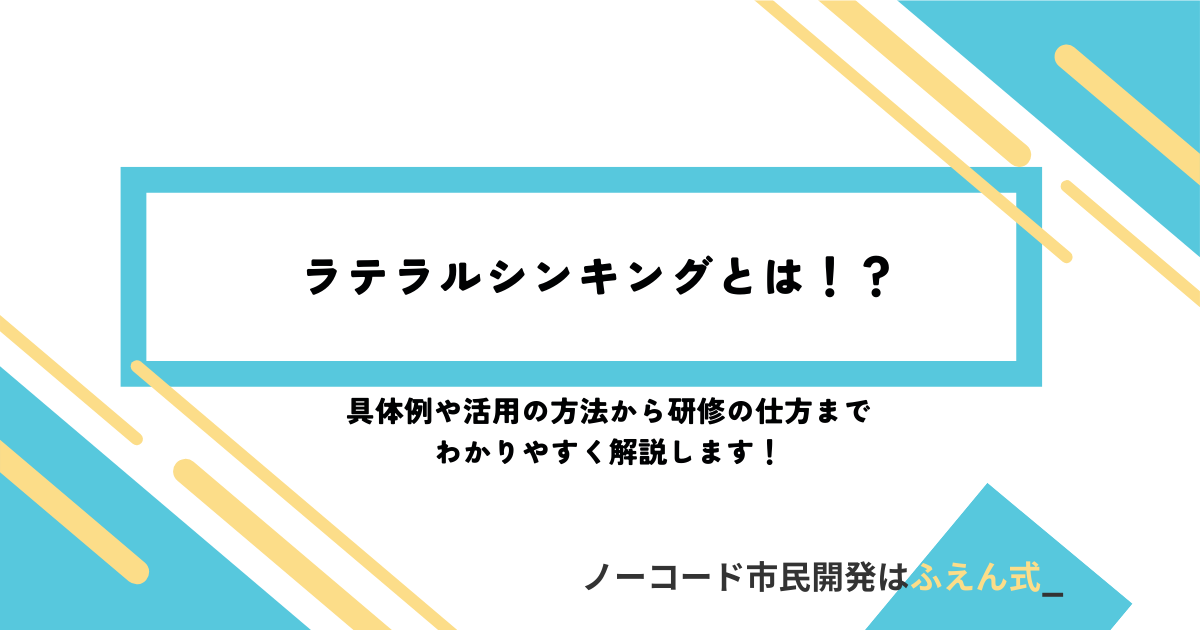ロジカルシンキングと同様、ラテラルシンキングというワードも人材育成やDXの観点で多く扱われるようになっており、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
ラテラルシンキングとは、従来の思考パターンにとらわれずに、新しい視点やアイデアを生み出す思考法です。
ラテラルシンキングは、DXや日常業務での課題解決において非常に強力な思考法なため、各企業では人材育成の項目として取り入れている企業が増えてきています。
この記事では、ラテラルシンキングの定義や特徴、具体例や活用の方法、他の思考法との違い、そして研修の仕方まで、わかりやすく解説しています。
お読みいただくことで、日常業務での活かし方や、具体的な研修の方法まで理解していただくことができるので、ぜひ最後までお読みください!。
ラテラルシンキングとは何か?

ラテラルシンキングの定義と特徴
ラテラルシンキングは、イギリスの心理学者エドワード・デボノ博士によって提唱された思考法です。
デボノ博士は、人間の思考は、慣れ親しんだパターンに沿って、縦に深く掘り下げる傾向があると指摘しました。これをバーティカルシンキングと呼びます。
バーティカルシンキングは、正しい答えを求めるときに有効ですが、新しい発見や創造をするときには不十分でした。
そこで、デボノ博士は、思考を横に広げるラテラルシンキングを提案しました。
ラテラルシンキングとは、従来の思考パターンにとらわれずに、新しい視点やアイデアを生み出す思考法で、思考を横に広げるという意味があります。
ラテラルシンキングの特徴は、既存の枠組みや常識にとらわれないことです。
問題を解決するために、一般的な方法や答えに固執せずに、異なる角度から問題を見つめることができるようになるため、新しい可能性や解決策、いわゆるオープンイノベーションを起こしやすいと言われています。
ラテラルシンキングを活用したDXの具体例
ファミリーマートのファミペイ
ファミリーマートのファミペイは、従来の一般的な考え方である「コンビニ決済は既存の決済方法を活用する」を覆し、ファミリーマートが自社のフィンテックサービスを提供している点で、ラテラルシンキングを活用していると言えます。
Incomeのユニークな保険商品
Incomeは保険商品を提供するNTUC Enterprisesの傘下にある企業で、保険商品の接点を増やし、保険利用の拡大をミッションとしていました。その中で「SNACK」というコーヒーを購入するごとに、自動的に傷害保険に一定額を支払う、といったユーザーのライフスタイルに寄り添った保険商品を開発しました。
これは、従来の一般的な考え方である「保険は定額で引き落とされる商品」であることを覆した点で、ラテラルシンキングを活用していると言えます。
ラテラルシンキングと他の思考法との違い

ラテラルシンキングとロジカルシンキングとの違い
ラテラルシンキングとロジカルシンキングは、思考の方向性や目的が異なります。
ラテラルシンキングは、思考を横に広げることで、新しい視点やアイデアを生み出すことを目的としますが、ロジカルシンキングは、思考を縦に深めることで、正しい答えや論理を導き出すことを目的とします。
しかし、ラテラルシンキングとロジカルシンキングは、相反する思考法ではありません。むしろ、互いに補完する思考法です。
ラテラルシンキングで新しいアイデアを出した後に、ロジカルシンキングでそのアイデアの妥当性や実現性を検証することで、より効果的な問題解決ができます。
[参考リンク-ロジカルシンキングとは!?使われるフレームワークから研修・人材育成の方法まで徹底解説!]
ラテラルシンキングとクリティカルシンキングとの違い
ラテラルシンキングとクリティカルシンキングは、思考の態度や評価基準が異なります。
ラテラルシンキングは、思考の自由度や多様性を重視し、アイデアを評価せずに受け入れます。
ラテラルシンキングでは、アイデアの量や質を高めることや、アイデアを組み合わせたり、発展させたりすることが重要で、発想力や洞察力を高めることに役立ちます。
クリティカルシンキングとは、思考の正確さや妥当性を重視し、アイデアを批判的に分析します。
クリティカルシンキングでは、アイデアの根拠や論理を検証し、誤りや偏見を排除し、判断力や論理力を高めることに役立ちます。
ラテラルシンキングとクリティカルシンキングも、相反する思考法ではなく、互いに補完する思考法です。
ラテラルシンキングで自由にアイデアを出した後に、クリティカルシンキングで批判的にアイデアを評価することで、より効果的な問題解決ができます。
[参考リンク-問題解決に必要なクリティカルシンキングとは!?ロジカルシンキングとの違いや効果的な研修の方法について解説します!]
ラテラルシンキングの3つの要素

前提や固定概念を疑う力
まず1つ目の要素は、前提や固定概念を疑う力です。
人は、想像以上に固定概念や前提といった、いわゆる「色眼鏡」を通して世界を見ています。
「〜であるべき」「〜であるはず」といった考えは、思考を狭め、ラテラルシンキングをすることを難しくします。
この要素はクリティカルシンキングの要素にもつながる重要な要素です。
例えば、今まで活用していたレガシーシステムでしかできないと思われていた業務を疑い、他の解決方法の選択肢はないのか、エクセルのマクロで同じようなことができないか、など考えられることがラテラルシンキングのとっかかりとなるのです。
前提や固定概念を取り外し、課題を捉えることで、新たな課題の解決方法が見えるようになります。
メタ思考(抽象化)
2つ目の要素は、最近書籍等でも話題になっているメタ思考です。
特に物事の「本質」というものを多角的に解釈することが重要です。
例えば、RPAツールとAPIは全く違うものですが、本質として「システムとシステムの機能やデータをつなげる役割」という点で共通項があります。
このようなメタ思考ができると、APIを開発しないと連携は難しい、と思われていた業務フローが、RPAツールによって連携が可能になるのです。
セレンディピティ
3つ目の要素はセレンディピティです。
セレンディピティとは、「偶然から価値を見つける力」と訳される言葉で、偶然をただの偶然ととらえずに、発現した偶然に価値を探せる力とされています。
たとえば、ポストイットなどの付箋は、もともとは接着剤を研究する過程で、粘着力が弱く、接着剤としては失敗だったものから、「適度な接着力で、何度も付け替えることができる」という価値を創出して、生まれたものです。
このように、偶発的に生まれたものから価値を見出すちからがセレンディピティであり、この力がまさにラテラルシンキングの活用となるのです。
ラテラルシンキングの研修の仕方

ラテラルシンキングのインプット
まずラテラルシンキングの研修の第一歩目として、ラテラルシンキングのインプットが必要です。
インプットでは、ラテラルシンキングの概要から、具体的なラテラルシンキングの事例などをインプットし、ラテラルシンキングというものを理解してもらうまでを指します。
これを行うには、Eラーニングなどの動画コンテンツで学習をさせると良いでしょう。
ラテラルシンキングのアウトプット
ラテラルシンキングの研修の次のステップでは、インプットしたラテラルシンキングを活用する実践、つまりアウトプットが必要です。
インプットだけでは、理解できていたとしても、実際の業務やプロジェクトでいきなり活用するのは難しいため、アウトプットを用いて定着と活用を促進します。
簡単に行えるものだと、ウミガメのスープといったゲームを活用したり、「なぞかけ」を活用したメタ思考のトレーニングを行うことも効果的です。
ラテラルシンキングのアウトプットには、課題解決のアイディエーションがおすすめ
先ほどラテラルシンキングのアウトプットについて触れましたが、アウトプットとDX推進を両軸で進めることができるように、DXにおける課題解決のアイディエーションのアウトプット研修がおすすめです。
このアウトプットを行う際には、多くのDXの事例をインプットした上で行うのが重要です。
多くの事例を見た上で、、DXというものをメタ思考で抽象化し、自分の取り組んでいる業務の当たり前を疑い、見えてきた課題に対して、抽象化したDXをどのように当てはめるかを考える。
といったように、DXにおける課題解決のアイディエーションには、ラテラルシンキングに必要な要素が詰まっています。
ぜひラテラルシンキングのアウトプットとして、活用してみてください。
まとめ
この記事ではラテラルシンキングの概要から、具体的な研修の方法まで徹底的に解説しました。
ラテラルシンキングはDXにおいても非常に有効な思考法であり、その研修にDXを絡めることで、人材育成とDXを両軸で進めることができるものでした。
ぜひこの記事を参考にして、DXも人材育成も成功に繋げていただければ幸いです。
あなたのDX推進に幸あれ!