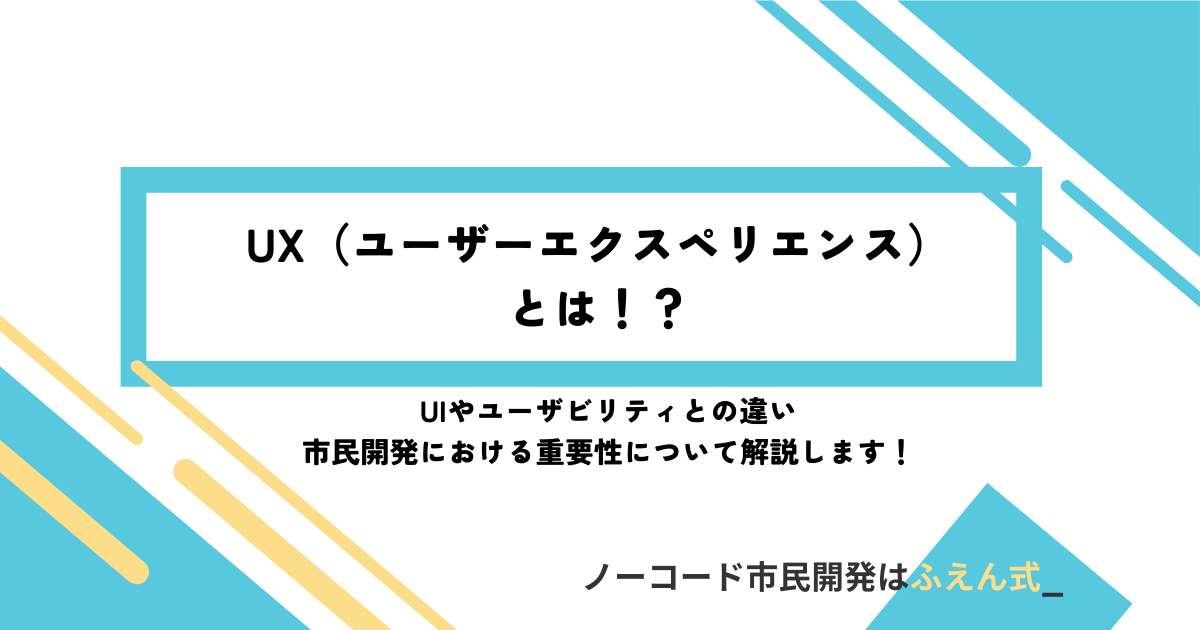多くのウェブサイトやアプリがあふれる現代、ユーザーがどのような体験をするかが重要です。そんな中で、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」が注目を集めています。
この記事では、UX(ユーザーエクスペリエンス)とは何か、その概要やUIやユーザビリティ、CXという言葉と、それらとUXとの違い、そしてなぜ今、注目されているのかについて詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みください。
UXとは

UXの概要
UX(ユーザーエクスペリエンス)は、利用者の体験価値を指す言葉です。
User eXperienceの略称であり、利用者が製品やサービスを利用する際に得る喜びや価値を示します。
ただし、UXは単に利用した瞬間だけの喜びや価値だけではなく、利用によってもたらされる様々な価値や喜びを包括した考えです。
その価値や喜びには、事前の期待感や利用後の爽快感、さらには長期間利用することによる満足度などが含まれます。
UXを考慮すること、すなわちUXデザインは、これらの価値や喜びを最大限に引き出すことを意味します。
UXは単なる利用者の感情だけでなく、製品やサービスが提供する体験全体を網羅し、その品質や価値を評価するための重要な概念です。
UXと混同される用語
UXはしばしば他の用語と混同されますが、以下のような違いがあります。
UI(ユーザーインターフェイス)との違い
UI(ユーザーインターフェース)とは、JIS Z 8520:2022によれば、”ユーザーがインタラクティブシステムで特定のタスクを達成するための情報及び制御を提供する、インタラクティブシステムの全ての部品からなる集合”とされています。
この定義から分かるように、UIはユーザーがデバイスやシステムとやり取りするためのインターフェース部分を指し、例えば、スマートフォンの画面やテレビのリモコンがそれに当たります。
一方、UX(ユーザーエクスペリエンス)は、「ユーザーの認知と知覚」のことを指します。
これはユーザーが製品やサービスを利用する際に心理的に経験する内容を指し、UIとは異なり目に見えたり触れたりするものではありません。
UXはユーザーが感じる満足度や喜び、ストレスの度合いなど、利用者の内部で起こる体験に焦点を当てます。
つまり、UIは外部から見えるインターフェースの側面を指し、ユーザーがシステムやデバイスとやり取りする手段のことであり、一方で、UXは内部のユーザーの体験や感情を指し、ユーザーがその製品やサービスを利用することによって得る喜びや価値を表します。
このように、UIとUXは異なる側面を持ちながら、ユーザーが製品やサービスをどのように体験するかを総合的に評価する重要な概念です。
CX(カスタマーエクスペリエンス)との違い
UX(ユーザーエクスペリエンス)と混同されやすい言葉にCX(カスタマーエクスペリエンス)がありますが、両者には重要な違いがあります。
CXの「カスタマー」という言葉は「顧客」という意味を持ちますが、その範囲は「サービスや製品に関わる全てのターゲット」を指します。一方、UXの「ユーザー」は特定のサービスや製品の利用者を指します。
UXは、ユーザーが特定のサービスや製品を利用することによって得る体験全般を指すのに対し、CXは直訳すると「顧客体験価値」という意味であり、サービスや商品に関わるあらゆるタッチポイントやチャネルにおいて顧客が感じる「ブランドらしさ」などを含めた体験の総称です。
つまり、UXは特定のサービスや製品の利用者が直接的に経験する体験に焦点を当てていますが、CXはより広い意味での顧客体験全体を包括しています。
この違いを理解することで、製品やサービスの改善において、適切なアプローチを取ることができます。
UXが注目される背景
最近、UXが注目されている背景には、以下のような要因があります。
顧客の価値観の多様化
ソフトウェアの利用者にとって、価値や満足度は単なる機能的な評価に留まりません。
利用者の好みや感情、期待など、様々な要因が影響を与えます。
つまり、同じ機能を持つソフトウェアであっても、利用者が変われば価値や満足度は大きく異なります。また、同じ利用者でも、利用シーンによって評価が変わる可能性があります。
このような個々の価値観の多様化に対応することが求められており、利用者が多様化する現代において、ソフトウェアやサービスを提供する側は、それぞれの利用者のニーズや価値観を理解し、最適な体験を提供する必要があるのです。
購買プロセスの変化
過去においては、購買行為は主に対面で行われることが一般的でした。しかし、近年では電話やインターネットを介した購買が増え、利用する機器もガラケーからPC、そしてスマートフォンへと変化してきました。
このような変化に伴い、購買に至るまでのプロセスや環境、購入のきっかけ、購入後のサポートなど、すべての段階が大きく変化しています。
特に、コロナ禍の影響により、非接触型の購買プロセスへの需要が高まっています。
これらの変化を踏まえて、利用者の購買行動を正しく理解し、適切に対応することが求められています。
購買プロセスの変化を正確に把握し、適切に対策を講じるためには、利用者と利用シーンを明確に把握することが不可欠です。
このような情報をもとに、企業やサービス提供者は購買プロセスの変化に柔軟に対応し、顧客満足度を向上させる戦略を構築する必要があります。
サービスのコモディティ化
顧客の価値観の多様化と購買プロセスの変化が進む中、商品やサービスにも大きな変化が求められています。
市場では、顧客の期待に応えるために多種多様な商品やサービスが生まれており、新しい商品やサービスを生み出す環境も整っているため、新しい商品やサービスの生産性向上と共に、コモディティ化の傾向も顕著になっています。
コモディティ化の影響により、市場には類似した商品やサービスが溢れ、価格競争などの問題が生じています。
競争が激化する中、差別化を図るための努力が提供者に求められます。
従来は品質や機能による優位性が競争力を生み出す場合もありましたが、コモディティ化が進んだ商品やサービスではそれだけでは不十分です。
競争優位性を確保するためには、提供者は利用者の視点から新たな価値を生み出す必要があります。
利用者が求める体験やニーズに焦点を当て、それに応じたサービスや製品を提供することが求められます。
このような取り組みが、コモディティ化に対抗し、市場での差別化を実現する重要な手段となっているのです。
デバイスの多様化
利用者を取り巻くデバイスも大きく変化しています。
特にIoTデバイスはインターネットに接続することで、これまで考えられなかった新しい機能やサービスを提供できるようになりました。
さまざまな行動様式や文化、好みが多様化する中で、利用者に対応するためにはさまざまな新しいデバイスやデバイス同士の組み合わせが生まれ、利用環境は複雑化しています。
また、通信環境が4Gから5Gに切り替わることで、ますますの可能性が広がりました。
これにより、利用者のデバイス利用環境を想定し、それに適したサービスを提供する必要が生じました。
新しいデバイスやそれらの組み合わせを利用者の視点で価値を生み出すように考えることが重要です。
これらの背景から、利用者の体験価値であるUXに注目が集まっています。
デバイスの多様化に対応し、利用者にとってより価値のある体験を提供することが求められているのです。
UXと市民開発

UXのユーザーは顧客だけではない
UXにおけるユーザーを顧客(クライアントまたはカスタマー)だけと認識されがちですが、提供するサービスまたはシステムにおけるユーザーという観点では、社内の業務アプリケーションを利用する社員もユーザーにあたります。
市民開発には、自社の社員が、自社における業務アプリケーションを開発することも含まれ、そうした場合、ユーザーの考え方は自社の社員にも適用されるのです。
[参考リンク-市民開発とは!?内製化を目指すための具体的な進め方やメリット・デメリットを徹底解説!]
UXデザインはデザイナーだけの仕事ではない
市民開発においても、UXデザインはデザイナーだけの仕事ではありません。
経済産業省の定めるデジタルスキル標準では、デザイナーという人材類型の中に、UXデザイナーというロールが定義されており、一般的にUXデザインはデザイナーがするものだとされています。
しかし、UXデザインとその根幹にあるデザイン思考はすべてのサービス提供者にとって必要な考え方とされ、DXリテラシー標準の「顧客・ユーザーへの共感」のスキル項目として定義されています。
このことから、社内の業務アプリケーション等を開発する市民開発者においても、UXデザインの概念は重要だと考えられます。
ユーザーが使いやすく、かつそれを活用することで満足度が高まったり、生産性が向上したり、働き方より良くなるようなシステムのその先のことまで考えられる力が求められるのです。
[参考リンク-経済産業省が提唱するDXリテラシー標準とは!?策定された背景やITパスポートとの関係まで徹底解説!]
UXを意識していないシステムは活用されない
顧客の価値観の変化の章で、UXをしっかり設計しないと競争が激化する世の中で活用してもらうことが難しいことに触れましたが、
市民開発においても、UXを意識していないシステムやサービスは利用者から敬遠され、活用されません。
これはUIにおいても同じことが言えますが、ユーザーの利用する状況やなども鑑みた上で、どんなデバイスで使えたらいいのか、どんな操作方法で使えたらいいのか、など、今の業務がよりよくなることを一番に考えた上で、開発をする必要があります。
UXデザインを向上するためのアプローチ

製品やシステムを作るより、顧客体験を作る意識を持つ
良いソフトウェアを生み出すためには、それ自体の完成度よりも利用者が得る価値を重視することが重要です。
開発者のこだわりや携わるポジションによって求められる内容は異なりますが、単に機能の実装にとどまらず、利用者が実際に使った際の体験や価値を重視する意識を持つことが必要です。
ユーザー視点を持つ
ソフトウェアを開発する上で、利用者の気持ちを理解することが重要です。
加えて、利用者を単なる層や集団として捉えるのではなく、個々の利用者の背景や特徴を考慮する観点も重要です。
利用者像を具体的にイメージすることで、利用者のニーズや気持ちをより深く理解することが可能です。
ユーザー視点を持つための手法の1つとして、ペルソナ手法があります。
ペルソナは、仮想の利用者像として設定される人物で、風貌、名前、年齢、性別、居住地、性格、趣味、ポリシーなどが具体的に設定されたものです。
このように利用者像を明確にすることで、開発者はより具体的な利用者像を共有し、ユーザー視点をプロジェクト内で一貫して適用することができます。
利用するシーンに配慮した仕組みを作る
ソフトウェアを開発する際、利用者が実際にどのような状況でそのソフトウェアを利用するかを把握し、その利用シーンに合わせた環境提供を行うことが重要です。
まず、適切なペルソナを用意し、利用者とソフトウェアの関係を利用文脈として考えます。
利用文脈は、利用者がソフトウェアをいつ、どのように利用するかを定義したもので、この文脈に基づいてソフトウェアの機能や設計を考えることができます。
利用文脈を考慮することで、矛盾のない仕組みを作ることが可能になります。
利用シーンは、最初にシナリオとして作成されますが、伝達方法や共有方法としてさまざまな手法が活用されることもあります。
利用者の気持ちに配慮し、利用シーンに合わせた環境を作るための設計を行うことで、利用者が快適にソフトウェアを利用できるような環境を提供することができます。
UXに配慮したソフトウェア作成には、利用するシーンに配慮した仕組み作りが不可欠です。
[参考リンク-デザインシンキングとは!?問題定義のためのフレームワークからメリットデメリット、研修の方法まで徹底解説します!]
まとめ
この記事では、UX(ユーザーエクスペリエンス)の概要や他の用語との違い、市民開発における重要性について解説しました。
是非、この記事を参考にして、自身のプロジェクトやビジネスにおけるUXを向上させてください。
あなたのDX推進に幸あれ!