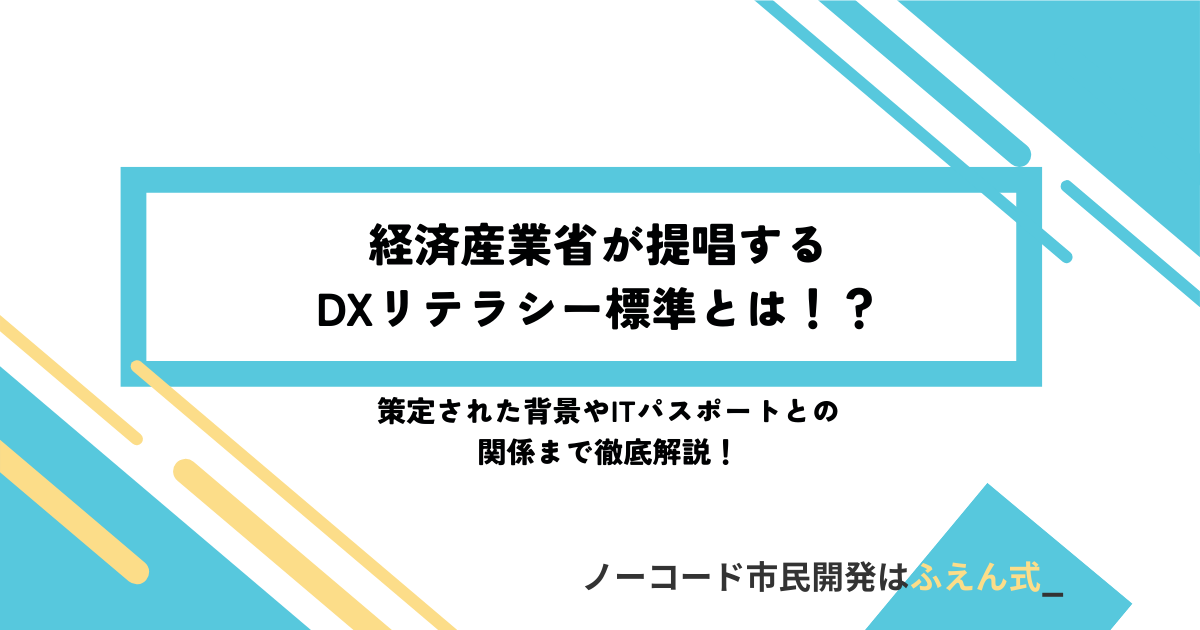デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の競争力を高め、持続可能な成長を実現するために不可欠です。
この記事では、経済産業省が策定した「DXリテラシー標準」について、DXを推進する上での個人の役割や、ITパスポートとの関連性について解説します。
また、DXリテラシー標準の市民開発への取り入れ方・考え方についても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
DXリテラシー標準とは

DXリテラシー標準の概要
DXリテラシー標準は、2022年に経済産業省が策定したデジタルスキル標準に内包される標準のひとつで、ビジネスパーソンがDXに参画し、その成果を仕事や生活で役立てるために必要なマインドセットやスキルを示した指針です。
いわゆる”DXの自分ごと化”をするために必要なスキルや知識・マンドセットを23項目で整理したものです。
DXリテラシー標準の周辺用語
デジタルガバナンスコード
デジタルガバナンスコードとは、デジタル化が進む「Society5.0」において、企業価値を高めるために実践すべき指針を示すものです。
経済産業省によって2020年11月に策定され、2022年9月にはその内容が「デジタルガバナンス・コード2.0」として更新されました。
このコードは、企業の規模や法人形態、個人事業主の有無に関わらず、すべての事業者に適用される考え方です。
デジタルガバナンスコードは、基本的事項、望ましい方向性、具体的な取り組み例の3つの部分に分けられており、デジタルトランスフォーメーション(DX)と密接に関連しています。
[参考リンク-デジタルガバナンスコードとは!?ガイドラインの概要から改訂された内容まで徹底解説!]
デジタルスキル標準
デジタルスキル標準は、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で不可欠な知識やスキル・マインドセットなどを定義したものです。
経済産業省によって2022年12月に策定されました。
この標準は、DXリテラシー標準とDX推進スキル標準の二つの標準を内包しており、それぞれが異なる対象と目的を持っています。
[参考リンク-IPAの提唱するデジタルスキル標準とは!?概要からITパスポートとの違いまで徹底解説します!]
DX推進スキル標準
DX推進スキル標準は、デジタルスキル標準に内包されているもう一つの標準で、DXを実際に推進する役割を担う人材に焦点を当て、そのために必要なスキルセットを5つの人材類型で整理したものです。
これは、デジタル技術を駆使するために必要な人材がどのようなものか、という枠組みと捉えることができます。
[参考リンク-経済産業省が提唱するDX推進スキル標準とは!?5つの人材類型や市民開発・ノーコードとの関連について徹底解説!]
DXリテラシーを身につけた人材のイメージ

出展:経済産業省
DXリテラシー標準を身につけた人材のイメージは、「DXを自分ごと化し、変革に向けて行動ができる」人材とされています。
具体的には、上記の画像ように、なぜDXを重要視しているのかを理解できていたり、自身の業務に対してどのようにデジタルを活用すれば良さそうかなどがわかる状態です。
DXリテラシー標準が求められる背景
DXを加速するためにビジネスパーソン一人一人の自分ごと化が必要
DXを成功させるためには、従業員の一人ひとりがDXを「自分ごと」として捉え、主体的に学び、行動することが求められます。
従業員がDXを自分ごと化することで、ツールの導入がスムーズになったり、現場課題の解決を早いサイクルで行うことができるようになるとされています。
逆に言えば、DXを自分ごと化できていない従業員がいることで、ツール導入が遅れたり、現場課題が見過ごされたり、DXを阻害する要因にもなっているとも言われています。
個人におけるDXリテラシー標準に沿った学びの重要性
個人にとっては、DXに取り組む上でDXリテラシー標準に沿って学ぶことで、必要な知識を体型立てて学ぶことで効率的に変わりゆく世の中に適応していくことができます。
また、体型立てられているDXリテラシー標準に沿って学ぶことで、DXや最新技術に対してアンテナを立てられるようになったり、日々生まれる新たな技術・言葉の内容や意味を自ら調べる姿勢が求められるようになるとされています。
つまり、デジタルや新しいビジネスの潮流に対して学んだり、リスキリングしたりする土台となるのです。
組織におけるDXリテラシー標準に沿った学びの重要性
組織にとっては、DXに取り組む上でDXリテラシー標準に沿って学ぶことで、階層ごとに以下のようなメリットを享受することができます。
- 経営層:自社に必要なDXを思案し、社員に提示することができる
- 事業や業務に知見のある従業員:企業や組織におけるDXの可能性の発掘ができ、DXが進みやすくなる
- 全従業員:DX推進に伴って発生する組織や業務への変化への受容性が高まる
DXリテラシー標準を構成する要素

マインド・スタンス
マインドスタンスは以下のように整理されています。
| 項目 | 内容 | 習項目例 |
|---|---|---|
| 変化への適応 | ・環境や仕事・働き方の変化を受け入れ、適応するために自ら主体的に学んでいる ・自身や組織が持つ既存の価値観の尊重すべき点を認識しつつ、環境変化に応じた新たな価値観、行動様式、知識、スキルを身につけている | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
| コラボレーション | ・価値創造のためには、様々な専門性を持った人と社内・社外問わずに協働することが重要であることを理解し、多様性を尊重している | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
| 顧客・ユーザーへの共感 | ・顧客・ユーザーに寄り添い、顧客・ユーザーの立場に立ってニーズや課題を発見しようとしている | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
| 常識にとらわれない発想 | ・顧客・ユーザーのニーズや課題に対応するためのアイデアを、既存の概念・価値観にとらわれずに考えている ・従来の物事の進め方の理由を自ら問い、より良い進め方がないか考えている | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
| 反復的なアプローチ | ・新しい取組みや改善を、失敗を許容できる範囲の小さいサイクルで行い、顧客・ユーザーのフィードバックを得て反復的に改善している ・失敗したとしてもその都度軌道修正し、学びを得ることができれば「成果」であると認識している | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
| 柔軟な意思決定 | ・既存の価値観に基づく判断が難しい状況においても、価値創造に向けて必要であれば、臨機応変に意思決定を行っている | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
| 事実に基づく判断 | ・勘や経験のみではなく、客観的な事実やデータに基づいて、物事を見たり、判断したりしている ・適切なデータを用いることにより、事実やデータに基づく判断が有効になることを理解し、適切なデータの入力を意識して行っている | 各自が置かれた環境において目指すべき具体的な行動や影響例 |
マインド・スタンスでは、DXを自分ごと化するために必要なマインドや姿勢が整理されており、このマインドをもつことで、ようやくDXに対して向き合うことができるとされています。
逆に言えば、このようなマインドや姿勢を持ち合わせていないと、DXに向き合うことが難しいとも言えます。
Why
Whyは以下のように構成されています。
| 項目 | 内容 | 学習項目例 |
|---|---|---|
| 社会の変化 | 世界や日本社会におきている変化を理解し、変化の中で人々の暮らしをよりよくし、社会課題を解決するためにデータやデジタル技術の活用が有用であることを知っている | ・メガトレンド・社会課題とデジタルによる解決(SDGs 等) ・日本と海外におけるDXの取組みの差 ・社会・産業の変化に関するキーワード(Society5.0、データ駆動型社会 等) |
| 顧客価値の変化 | 顧客価値の概念を理解し、顧客・ユーザーがデジタル技術の発展によりどのように変わってきたか(情報や製品・サービスへのアクセスの多様化、人それぞれのニーズを満たすことへの欲求の高まり)を知っている | ・顧客・ユーザーの行動変化と変化への対応 ・顧客・ユーザーを取り巻くデジタルサービス |
| 競争環境の変化 | データ・デジタル技術の進展や、社会・顧客の変化によって、既存ビジネスにおける競争力の源泉が変わったり、従来の業種や国境の垣根を超えたビジネスが広がったりしていることを知っている | ・デジタル技術の活用による競争環境変化の具体的事例 |
DXがなぜ必要なのか、その背景にある社会的、経済的な変化を理解することがWhyで抑えるべき要点です。
この3つの変化を通して「DXはやらないといけない!」と思えることが重要です。
What
Whatは以下のように構成されています。
| 項目 | 内容 | 学習項目例 |
|---|---|---|
| データ:社会におけるデータ | データ」には数値だけでなく、文字・画像・音声等様々な種類があることや、それらがどのように蓄積され、社会で活用されているか知っている | ・データの種類 ・社会におけるデータ活用 |
| データ:データを読む・説明する | ・データの分析手法や結果の読み取り方を理解している ・データの分析結果の意味合いを見抜き、分析の目的や受け取り手に応じて、適切に説明する方法を理解している | ・データの分析手法(基礎的な確率・統計の知識) ・データを読む(比較方法・重複等) ・データを説明する(可視化・分析結果の言語化) |
| データ:データを扱う | ・デジタル技術・サービスに活用しやすいデータの入力や整備の手法を理解している ・データ利用には、データ抽出・加工に関する様々な手法やデータベース等の技術が欠かせない場面があることを理解している | ・データの入力 ・データの抽出・加工(クレンジング・集計等) ・データの出力 ・データベース(データベースの種類、構造 等) |
| データ:データによって判断する | ・業務・事業の構造、分析の目的を理解し、データを分析・利用するためのアプローチを知っている ・期待していた結果とは異なる分析結果が出たとしても、それ自体が重要な知見となることを理解している ・分析の結果から、経営や業務に対する改善のアクションを見出し、アクションの結果どうなったかモニタリングする手法を理解している ・適切なデータを用いることで、データに基づく判断が有効となることを理解している | ・データドリブンな判断プロセス ・分析アプローチ設計 ・モニタリングの手法 |
| デジタル技術:AI | ・AIが生まれた背景や、急速に広まった理由を知っている ・AIの仕組みを理解し、AIができること、できないことを知っている ・AI活用の可能性を理解し、精度を高めるためのポイントを知っている ・組織/社会でよく使われているAIの動向を知っている | ・AIの歴史 ・AIを作るための手法・技術 ・AIの得意分野・限界 ・人間中心のAI社会原則、ELSI ・最新の技術動向(生成AIなど) |
| デジタル技術:クラウド | ・クラウドの仕組みを理解し、クラウドとオンプレミスの違いを知っている ・クラウドサービスの提供形態を知っている | ・クラウドの仕組み(データの持ち方、データを守る仕組み) ・クラウドサービスの提供形態(SaaS、IaaS、PaaS 等) ・最新の技術動向 |
| デジタル技術:ハードウェア・ソフトウェア | ・コンピュータやスマートフォンなどが動作する仕組みを知っている ・社内システムなどがどのように作られているかを知っている | ・ハードウェア(ハードウェアの構成要素、 コンピュータの種類) ・ソフトウェア(ソフトウェアの種類、プログラミング的思考) ・企業における開発・運用 ・最新の技術動向 |
| デジタル技術:ネットワーク | ・ネットワークの基礎的な仕組みを知っている ・インターネットの仕組みや代表的なインターネットサービスを知っている | ネットワークの仕組み(LAN・WAN、通信プロトコル) ・インターネットサービス(電子メール) ・最新の技術動向 |
Whatではデータというものがどんな種類があって、どんな活用がされていて、どんな構造になっているか、というDX推進に欠かせないデータ活用の基礎知識に関するまとまりと、
AIやクラウドといったデジタルにまつわる技術の基礎知識に関するまとまりの2つで構成されています。
How
Howは以下のように構成されています。
| 項目 | 内容 | 学習項目 |
|---|---|---|
| 活用事例・利用方法:データ・デジタル技術の活用事例 | ・ビジネスにおけるデータ・デジタル技術の活用事例を知っている ・データ・デジタル技術が様々な業務で利用できることを理解し、自身の業務への適用場面を想像できる | ・事業活動におけるデータ・デジタル技術 の活用事例 ・生成AIの利用事例 |
| 活用事例・利用方法:ツール利用 | ・ツールの利用方法に関する知識を持ち、日々の業務において、状況に合わせて適切なツールを選択できる | ・日常業務に関するツールの利用方法 ・生成AIの利用方法(指示(プロンプト)の手法等) ・自動化・効率化に関するデジタルツールの利用方法 |
| 留意点:セキュリティ | ・セキュリティ技術の仕組みと個人がとるべき対策に関する知識を持ち、安心してデータやデジタル技術を利用できる | ・セキュリティの3要素 ・ セキュリティ技術 ・個人がとるべきセキュリティ対策 |
| 留意点:モラル | ・個人がインターネット上で自由に情報のやり取りができる時代において求められるモラルを持ち、インターネット上で適切にコミュニケーションできる ・捏造、改ざん、盗用などのデータ分析における禁止事項を知り、適切にデータを利用できる ・データ流出の危険性や影響を想像できる | ・ネット被害・SNS・生成AI等のトラブルの事例・対策 ・データ利用における禁止事項・留意事項 |
| 留意点:コンプライアンス | ・プライバシー、知的財産権、著作権の示すものや、その保護のための法律、諸外国におけるデータ規制等について知っている ・実際の業務でデータや技術を利用するときに、自身の業務が法規制や利用規約に照らして問題ないか確認できる | ・個人情報の定義と個人情報に関する法律・留意事項 ・著作権・産業財産権・その他の権利が保護する対象 ・諸外国におけるデータ規制 ・サービス利用規約を踏まえたデータの利用範囲 |
Howでは具体的にDXで実践されているデジタルやツールに関しての活用事例を理解し、自身の業務への適用のイメージができるようになるためのスキルのまとまりと、
DXを推進する上で留意すべき3つのポイントについてのスキルのまとまりで構成されています。
WhatとHowの違い
DXリテラシー標準においては、実際の業務で知識・スキルを利用できるレベル、すなわち手を動かすことができるレベルまで求めるか否か、といった観点でWhatとHowを区分しています。
Whatに関してはHowより前提となる知識として捉えられており、ベンダーや情シス部門とコミュニケーションをするときに同じレベルで話せるようになるための知識とイメージすることができます。
Howに関しては、実際に業務にDXを適用しようとしたり、アイデアを出すときに必要な知識群として捉えられています。
ITパスポートとの違い

2022年3月11日に発出された「新たなDXリテラシー標準の検討について」という資料で、DXリテラシー標準とITパスポートやG検定といった資格との対応関係が示されました。
これによると、DXリテラシー標準はITパスポートと比べ、システム監査や、ビジネス・財務関連知識、離散数学といった分野以外を包含している形となっており、例えば2進法や16進法といった知識はDXリテラシー標準には含まれていません。
また、DXリテラシー標準では、ITパスポートより広い範囲の知識を必要としており、特にWhatのデータやデジタル技術の文脈のところは、G検定のようなAIに関する知識や、データサイエンティストスキルにあるデータ活用といった知識を必要としています。
DXリテラシー標準はDXを推進する上で必要なスキルを網羅しており、ITパスポートはIT化を進める上で必要なスキルを網羅していると考えられます。
これは、DXがビジネスの変革事態を目的としているという考え方が反映されており、IT化はDXを進める手段のひとつであることがわかります。
DXリテラシー標準の市民開発への活用

DXリテラシー標準には割とレベルが高いことを認識する
市民開発DXリテラシー標準を活用するときには、まずDXリテラシー標準が割とレベルが高いということを理解する必要があります。
特にWhatのデータのまとまりのスキルに関しては、データの分析手法を理解していたり、データの抽出や加工ができるレベルを求めていますが、これを一般社員に求めるにはかなりレベルが高いでしょう。
そのため、DXリテラシー標準の中でも、どこまでを自社に必要とするかの取捨選択をする必要があります。
活用者に求めるレベルはどこまでかを検討する
市民開発DXリテラシー標準を活用するときには、DXリテラシー標準のレベルが高いことを認識した上で、活用するレベルの従業員にどこまで求めるかを検討する必要があります。
前述でも挙げたように、データ分析の手法を理解していたり、データの抽出や加工ができるレベルは、「BIツールを活用したデータドリブン経営を目指している」といった状況でない限り、活用者レベルには求める必要はありません。
また、活用者に市民開発で開発したアプリケーションへの改修をやらせるのか、改修はやらないが改善要望の要求の整理まで求めるのか、ただ活用させるだけなのか、などによって求めるスキルセットは変わってきます。
マインドスタンスは必須
市民開発DXリテラシー標準を活用するときには、マインドスタンスは必須であることを押さえておく必要があります。
特に、以下の3つは押さえておく必要があるでしょう。
- 変化への適応:DXという新たな概念に触れた時に、前向きに捉えられる姿勢
- 反復的なアプローチ:アジャイル型・多産多死の考え方を持ち、失敗を恐れず挑戦する姿勢
- 事実に基づく判断:今までのやり方に固執せず、事実をもとに変化を受け入れる姿勢
この3点を抑えることで、現場への市民開発の浸透をよりスムーズにすることができます。
まとめ
この記事ではDXリテラシー標準について、概要から市民開発への活用について解説しました。
DXリテラシー標準は、個人と組織がDXを推進するための重要な指針であり、この標準に沿って学び、スキルを身につけることで、デジタル化が進む社会での競争力を高めることができます。
ぜひこの記事を参考に、DXや市民開発を成功に導いてください。
あなたのDX推進に幸あれ!