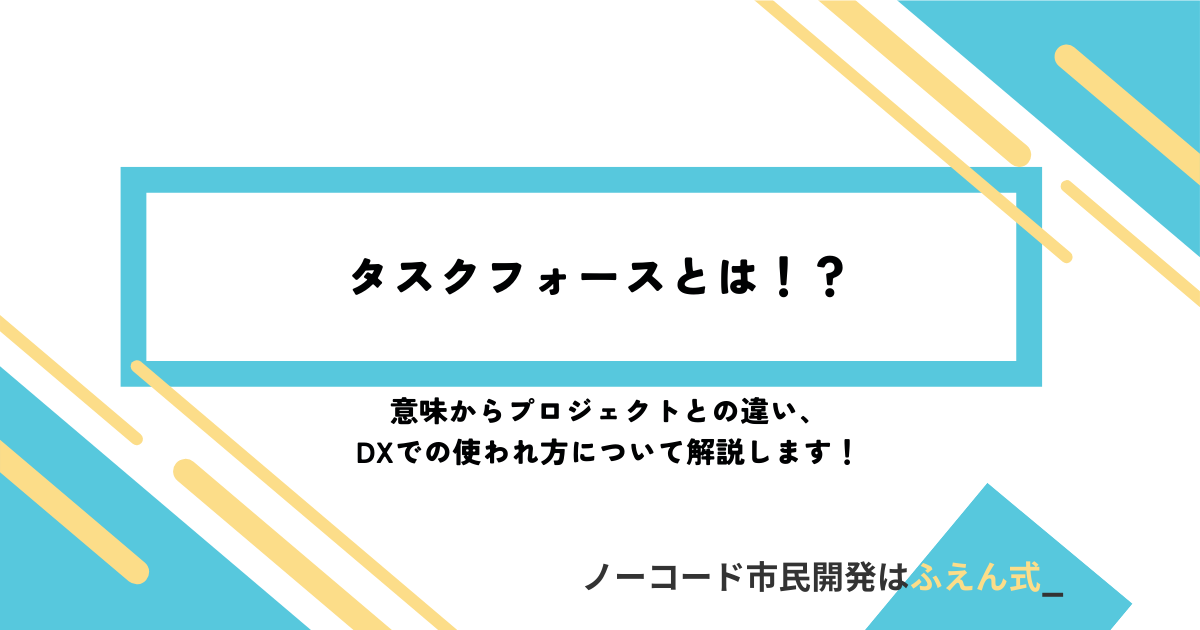ビジネスの世界では、日々様々な課題が発生します。それらの課題に対して、組織はどのように取り組むべきでしょうか?
特に、急を要する問題や、特定の専門知識を必要とする難題に直面した時、通常のチーム構成や業務フローだけでは対応が難しいこともあります。
そんな時に活用されるのが「タスクフォース」です。
この記事を読むことで、タスクフォースが何であるか、そしてそれがどのようにしてビジネスの課題解決に貢献するのかについての理解を深めることができますので、ぜひ最後までお読みください。
タスクフォースとは
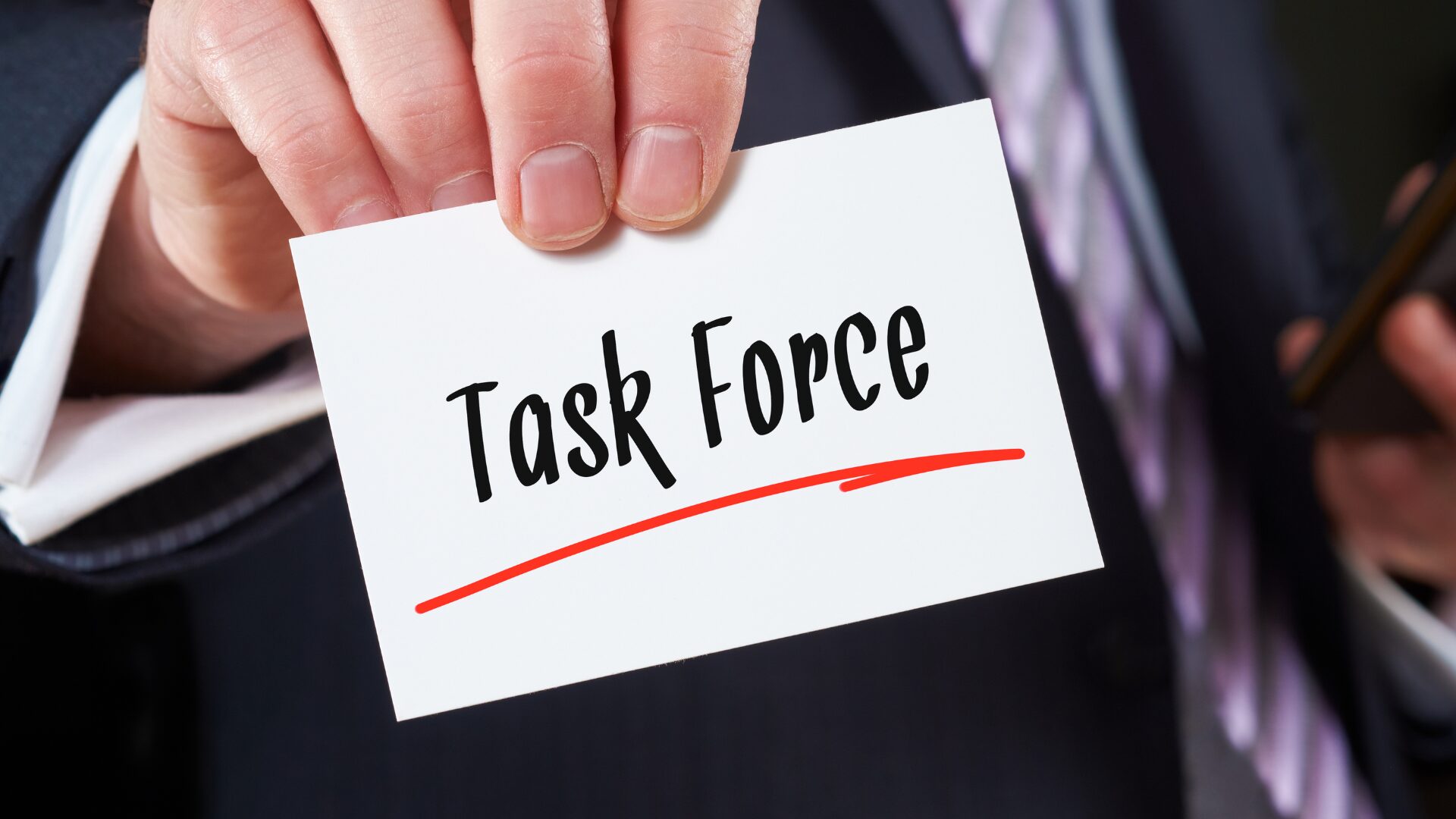
タスクフォースの概要
タスクフォースは、一般的に短期間に集中して特定の目標や課題に取り組むために組織されるチームです。
その目的は、新しいプロジェクトの立ち上げ、緊急の問題への対応、あるいは特定の目標達成のための特別な取り組みなど多岐にわたります。
企業で発生するタスクフォースの多くは、参加するメンバーはタスクフォースに集中する形ではなく、現場の業務と兼務する形で、進められることが一般的です。
タスクフォースと混同される言葉との違い
プロジェクトとタスクフォースの違い
プロジェクトチームとタスクフォースはしばしば混同されがちですが、重要な違いがあります。
プロジェクトチームは通常、より長期間にわたる目標を持ち、複数のフェーズやタスクを含むことが多いです。
一方で、タスクフォースはより短期間で、特定の目標に向けて集中的に取り組む特性があります。
つまり、タスクフォースとプロジェクトでは課題に対して向き合う期間が大きく異なり、また、対象となる課題も緊急度が高いものがタスクフォースなのです。
ワーキンググループ
プロジェクトチームのほかに、タスクフォースと似ている用語で「ワーキンググループ」というものもあります。
ワーキンググループはタスクフォースとほぼ同義語で使われており、特定の問題を解決するために作られるチームのことを指します。
しかし、タスクフォースとワーキンググループには大きな違いがあります。
それは、解決すべき課題や問題の規模です。
タスクフォースは、より大規模で複雑な課題に対処するために組織され、作業ごとに細分化された組織の一部として実行されます。
一方、ワーキンググループは主に、政府系の機関による国家単位での政策や、企業の存続や経営不振などの問題に対応するために活用されることが多いのが特徴です。
要するに、タスクフォースはより大規模で包括的な課題に取り組む際に用いられ、ワーキンググループは特定の問題に対する迅速な対応を目指す際に活用されるのです。
タスクフォースの目的
タスクフォースは、軍事用語から派生し、特定の任務に特化した機動部隊を指す言葉として始まりました。
ビジネス界では、この用語は緊急かつ重要な内部課題に対処するために一時的に形成されるチームを表します。
緊急性の高い課題に迅速に対応する必要があるため、タスクフォースは社内の様々な部署から選ばれた有能なメンバーで構成され、日常業務から切り離されて活動します。
これにより、部門間の連携が促進され、組織全体の問題解決が迅速かつ効果的に行われます。
タスクフォースは、ただ緊急の問題を解決するだけでなく、業務改善や組織改革の実施にも貢献します。
実際に、タスクフォースを通じて業務プロセスを改善し、組織の効率化を実現した企業は数多く存在します。
このように、タスクフォースは一時的ながらも、組織にとって重要な役割を果たすのです。
タスクフォースのメリット

い解決のためにリソースを注ぐことができる
タスクフォースのメリット1つ目は解決のためにリソースを注ぐことができることです。
企業のリソースは有限であるため、どの目的にどれくらい使うのかを適切に見極めることが重要です。ここで、タスクフォースが注目されます。
タスクフォースは、チームとして対応すべき短期的で明確な目的があります。
そのため、ヒト、モノ、カネ、情報といった、その課題を解決するために必要なリソースを効率的に配分できるというメリットがあります。
結成したチームは通常の業務を中断せずに短期間で課題や問題に対応し、スピーディーに解決に向けて取り組むことができる体制を作ります。
組織横断的にメンバーを集めることができる
タスクフォースのメリット2つ目は組織横断的にメンバーを集めることができることです。
タスクフォースは、明確な課題解決を目指すチームであり、その構成においては、必要なスキルセットを持つ適任者を選出することがしやすくなります。
企業内では各部署が専門性に基づいて業務を進めていますが、タスクフォースを利用することで、部門の垣根を越えた多様な専門知識を持つメンバーを一つのチームに集結させることが可能です。
この組織横断的なアプローチは、部門間の利害を超えて共通の目標に集中することを可能にし、課題解決への道をスピーディーに進めることができます。
課題に対して機動力の高い迅速な対応ができる
タスクフォースのメリット3つ目は課題に対して機動力の高い迅速な対応ができることです。
タスクフォースは主に社長やCXO、事業部門長などの直下組織として機能することが多く、意思決定に関するリードタイムが短くなる傾向があります。
それに加えて上記2つのメリットが合わさることで、タスクフォースは、その柔軟な構造と集中的な取り組みにより、迅速かつ機動的に課題に対処することができるのでます。
タスクフォースの進め方

メンバーの選出と各部への協力の依頼
タスクフォースの進め方1つ目はメンバーの選出と各部への協力の依頼です。
各部署から適切な人材を選び出すことで、緊急かつ重要な課題に迅速に対応できるチームを形成します。
さらに、タスクフォースは柔軟性を持ち、プロジェクトの進行に応じて新たなメンバーを追加することが可能です。
これにより、特定の業務に必要な専門性を持つ人材を随時チームに組み入れ、効率的な問題解決を実現します。
ここで重要なのが、タスクフォースのメンバーを選出した部門に協力の依頼とコンセンサスを取ることです。
企業として重要な取り組みではあれ、現場のリソースを一部削減することには変わりないため、後のハレーションを防ぐためにも、現場との調整はしっかりとしておく必要があります。
課題とゴール、スケジュールの明確化
タスクフォースの進め方2つ目は課題とゴール、スケジュールの明確化です。
プロジェクトを進める前に、タスクフォースのメンバーは解決すべき内容や規模感、課題の本質を共有します。
その後、具体的な課題解決のために必要なタスクを設定し、明確に書き出し、ゴールを明確に定義した後、実現までのスケジュールを策定・共有します。
ここで重要なポイントは活動スケジュールは無理のない範囲で設定することです。
権限と裁量の調整と付与
タスクフォースの進め方3つ目は権限と裁量の調整と付与です。
タスクフォースは、タスクの重要度や緊急度に応じて適切な権限を持つことが必要です。
推進者は経営陣にこれを説明し、認識してもらうことが重要です。
タスクフォースは迅速な問題解決を求められるため、計画を立てる際に社内調整や上長の承認に時間を費やすことは避けないと、タスクフォースの良さを発揮することはできません。
そのため、タスク遂行に必要な予算や執行権などの権限も適切に付与するため、経営陣やマネジメント層と調整をする必要があります。
施策の実行
タスクフォースの進め方4つ目は施策の実行です。
タスクフォースにおいて、解決すべき課題とスケジュールを定め、権限を付与した後は、具体的な行動計画を策定し、施策を実行に移します。
多様なバックグラウンドを持つメンバーが一堂に会するため、チームとしての統一感を確立することが必要です。
そのためには、タスクフォースの価値観、目指す方向性、そして遵守すべきルールを事前に定め、全員で共有することが重要です。
タスクフォースは、日常的に密接にコミュニケーションを取っているわけではないメンバーで構成されることが多く、価値観のズレを防ぎ、メンバーの能力を最大限に活かすためには明確なガイドラインが求められます。
開放的で発言しやすい環境を作り、「意見を否定しない」といった基本的なルールを明文化することなどで心理的安全性を確保することが非常に重要になります。
[参考リンク-組織に求められる心理的安全性とは!?DX推進での考え方や確保の方法に言及しながらわかりやすく解説します!]
施策のモニタリング
タスクフォースの進め方5つ目は施策のモニタリングです。
タスクフォースにおける施策の実行中は、継続的なモニタリングが必要となります。
このプロセスにより、課題の現状や解決度合いを客観的に評価することが可能になります。
タスクフォースだけでなく、社内外からの視点で進捗を把握し、成果を定量化することが重要です。
これにより、次の行動計画へと効果的に移行することができます。
また、成功のみならず、失敗からも学ぶことはタスクフォースの重要な側面です。
高い能力を持つ専門家や技術者が集まっていても、予期せぬ結果や課題の悪化が発生することがあります。
失敗の原因を理解し、それを次のステップへと活かすことは、継続的な改善と成長につながります。
施策の振り返り
タスクフォースの進め方6つ目は施策の振り返りです。
タスクフォースの活動完了後は、行った活動と得られた結果の徹底的な振り返りが必要です。
タスクフォースは、緊急性を要する課題に対応するために一時的に組成されるため、課題解決後には速やかに解散することが多いため、得られた成果を長期的なプロジェクトチームに引き継ぐことも多くあります。
この過程で、チーム内で共有された知識や生まれたノウハウ、プロセスが失われがちです。しかし、これらを組織運営に活かすことは、タスクフォースの実施において極めて重要です。
単に課題解決の方法だけでなく、活動中に明らかになった改善点や新たな課題も含め、全体の取り組みを詳細に振り返ることが推奨されます。
これにより、将来同様の課題に直面した際に、迅速な解決策を見出す手助けとなります。
施策で得た成功・ナレッジの共有
タスクフォースの進め方7つ目は施策で得た成功・ナレッジの共有です。
タスクフォースの活動が終了した後は、今回の取り組みを通じて得たノウハウや成果を各部署および組織全体で共有しましょう。
反省点や改善案なども詳細に記録し、検証することが重要です。
これにより、新たな課題が発生した際には過去の成功体験や解決手法を活用できます。
さらに、今後のプロジェクトや企業の経営方針にも有益な資産となるでしょう。
また、プロジェクトチームに引き継ぐ際には、タスクフォースでの成功体験が社内で口コミとなり、よりプロジェクトの推進がしやすくなるといった副次的な効果を得ることにもつながります。
タスクフォースの成功事例

マクドナルド
2015年、マクドナルドは異物混入問題に直面し、これが品質への懸念と危機管理の不備による信頼喪失につながりました。
この危機を受けて、日本マクドナルドは佐藤仁志氏を委員長に迎え、「お客様対応プロセス・タスクフォース」を設立しました。
このチームは品質保証、法務、顧客対応、オペレーションの社内代表者で構成され、消費者視点やソーシャルメディア対応に精通した有識者と危機管理の専門家が外部メンバーとして加わりました。
タスクフォースの目的は、顧客対応プロセスを再検証し、問題を特定してサービス品質を向上させることでした。
その結果、異物の取り扱いと情報伝達の基準を見直し、お問い合わせの情報管理を強化し、未然防止策を講じました。
また、「聞く姿勢、見て頂く姿勢」を重視したコミュニケーション手法を確立し、顧客対応の基準を見直し、一元化することに成功しました。
この取り組みは、危機を乗り越えるためのタスクフォースの効果的な活用例として評価されています。
味の素
味の素は、ASV(Ajinomoto Group Shared Value)を従業員一人ひとりが自分ごとと捉え、組織の実行力を向上させることを目指して、「全社オペレーション変革タスクフォース」を設立しました。
このタスクフォースは、ASVエンゲージメントの向上と個人の能力開発を同期させるため、社員が「食と健康の課題解決」に取り組むマネジメントサイクルを構築し、味の素グループ全体に浸透させることを目的としています。
さらに、サプライチェーンマネジメントの改善、直接・間接材コストの削減、スマートコーポレートの推進などにも取り組んでおり、食品事業本部、アミノサイエンス事業本部、コーポレート本部と緊密に連携し、ビジョン達成に向けた企業文化の変革を推進しています。
DX推進タスクフォース成功の要諦

DX推進タスクフォースで行うこと
DX推進タスクフォースは、デジタル技術を活用して組織の変革を推進するために結成されます。
これには、以下のような活動が含まれます。
- デジタル化戦略の策定: デジタル技術を活用したビジネスモデルの構築や、業務プロセスのデジタル化を計画します。
- 業務改善インフラの改善: 効率的なデータ管理や通信のためのITインフラを整備し、ノーコードツールなど、最新の技術を導入します。
- DXエバンジェリストの育成:各部門でDXを推進できる人材をタスクフォースとして短い期間で育成します。
これらのようにさまざまな目的のDX推進タスクフォースが活躍していますが、これは逆説的に、タスクフォースのように企業の叡智を結集して取り組まないとDXは起こらないということも示唆しています。
課題・ゴールの設定:実現可能性を重視する
DX推進タスクフォースの成功の要諦1つ目は課題・ゴールの設定をする際に、実現可能性を重視することです。
例えば、ノーコード業務改善タスクフォースや、AI活用タスクフォースなどの成功と失敗の概念が存在するタスクに関しては、実現可能性を重視する必要があります。
戦略策定タスク等、アウトプットの質の問題はあれど、成功・失敗の概念がないタスクは該当しません。
これは、そのタスクが失敗した時、そのような取り組みに対するイメージの悪化やレッテルの脅威から逃れるためです。
特に、初めて会社でDXに取り組んだり、初めてツールやAIの活用に取り組む場合は、最初の取り組みの成否が後の取り組みへ多大なる影響を及ぼします。
そのため、投資対効果が大きく、実現可能性が低いよりも、投資対効果は中程度で、実現可能性が高いものをゴールに設定すると良いでしょう。
適切なメンバーの選定
DX推進タスクフォースの成功の要諦2つ目は、適切なメンバーの選定をすることです。
特にDXに関する取り組みでは、参加メンバーに対するスキルに目を向けがちですが、スキルよりも意欲やマインド面を重視することが必要です。
もちろん最低限のスキルも必要ですが、トランスフォームさせるためには、多くの壁が立ちはだかり、特に人や組織に関わる壁が高く聳え立ちます。
その壁を越えようとするマインドがなければ、いくらスキルがあっても壁は乗り越えられません。
そのため、メンバーを選定する際は、意欲やマインドを重視した選抜や選定をすると良いでしょう。
権限・裁量・予算を与える
DX推進タスクフォースの成功の要諦3つ目は、権限・裁量・予算を与えることです。
多くの企業の場合、この3つの出所は経営層や事業部門長にあり、DX推進タスクフォースが組織を横串でアプローチした場合に、承認や認証プロセスで多くのリソースや時間が割かれてしまうことが散見されます。
そして、定められた期間内に結果が出せなくなったり、承認プロセスを得ることが目的となってしまったりと、失敗の入り口になってしますのです。
そのため、事前に経営層とコンセンサスをとり、DX推進タスクフォースに権限・裁量・予算を与えることで、より迅速な課題解決が可能になります。
現場の協力を得やすい環境づくり
DX推進タスクフォースの成功の要諦4つ目は、現場の協力を得やすい環境づくりをすることです。
そもそもタスクフォースに参加しているメンバーは、現業がある中で現場のリソースを減らしてタスクフォースを推進しているため、タスクフォースに対する協力が大前提となります。
また、特に業務改善といった、既存のやり方を変えるような取り組みは、現場からの反発が起きやすいため、この考え方が非常に重要になります。
現場にしっかりと認知をしてもらい、協力を要請できる土壌ができることで、タスクフォースの活動がスムーズに進行し、目標達成に向けて組織全体が一丸となることができます。
まとめ
タスクフォースは、特定の課題に対して集中的に取り組むための強力な手段です。
DX推進においても、タスクフォースは重要な役割を果たします。
上記で述べた進め方やメリット、成功事例を参考にしながら、自組織のタスクフォースを効果的に運用していくことが、今後のビジネスの成功につながるでしょう。
あなたのDX推進に幸あれ!