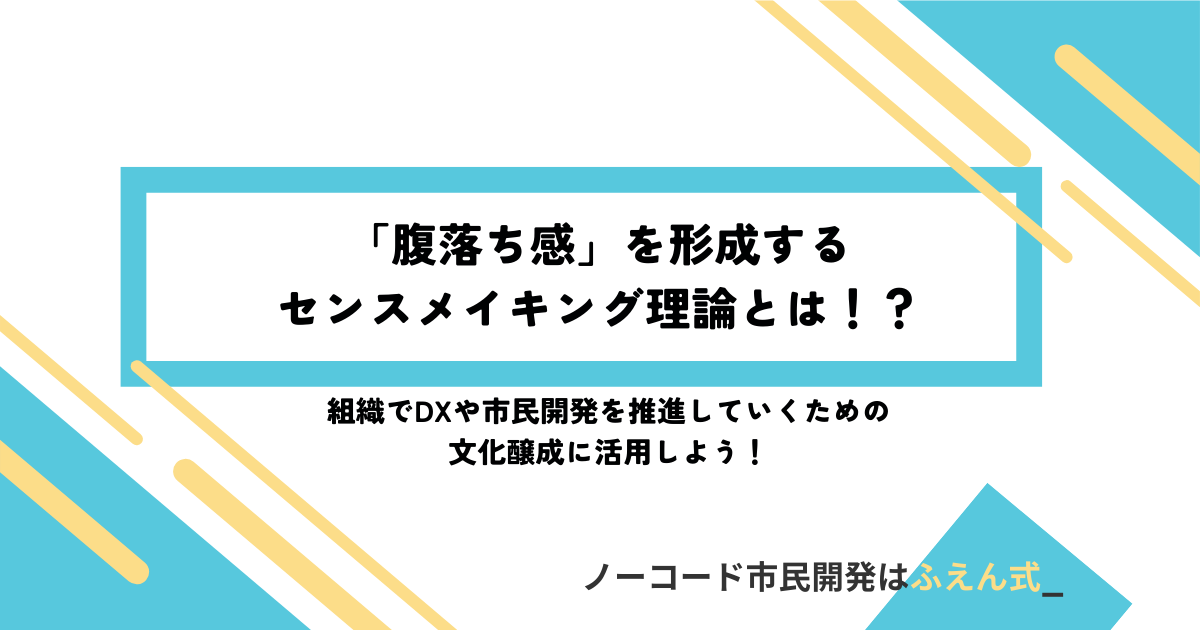組織でDXを推進していくために必要なことは何だと思いますか?
技術的なスキルやツールの導入だけではなく、組織の文化やメンバーのマインドセットも重要な要素ですよね。
しかし、組織の文化やメンバーのマインドセットを変えるのは簡単なことではありません。特に、変化に対して抵抗感や不安を持つ人が多い場合は、なおさら難しいでしょう。
そこで、この記事では、組織でDXを推進していくために役立つ「センスメイキング理論」という概念について解説します。
センスメイキング理論とは、人々が自分の置かれた状況や経験に意味を与えるプロセスのことです。
センスメイキング理論を理解することで、組織の変革や、マインドチェンジのための施策に活用できますので、ぜひ最後までお読みください。
センスメイキング理論とは

この章では、センスメイキング理論について、概要と注目されている背景について解説します。
センスメイキング理論の概要
センスメイキング理論とは、人々が自分の置かれた状況や経験に意味を与えるプロセスのことです。センスメイキングとは、日本語で「意味づけ」と訳されます。
センスメイキング理論は、1980年代にアメリカの組織学者であるカール・ワイックによって提唱された理論です。
ワイックは、人々は自分の行動や判断の根拠となる「腹落ち感」を求めており、そのために自分の環境や経験に対して意味づけをしていると考えました。
センスメイキング理論によると、人々は以下のような要素でセンスメイキングを行っています。
- 環境から部分的な情報を収集する
- 自分のアイデンティティや価値観と照らし合わせる
- 過去の経験や知識と比較する
- 他者とコミュニケーションをとる
- 説得力や納得力のあるストーリーを作る
- そのストーリーに基づいて行動や判断をする
- その結果に応じてストーリーや意味を修正する
それぞれの要素についての詳細は、「センスメイキングの7つの要素」の章で解説します。
センスメイキング理論が注目されている背景
なぜ1980年台に提唱されたセンスメイキング理論が今注目されているのでしょうか?
それは、現代社会が「VUCA」と呼ばれる不確実性、複雑性、曖昧性、変動性の高い環境になっているからです。
VUCAの環境では、予測や計画が困難になり、常に変化に対応しなければなりません。
そのため、人々は自分の置かれた状況や経験に対して、より柔軟に意味づけを行う能力が求められます。
センスメイキング理論は、VUCAの環境において、人々がどのように意味づけを行い、行動や判断をするのかを説明する有効なフレームワークとなります。
また、センスメイキング理論を活用することで、人々は自分の意味づけのプロセスを意識し、改善することができます。
センスメイキングが必要な3つの環境

この章では特にセンスメイキングが重要な3つの環境について解説します。
危機的な状況
危機的な状況とは、突発的で予期せぬ出来事が起こり、人々の安全や生活に大きな影響を及ぼすような状況です。例えば、コロナウイルスによるパンデミックなどが該当します。
組織では、ディスラプターの脅威に晒された時も危機的な状況に該当します。
危機的な状況では、人々は自分の環境や経験が全く通用しない状態にあると感じ、既存の意味づけやストーリーが信じられなくなってしまいます。
そのため、危機的な状況に陥った際には、新たな意味づけやストーリーを創造するためのセンスメイキングをする必要があります。
危機的な状況でセンスメイキングを行うことで、人々は以下のようなメリットがあります。
- 状況の理解や受容がしやすくなる
- 適切な行動や判断ができるようになる
- ストレスや不安を軽減することができる
アイデンティティへの脅威
アイデンティティへの脅威とは、自分の自己概念や自尊感情に関わるような出来事が起こり、人々のアイデンティティが揺らぐような状況です。例えば、個人で言えば失恋や失職、人間関係のトラブルなどが該当します。
組織で言えば、DXによって事業ドメインが多様化し混在化する現代で、自社の立ち位置があやふやになってしまう状態がこれに該当します。
アイデンティティへの脅威では、組織は自社の環境や経験に対して、既存のアイデンティティに合致しない意味づけやストーリーが生じ、自社が提供する価値とは何か、という概念の統一ができなくなる可能性があります。
そのため、自社のアイデンティティに適合する新たな意味づけやストーリーを創造する必要があります。
アイデンティティへの脅威に対してセンスメイキングを行うことは、以下のようなメリットをもたらします。
- 自社のアイデンティティを再構築することができる
- 自社の価値観や目標を明確にすることができる
意図的な変化
意図的な変化とは、自分や組織が望む方向に向かって、積極的に変化を起こそうとする状況です。
例えば、DXによる組織改革、市民開発への取り組み、新しいプロジェクトやイノベーションなどが該当します。
意図的な変化では、人々は自分の環境や経験に対して、既存の意味づけやストーリーが不十分になり、既存の行動から変化できない可能性があります。
そのため、変化をしてもらえるように新たな意味やストーリーを創造する必要があります。
意図的な変化に対してセンスメイキングを行うことは、以下のようなメリットをもたらします。
- 変化に対するモチベーションやコミットメントが高まる
- 変化に対する抵抗感や不安を減らすことができる
- 変化に対する学習や創造性が促進される
[参考リンク-市民開発とは!?内製化を目指すための具体的な進め方やメリット・デメリットを徹底解説!]
センスメイキングの7つの要素

センスメイキングを行うために必要な要素が7つあります。
これらの要素は、センスメイキングのプロセスを分析するための指標となり、要素を意図的に加えることで、センスメイキングの質や効果を向上させることができます。
アイデンティティ
アイデンティティとは、自分が誰であるかという自己概念のことです。
アイデンティティは、センスメイキングの中心的な要素です。なぜなら、人や組織はは自分や自社のアイデンティティに基づいて、自分の環境や経験に意味を与えたり、行動をするからです。
アイデンティティを得ることで、自分や自社の価値観や目標を明確にすることができたり、自分の役割や責任を認識することができるため、腹落ちをする一つの要素となるのです。
回想・振り返り
回想・振り返りとは、自分の過去の経験や知識を思い出すことです。
危機的な状況を乗り越えてきた成功体験や、意図的な変化を続けてきた状況を振り返ることで、これから行なっていく変革の原動力となったり、現在進行形での経験をした後で、しっかりと振り返りをすることで、学びを概念化し、今後に活用できるようになります。
回想・振り返りを活用することで、以下のような効果があります。自分や自社の状況や経験に対する理解や洞察が深まり、自分の置かれている状況や行為によって生まれた経験を学びに昇華することができるようになります。
また、今までの成功経験やうまく行った行動を回想することで、現在や、その先に対して自信を得られます。
行為
行為とは、自分の環境や経験に対して何かはたらきかけることを指します。
この行為が、センスメイキングをもたらす原点になります。
この行為が環境になにか影響を与えることができる唯一の要素であり、行為を活用することで、アイデンティティの確認ができたり、環境情報の部分的感知ができるようになります。
社会性
社会性とは、他者との関係やコミュニケーションをとることで、自身や個人と組織やステークホルダーとの関係性を補足することです。
社会性によって自分の環境や経験に意味づけを行なったり、意味づけを強めたりすることができます。
継続性
継続性とは、行為から始まり、環境情報の部分的感知をし、回想・振り返りをして意味づけを強め、アイデンティティに納得する、といった一連のサイクルを継続することを指します。
継続性を持つことで、意味付けの練度が高まり、腹落ちがより深まります。
環境情報の部分的感知
環境情報の部分的感知とは、自分が行動すること(行為)によって、新たにに触れる情報を感知することを言います。
前提として、人々は自分の置かれている環境から完全な情報を得ることができておらず、行動をして初めてその環境に触れることができるという考え方があります。
環境情報の部分的感知には行為が欠かせないのです。
説得性・納得性
説得性・納得性とは、自分の環境や経験に対する意味やストーリーが他者にも受け入れられることです。
説得性・納得性は、センスメイキングの目的となる要素です。なぜなら、人々は自分の環境や経験に対する意味やストーリーを他者と共有し、共通の理解や行動を促進することを望むからです。
説得性・納得性を獲得するには、ストーリーテリングという考え方を適用することができます。
ただ論理的に話すだけでなく、行為から得た経験や、アイデンティティからくる考えなどをストーリーに載せて伝えることが重要です。
センスメイキング理論とDX

ここまで、センスメイキング理論の概要と要素について説明しました。この章では、センスメイキング理論とDXの関連について解説します。
VUCAの時代とDX
DXは、現代社会がVUCA時代になっていることに対応するために必要な取り組みです。
VUCAの環境では、組織は以下のような課題に直面します。
- 不確実性:将来の予測や計画が困難になる
- 複雑性:組織の内外の要因や関係が多様化し、分析や管理が困難になる
- 曖昧性:組織の目標や方向性が不明確になり、意思決定や行動が困難になる
- 変動性:組織の環境や市場が急速に変化し、対応や適応が困難になる
DXは、これらの課題に対して、デジタル技術を活用して、組織の変化に対応しやすくし、変革を行うことの土台となります。
そしてこのDXにこそ、センスメイキングが必要なのです。
[参考リンク-VUCAの時代とは?生き抜くための方法やアジャイルとの関連までわかりやすく解説!]
DXになぜセンスメイキングが必要なのか
ここまで読んでくださった方なら、もう察しがついているかもしれません。
DXはVUCAの時代という不確実性の高い状況の上で、危機的状況にあり、かつ自社のアイデンティティが脅威に晒されている状態になっているのです。
DXは、デジタル技術の導入だけではなく、組織の文化やメンバーのマインドセットの変革も必要とします。つまり、DXは、アイデンティティへの脅威があり、危機的な状況の中で、意図的な変革を起こすことなのです。
しかし、意図的な変化を起こすために、組織の文化やメンバーのマインドセットを変えるのは簡単なことではありません。
特に、変化に対して抵抗感や不安を持つ人が多い場合は、なおさら難しいでしょう。
そこで、センスメイキング理論が役立ちます。センスメイキング理論は、組織や個人が変化に対応しやすくなり、より効果的な行動や判断ができるようになるためのフレームワークとなるのです。
組織に対してDXをセンスメイキングするには
では、具体的にどのようにして、組織に対してDXをセンスメイキングすることができるのでしょうか?
ここでは、センスメイキングの7つの要素を活用して、組織に対してDXをセンスメイキングするための方法を紹介します。
アイデンティティ
組織や個人のアイデンティティにDXを関連付けることで、DXに対するモチベーションやコミットメントを高めます。
アイデンティティを得る・与える方法としては、自社のパーパスを設定したり、自社のミッション・ビジョン・バリューを浸透させたり、オープンバッジ制度を活用し、メンバーに役割と権限を与えることができます。
回想・振り返り
組織や個人の過去の経験や知識にDXを関連付けることで、DXに対する理解や自身を与えます。
また、DXにおける行為に対して得た環境情報の部分的感知に対して、回想をすることで意味づけを深めます。
回想・振り返りをできるようにするためには、過去の変革を乗り越えてきた歴史を社内に周知させたり、人材育成に経験学習を取り入れたり、振り返りのフレームワークを導入することができます。
[参考リンク-人材育成や研修に取り入れるべき”振り返り”のフレームワークとは!?]
行為
DXに関する行為を行うことで、環境情報の部分的感知ができたり、DXを自身で体感することができます。
行為を起こすためには、行為を起こすまでのステップを最小単位で設定して、行動に移しやすくしたり、行為となるような実践研修を実施することができます。
[参考リンク-組織や人の変化を後押しするナッジ理論とは!?フレームワークや人材育成への活用までわかりやすく解説します!]
社会性
DXに関するコミュニケーションやDXに触れる機会を作ることで、組織の中のDXに個人としてDXをしていることを補足します。
例えば、DXについての社内コミュニティを設置して、組織としての取り組みの中で自分がDXに取り組んでいることを理解したり、発信することができます。
継続性
DXに対しての発信や行動をさせる仕組みを継続的に与えることで、センスメイキングをより高めることができます。
例えば、ラーニングエクスペリエンスデザインを取り入れたDXを体感することのできる研修体系を作り、実施することができます。
環境情報の部分的感知
行為によって生まれた経験や結果によって、自分がDXに対して考えていることを確かめたり、得られた結果からよりセンスメイキングができるようになります。
環境情報の部分的感知をさせるには、行為を発生させることが最も重要となります。
説得性・納得性
ストーリーを用いて、説得力や納得力を高めることで、DXに関する腹落ち度を深めることができます。
事業計画などの数値計画だけでなく、ミッション・ビジョン・バリューなどの定性的なものにDXに関するストーリーを関連付けたり、社内に対するトップマネジメントからのDXに関する講和をすることができます。
まとめ
この記事では、センスメイキング理論とDXの関係について解説しました。
センスメイキング理論とは、人々が自分の置かれた状況や経験に意味を与えるプロセスのことです。
センスメイキング理論を理解することで、組織や個人が変化に対応しやすくなり、より効果的な行動や判断ができるようになります。
センスメイキング理論を取り入れた市民開発に向けた研修カリキュラムを下記資料からダウンロードできますので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたのDX推進に幸あれ!