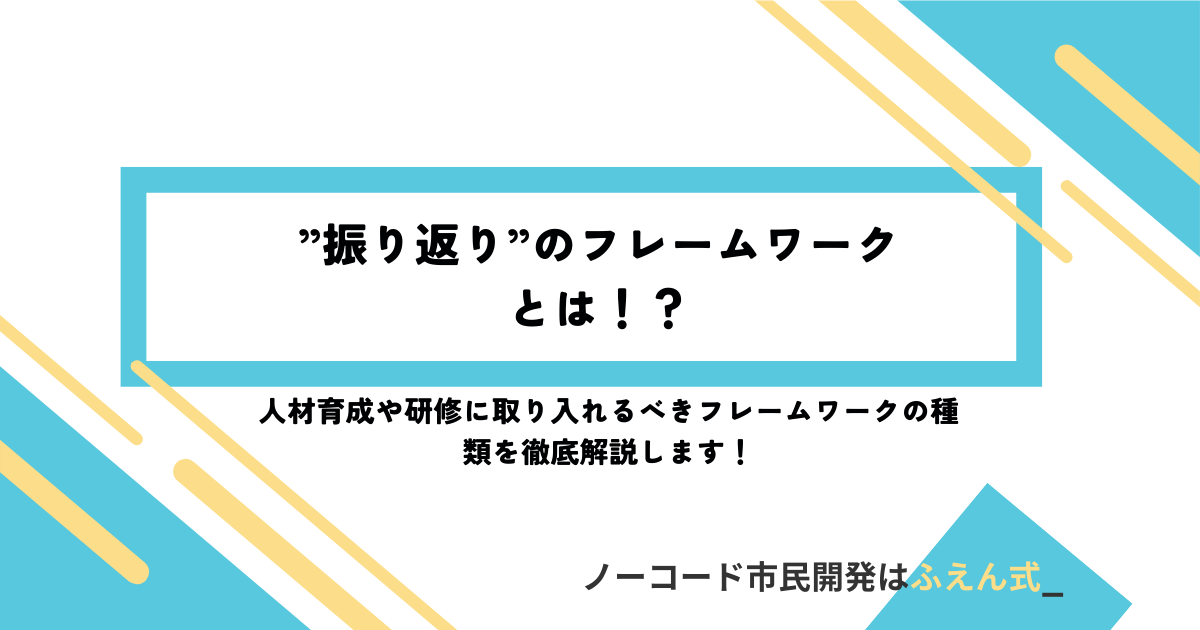学習や成長を促進するためには、振り返りが欠かせません。
振り返りとは、自分や他者の行動や結果について、客観的に分析し、評価し、改善策を考えることであり、振り返りを行うことで、自己理解や自己認識を深め、学習効果を高めることができます。
しかし、振り返りをするといっても、どのようにすればいいのでしょうか?
この記事では、振り返りを効果的に行うためのフレームワークを紹介します。
フレームワークを使うことで、振り返りの内容や方向性を明確にし、時間や労力を節約することができます。
この記事を読むことで、以下のようなお悩みを解決できます。
- 振り返りの方法がわからない
- 振り返りの効果が感じられない
- 振り返りの時間がない
この記事で紹介するフレームワークは、人材育成や研修の現場で実際に使われているものです。
また、研修以外にも、日常の業務やプロジェクト、個人の学習など、さまざまな場面で活用できますので、ぜひ最後までお読みください!
振り返りの重要性

振り返りは、人材育成や研修において、非常に重要な役割を果たします。この章では、振り返りの重要性について下記の3つの観点で解説していきます。
振り返り-リフレクションとは
振り返りとは、英語でリフレクションと言います。リフレクションとは、鏡に映るように、自分や他者の行動や結果を客観的に見つめ直すことです。
リフレクションを行うことで、自分の強みや弱み、成功や失敗の原因、改善や学習のポイントなどを明らかにすることができます。
リフレクションには、以下のような種類があります。
- 自己リフレクション:自分の行動や結果について振り返ること
- 相互リフレクション:他者の行動や結果について振り返ること
- 共同リフレクション:チームや組織の行動や結果について振り返ること
リフレクションは、単に過去を振り返るだけではなく、未来に向けて行動を改善するための手段です。リフレクションを通して、自分や他者の成長を促進することができます。
振り返りが必要とされる人材育成
振り返りを行うことで、研修の効果を高めることができます。
具体的に人材育成においての振り返りは下記のようなメリットをもたらします。
理解度の確認と学習の定着
学習や研修の内容を理解できたかどうかを確認することです。
自身が学んだことを復習したり、試してみたりすることで、自分にどれだけ落とし込めているかを確認することができます。
応用力や実践力の向上
教育や訓練の内容を実際の業務や状況に応用できるようにすることです。
振り返りをすることで、具体的な学びを概念化し、今後に活用できるように自身に落とし込むことができます。
[参考リンク-ノーコード人材・市民開発者の育成方法とは!?学習の入門からノーコード研修までおすすめのやり方を徹底解説します!]
研修以外にも必要な振り返り
振り返りは、研修だけではなく、日常の業務やプロジェクト、個人の学習など、さまざまな場面で必要です。振り返りを行うことで、以下のようなメリットがあります。
問題解決能力の向上
実践の中で得た経験を振り返り、概念化し、学びに昇華することで、経験をもとに似たような状況や課題が目の前にあるときに、問題点や論点を見つけ、解決することができます。
創造性の発揮
これまでの経験を振り返ることで、概念化した学びを紐付け、新たな解決策やイノベーションを創造することができます。
コミュニケーション力の強化
2者間以上でのフィードバックをすることで、それぞれに対してのコミュニケーション力の向上が図れます。
また、フレームワークを活用することで、軋轢のないフィードバックやコミュニケーションができるようになります。
振り返りのフレームワーク
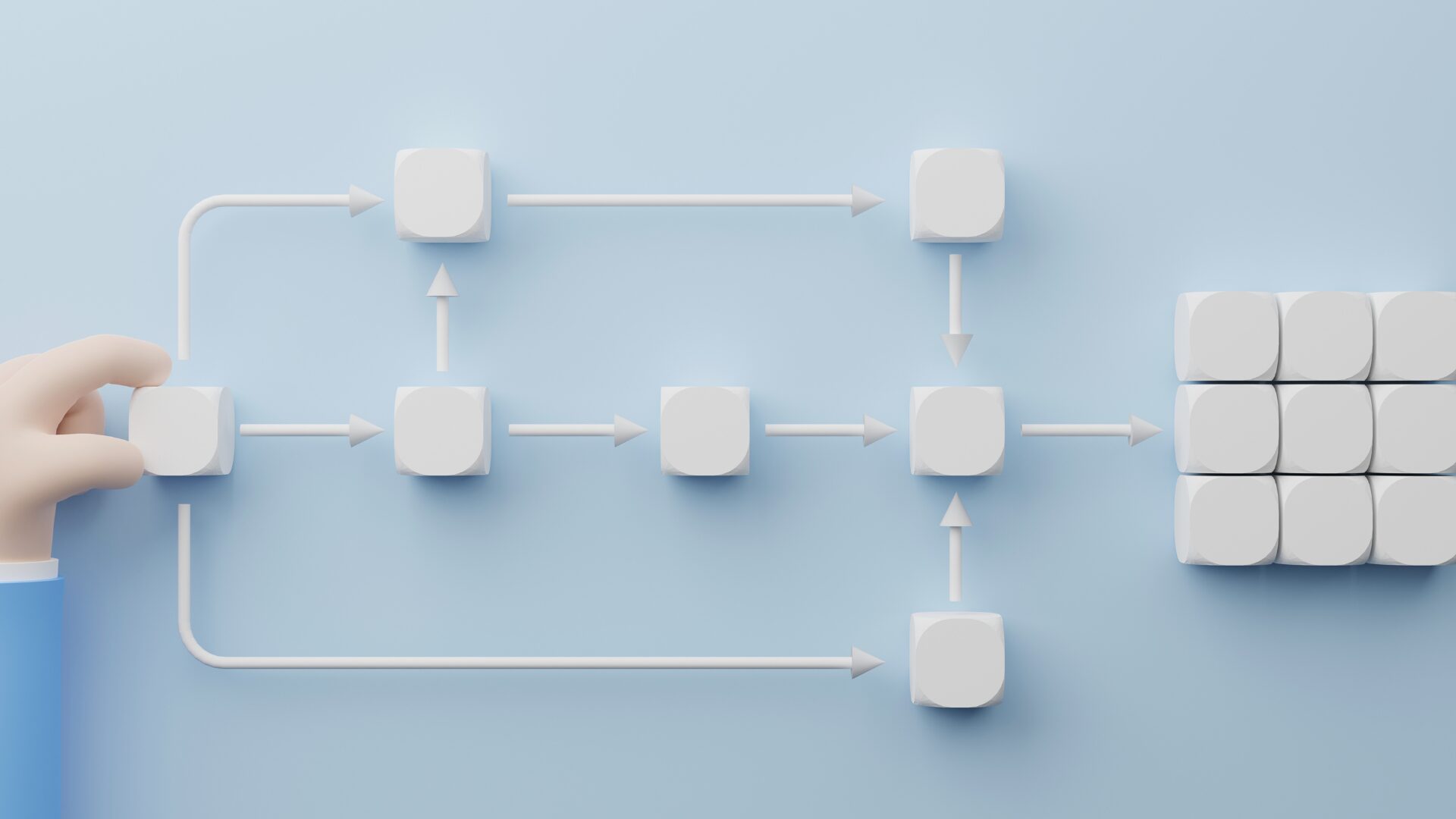
振り返りにはフレームワークを使うことが効果的です。
フレームワークを使うことで、振り返りの内容や方向性を明確にし、時間や労力を節約することができます。
ここでは、人材育成や研修によく使われる振り返りのフレームワークを紹介します。
KPT
KPTとは、Keep(継続すべきこと)、Problem(問題点)、Try(改善策)の頭文字をとったものです。
KPTは、振り返りの最も基本的なフレームワークで、自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Keep:良かったことや成功したことは何か?これを継続するためにはどうすればいいか?
- Problem:悪かったことや失敗したことは何か?これを解決するためにはどうすればいいか?
- Try:次にやってみたいことや挑戦したいことは何か?これを実現するためにはどうすればいいか?
KPTは、振り返りの目的や内容に応じて、さまざまなバリエーションがあります。例えば、以下のようなものがあります。
- KPTA:Action(具体的な行動)を加えることで、Tryの実行性を高める
- KPTW:Wish(願望や目標)を加えることで、Tryのモチベーションを高める
- KPTT:Thank(感謝や称賛)を加えることで、Keepのポジティブな感情を高める
KPTは、個人やチームの振り返りに適しています。
YWT
YWTとは、Yatta(やったこと)、Wakatta(わかったこと)、Tsugi ni yaru koto(次にやること)の頭文字をとったものです。
YWTは、KPTと似たフレームワークですが、より学習に焦点を当てたもので、自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Yatta:何をやったのか?どのようにやったのか?やったことの評価はどうか?
- Wakatta:何を学んだのか?どのように学んだのか?学んだことの意味は何か?
- Tsugi ni yaru koto:次に何をやるのか?どのようにやるのか?やることの目的は何か?
YWTは、学習の効果や成果を確認するための振り返りに適しています。
Start-Stop-Continue-Change
Start-Stop-Continue-Changeとは、Start(始めるべきこと)、Stop(やめるべきこと)、Continue(続けるべきこと)、Change(変えるべきこと)の頭文字をとったものです。
Start-Stop-Continue-Changeは、KPTと似たフレームワークですが、より行動にフォーカスを当てたもので、自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Start:今までやっていなかったことで、始めるべきことは何か?これを始めるためにはどうすればいいか?
- Stop:今までやっていたことで、やめるべきことは何か?これをやめるためにはどうすればいいか?
- Continue:今までやっていたことで、続けるべきことは何か?これを続けるためにはどうすればいいか?
- Change:今までやっていたことで、変えるべきことは何か?これを変えるためにはどうすればいいか?
Start-Stop-Continue-Changeは、自分や他者の行動や結果を改善するための振り返りに適しており、業務やプロジェクトの途中や終了時に振り返りを行う際に便利です。
FDL
FDLとは、Fact(事実)、Discovery(発見)、Learning(学び)の頭文字をとったものです。
FDLは、YWTと似て、学習にフォーカスを当てたフレームワークですが、発見から得た情報を概念化し、学びに昇華することで、学習をより深めることを目的としたものです。
FDLでは、自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Fact:何が起こったのか?どのようなデータや証拠があるのか?事実に基づいて客観的に記述すること
- Discovery:何がわかったのか?どのような気づきや感想があるのか?発見に基づいて主観的に記述すること
- Learning:何を学んだのか?どのような知識やスキルが身についたのか?学びに基づいて具体的に記述すること
FDLは、自分や他者の学習の成果や価値を明確にするための振り返りに適しており、教育や訓練の最終日や修了後に振り返りを行う際に便利です。
Star Fish
Star Fishとは、Keep Doing(継続すべきこと)、Less Of(減らすべきこと)、More Of(増やすべきこと)、Stop Doing(やめるべきこと)、Start Doing(始めるべきこと)の5つのカテゴリーを、星の形に分けたものです。
Star Fishは、Start-Stop-Continue-Changeをより細かく分類したものと捉えることができます。
Star Fishでは自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Keep Doing:良かったことや成功したことは何か?これを継続するためにはどうすればいいか?
- Less Of:悪くはなかったが、改善の余地があることは何か?これを減らすためにはどうすればいいか?
- More Of:良くはなかったが、ポテンシャルがあることは何か?これを増やすためにはどうすればいいか?
- Stop Doing:悪かったことや失敗したことは何か?これをやめるためにはどうすればいいか?
- Start Doing:今までやっていなかったことで、始めるべきことは何か?これを始めるためにはどうすればいいか?
Star Fishは、自分や他者の行動や結果を最適化するための振り返りに適しており、業務やプロジェクトのレビューや評価時に振り返りを行う際に便利です。
PDCA
PDCAは振り返りのフレームワークの中でも有名な概念で、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の頭文字をとったものです。
PDCAは、振り返りの中でも、特に改善サイクルを重視したフレームワークです。
PDCAでは、自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Plan:何を目標とするのか?どのように達成するのか?計画を立てること
- Do:計画に沿って行動すること
- Check:行動の結果を測定し、目標との差異を確認すること
- Act:差異を分析し、原因を特定し、改善策を実施すること
PDCAは、自分や他者の行動や結果を継続的に改善するための振り返りに適している、業務やプロジェクトを継続的に改善するための振り返りを行う際に便利です。
LAMDA
LAMDAとは、Look(観察)、Ask(問いかけ)、Model(モデル化)、Discuss(議論)、Act(行動)の頭文字をとったものです。
LAMDAは、PDCAと似たフレームワークですが、より問題解決に焦点を当てたものです。
LAMDAでは、自分や他者の行動や結果について、以下のように振り返ります。
- Look:何が起こっているのか?どのような現象や事象があるのか?観察すること
- Ask:何が問題なのか?どのような仮説や疑問があるのか?問いかけること
- Model:問題の原因や構造は何か?どのようなロジックやフレームワークがあるのか?モデル化すること
- Discuss:モデルの妥当性や有効性はどうか?どのような意見や反論があるのか?議論すること
- Act:どのような解決策や改善策があるのか?どのように実行するのか?行動すること
LAMDAは、自分や他者の行動や結果を根本的に改善するための振り返りに適しており、業務やプロジェクトの問題解決に挑む際に便利です。
振り返りを人材育成に活かすには

振り返りのフレームワークを人材育成に活かすにはどうすればいいのでしょうか?
ここでは、振り返りを人材育成に活かすためのポイントについて3つに分けて解説します。
個人の振り返り
個人の振り返りとは、自分自身の行動や結果について振り返ることで、学びや経験を概念化し、次に活かすことができるようになります。
個人の振り返りを行うには、具体的には下記のような方法があります。
- 参加した研修に対してYWTで振り返りを行い、次にやること(実践)を考える
- 自身が参加しているプロジェクトに対して、PDCAで振り返りを行い、自身の行動を改善する
個人の振り返りを行う際には、下記の点に注意する必要があります。
- 定期的に行う:振り返りは、一度だけではなく、定期的に行うことが大切です。振り返りを習慣化することで、自分の成長を促進することができます。
- 正直に行う:振り返りは、自分に嘘をつかないことが大切です。自分の行動や結果について、客観的に見つめ直し、素直に認めることができます。
- ポジティブに行う:振り返りは、自分を責めたり、否定したりしないことが大切です。自分の行動や結果について、良い点や成功点を見つけ、自分を褒めたり、励ましたりすることができます。
上司・上席からの振り返り
上司・上席からの振り返りとは、自分の行動や結果について、上司や上席の人からフィードバックやアドバイスをもらうことです。
上司・上席からの振り返りを受けるためには、具体的には下記のような方法があります。
- 上司との1on1面談の中で、LAMDAを使った振り返りを定期的に行う
- プロジェクトリーダーとの1on1面談の中で、FDLを自分と上司の両者の意見を用いて振り返りを行う
上司・上席からの振り返りの際には、下記の点に注意する必要があります。
- 受け入れる:振り返りは、上司や上席の人からの意見や感想を受け入れることが大切です。自分の行動や結果について、批判や指摘を受けたとしても、反発したり、逆ギレしたりしないことができます。
- 質問する:振り返りは、上司や上席の人からの意見や感想を理解することが大切です。自分の行動や結果について、詳細や根拠を聞いたり、具体的な例を求めたりすることができます。
- 感謝する:振り返りは、上司や上席の人からの意見や感想を感謝することが大切です。自分の行動や結果について、フィードバックやアドバイスをもらったことに対して、お礼を言ったり、感謝の気持ちを伝えたりすることができます。
育成計画の振り返り
育成計画の振り返りとは、組織に対して作成した教育カリキュラムや、実施計画にたいしての振り返りのことです。
育成計画の振り返りは、具体的に下記のような方法があります。
- Start-Stop-Continue-Changeを使って、教育カリキュラムの見直しを行う
- StarFishを用いて、カリキュラムの振り返りを行う
育成計画の振り返りの際には、下記の点に注意する必要があります。
- 定量目標を設定する:振り返りを行うためには、定性面だけでなく、定量面と定性面の両方で振り返りができるようにすることが必要です。
- 可視化する:振り返りは、進捗や成果を記録し、見える化することが大切です。目標や計画には、設定した定量目標を可視化できるようにすると効果的です。
[参考リンク-ラーニングエクスペリエンスデザインとは!?研修効果を最大化するための理論をDXの人材育成への活用も併せて解説!]
まとめ
この記事では、人材育成や研修に取り入れるべき振り返りのフレームワークについて紹介しました。
振り返りとは、自分や他者の行動や結果について、客観的に分析し、評価し、改善策を考えることであり、自己理解や自己認識を深め、学習効果を高めることができるものでした。
ぜひ今回の記事で紹介したフレームワークを活用して、人材育成やプロジェクトの成功に役立てていただけたら幸いです。
あなたのDX推進に幸あれ!