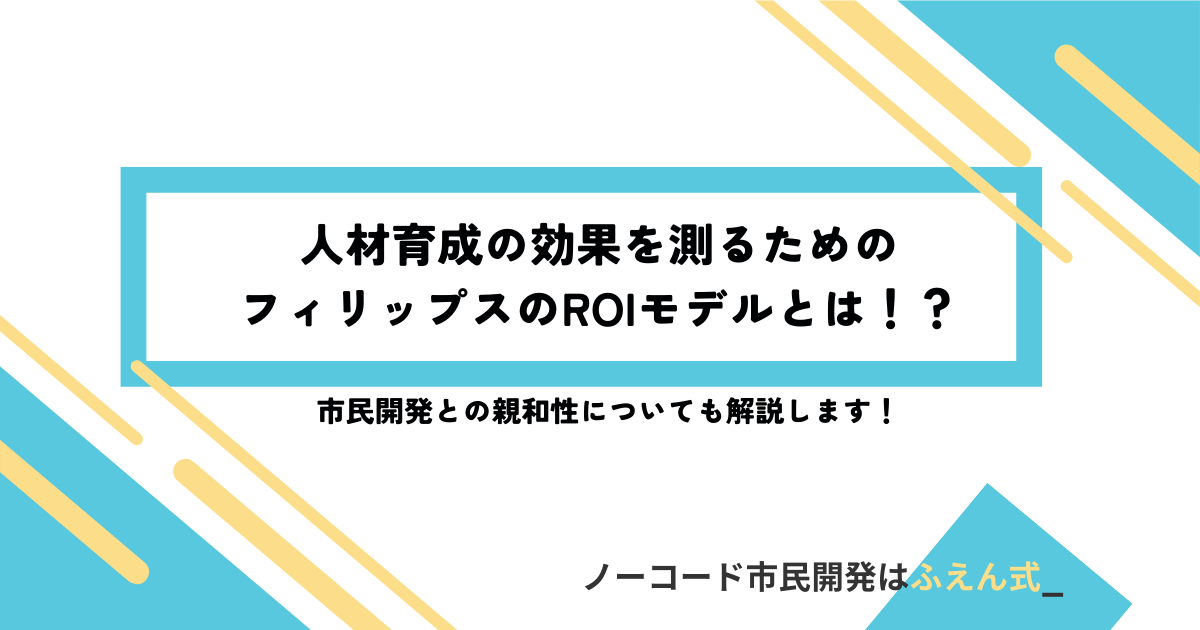人材育成に投資する企業は多いですが、その効果をどう測るかは難しい問題です。
人材育成の効果を測るためには、どのような指標や方法が必要なのでしょうか?
この記事では、人材育成の効果を測るためのモデルの一つである「フィリップスのROIモデル」について解説します。
このモデルを使うと、人材育成による経済的な効果だけでなく、学習者の反応や学び、行動変容、組織への貢献など、様々なレベルでの効果を測ることができます。
市民開発に対する人材育成と、フィリップスのROIモデルの考え方についても最後の章で触れますので、ぜひ最後までお読みください。
フィリップスROIモデルとは!?

フィリップスのROIモデルの概要
フィリップスROIモデルとは、ジャック・フィリップス博士が提唱した概念で、人材育成による投資対効果(ROI)を算出するためのモデルです。
カークパトリックモデルを発展させたもので、以下の5つのレベルで人材育成の効果を測ります。
- Level1: Reaction(反応)
- Level2: Learning(学習)
- Level3: Behavior(行動)
- Level4: Results(結果)
- Level5: ROI(投資対効果)
カークパトリックモデルとの違い
フィリップスのROIモデルは、カークパトリックモデルを発展させたものですが、どのような違いがあるのでしょうか?
カークパトリックモデルは、人材育成の効果を4つのレベルで評価するモデルですが、その中でも最も重要なのはLevel4の結果です。
しかし、カークパトリックモデルでは、Level4の結果が人材育成によってもたらされたものなのか、それとも他の要因によるものなのかを区別することができません。
また、カークパトリックモデルでは、人材育成にかかったコストと結果の金額との関係を明確にすることができません。
フィリップスのROIモデルは、これらの問題を解決するために、以下の2つの工夫をしています。
- Level4の結果に対して、人材育成以外の要因を考慮して、人材育成による効果のみを分離することを行います。これを「分離技法」と呼びます。分離技法には、コントロールグループ法、トレンドライン分析法、予測モデル法などがあります。
- Level4の結果の金額と、人材育成にかかったコストとの比較を行い、ROIを算出することを行います。これにより、人材育成による経済的な効果を明確にすることができます。
フィリップスのROIモデルが注目される理由
フィリップスのROIモデルは、人材育成による効果を測るためのモデルとして、注目されています。その理由は、以下の2つが挙げられます。
人材育成に対する投資意欲の高まり
リスキリングやアンラーニングといった言葉が流行しているように、現在日本では学ぶことや学ばせることに対して非常に関心が高まっています。
しかし、人材育成や教育といった文脈では、投資対効果が見えづらく、今までの形骸化した研修から脱することができない企業も多いです。
そのような中で、投資対効果を見える化できるフィリップスのROIモデルは、人材育成や教育に対してROIを求めることができる方法として、注目されています。
[参考リンク-ノーコード人材・市民開発者の育成方法とは!?学習の入門からノーコード研修までおすすめのやり方を徹底解説します!]
DX
デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展とともに、その重要性が高まっています。
DX人材を育成することにより、企業は効率化やイノベーションを推進し、競争力を高めることができますが、その投資効果を正確に測定することは難しく、多くの企業で課題となっています。
フィリップスのROIモデルは、このようなデジタル投資の成果を金銭的価値に換算し、投資対効果を明確に示すことで、経営層の意思決定を支援することができるのです。
フィリップスのROIモデルのレベル別測定項目

Level1: Reaction(反応)
Level1では、学習者が人材育成に対してどのような反応を示したかを評価します。
反応で評価する項目は、学習者の満足度や感想、学習意欲やモチベーションなどです。
反応は、人材育成の質や効果に影響を与える要素であり、反応が良ければ、学習者は学習に積極的に取り組み、次のレベルへと進む可能性が高まると判断できます。
反応が悪ければ、学習者は学習に対して消極的になり、学習効果が低下する可能性があります。
反応を測る方法としては、以下のようなものがあります。
- アンケート 学習者に人材育成に関するアンケートを実施します。アンケートには、人材育成の内容や方法、講師やファシリテーター、学習環境などの質問も含みます。アンケートは、人材育成の直後に行うのが望ましいです。
- インタビュー 学習者に人材育成に関するインタビューを行います。インタビューでは、アンケートでは表現できない学習者の感想や意見、感情や感動などを聞き出します。インタビューは、アンケートの補足として行うのが効果的です。
- フォーカスグループ 学習者を数人のグループに分けて、人材育成に関するグループディスカッションを行います。フォーカスグループでは、学習者同士の意見交換や共感、気づきなどを促します。フォーカスグループは、学習者の反応を深く掘り下げるのに有効です。
Level2: Learning(学習)
Level2では、学習者が人材育成によってどのような知識やスキルを習得したかを評価します。
学習で評価する項目は、学習者の能力やスキルの向上度合いです。
学習は、人材育成の目的や目標に沿って行われるべきであり、学習が適切に行われれば、学習者は次のレベルである行動変容につなげることができます。
学習が不十分であれば、学習者は行動を変えることができず、得たい効果が得られません。
学習を測る方法としては、以下のようなものがあります。
- テスト 学習者にテストを実施します。テストには、人材育成で学んだ知識やスキルに関する問題が含まれます。テストは、人材育成の前後に行うことで、学習者の学習効果を比較することができます。
- アンケート 学習者に人材育成に関するアンケートを実施します。アンケートには、学習者が自己評価する学習効果や自信度、学習内容の理解度や応用度などについての質問を含めます。アンケートは、テストの補足として行うのが効果的です。
- ポートフォリオ 学習者に学んだ内容に関するポートフォリオを作成させます。ポートフォリオとは、学習者が人材育成で学んだことを示す資料や企画、システムのことを指します。ポートフォリオは、学習者の学習過程や成果を可視化するのに有効です。
Level3: Behavior(行動)
Level3では、学習者が人材育成によってどのように行動を変容させたかを評価します。
行動で評価する項目は、学習者の実際の業務や日常生活での振る舞いや行動です。
行動は、人材育成の最終的な目的や成果に直結する要素であり、行動が変われば、組織や社会に対する貢献度や価値が高まります。
行動が変わらなければ、人材育成の効果が見えません。
行動を測る方法としては、以下のようなものがあります。
- 自己評価 学習者の実際の業務や日常生活での行動を自信に評価させます。自己評価は評価者と学習者のみが関わります。自己評価は、人材育成の前後に行うことで、学習者の行動変容の度合いを比較することができます。
- フィードバック 学習者の実際の業務や日常生活での行動に対してフィードバックを行います。フィードバックには、学習者の上司や同僚、部下、顧客などが関わります。フィードバックは、学習者の行動の改善点や課題、成功事例やベストプラクティスなどを伝えます。フィードバックは、観察の補足として行うのが効果的です。
- パフォーマンス評価 学習者の実際の業務や日常生活での行動に対してパフォーマンス評価を行います。パフォーマンス評価には、学習者の上司や人事部などが関わりまます。パフォーマンス評価は、学習者の行動が組織の目標や戦略にどのように貢献しているかを測ります。
Level4: Results(結果)
Level4では、学習者の行動変容が組織にどのような結果をもたらしたかを評価します。
結果で評価する項目は、組織の業績や目標達成度、社会的責任などです。
結果は、人材育成の最終的な成果や効果を示す要素であり、結果が良ければ、人材育成は組織にとって価値ある投資であると言えます。
結果を測る方法としては、以下のようなものがあります。
- 業績指標 学習者の行動変容が組織の業績にどのように影響したかを測ります。業績指標には、売上や利益、生産性、品質、顧客満足度、離職率、事故率などが含まれます。業績指標は、人材育成の前後に行うことで、学習者の行動変容による結果の変化を比較することができます。
- 目標達成度 学習者の行動変容が組織の目標や戦略にどのように貢献したかを測ります。目標達成度には、組織のビジョンやミッション、中長期計画、年度計画などが含まれます。目標達成度は、人材育成の前後に行うことで、学習者の行動変容による結果の達成度を比較することができます。
Level5: ROI(投資対効果)
Level5では、人材育成にかかったコストと、Level4で得られた結果の金額との比較を行い、ROIを算出します。
ROIは、人材育成による経済的な効果を示す指標です。
ROIは、以下の式で求められます。
ROI=Level4の結果の金額−人材育成のコスト×100%
ROIを算出することで、人材育成が組織にとってどの程度の収益性を持つかを判断することができ、ROIが高ければ、人材育成は組織にとって有益な投資であると言えます。
ROIを算出する方法としては、以下流れで行います。
- 分離技法による結果の金額の算出 Level4の結果に対して、人材育成以外の要因を考慮して、人材育成による効果のみを分離することを行います。これを「分離技法」と呼びます。分離技法には、コントロールグループ法、トレンドライン分析法、予測モデル法などがあります。
- コストの算出 人材育成にかかったコストを算定します。コストには、人材育成の開発費や実施費、参加費や交通費、学習者の時間費用などが含まれます。コストは、人材育成の期間や範囲に応じて算定します。
- ROI算出 分離技法で得られた人材育成による効果の金額と、コスト算定で得られた人材育成のコストとの比較を行い、ROIを算出します。ROIは、上記の式で求められます。
ROI算出のための実務のステップ

計画立案
1つ目のステップは計画立案です。
計画立案では、人材育成の目的や目標、評価の方法や指標、データ収集の計画や方法、データ分析の計画や方法、報告の計画や方法などを明確にします。
計画立案の際には下記のポイントを押さえる必要があります。
事業計画やDX戦略と教育プログラムの整合性を確認する
計画する教育プログラムが、事業計画やDX戦略に準じていたり、整合性が取れているものになっているかを確認します。
このフェーズがうまくいかないと、Level4はもとより、ROIの算出は非常に難しくなるため、しっかりと目的を明確にして教育プログラムを作りましょう。
適切なソリューションを選択する
各教育プログラムが、適切なソリューションとなっているかを確認します。
例えば、プロジェクトベースドラーニングの前段のインプット研修がオフラインでの集合研修となっていた場合に、「本当にそれはオフラインでやる必要があるか、割くべきコストやリソースが多くないEラーニングで代替はできないか」などソリューションの見直しを行いましょう。
ここでは、ROI算出の際のコストを最大限少なくできないか、人件費やリソースは減らすことができないか、といった観点で見直すと良いでしょう。
研修成果がでる計画を作る
研修効果がしっかりと算出できるように、算出するためのデータの収集や分析方法を計画します。
ここでは定量的・定性的に何を指標とするかを決め、その上でそれらのデータを受講者や業績からどのように集めるかを計画します。
データ収集①
データ収集①では、人材育成の前に、Level1からLevel2の各レベルのデータを収集します。
完了した研修の数や、研修に対しての好感度、学習習得度などを測ります。
方法としては、アンケートやサーベイ、インタビューやテストなどを活用することが多いです。
データ収集②
データ収集②では、人材育成の後に、Level3からLevel4の各レベルのデータを収集します。
職場での活用度や、業務への影響度を測ります。
方法としては、フォーカスグループを用いたり、KPIモデリングをして可視化することが多いです。
データ分析
データ分析では、ROIを測定するためにLevel4で算出されたデータを分析します。
ステップとしては下記の流れで行います。
- Level4データの分離:Level4で得られた効果の数値に対して、研修による影響度がどの程度だったかを算出し、その効果分を分離します。
- Level4データの金額算出:Level4で得られたデータをROIの指標とするために金額換算します。業務改善系であれば、削減された業務時間に人件費を掛けて金額算出したりします。
- 見えざる利益・メリットの整理:ここでは、Level4で測定した指標以外に、効果が出ているものはないかを探します。
- コスト算出:ここでは研修に使ったコストを算出します。この場合、研修時間も含む場合が多いです。
- ROI算出:ここまでで出た数値をもとに、ROIを算出します。
報告
報告では、データ分析で得られた結果を報告します。報告では、以下の2つを行います
- 主な関係者にデータでストーリーを語る
- ブラックボックスの精神で改善し、予算増額
主なステークホルダーに対して、データで示すだけでなく、全体をストーリーとして伝えることが重要です。
ここでしっかりとROIを見据えた研修に効果をストーリー仕立てで伝えられるかどうかで、その後の予算増額ができるかが関わってきます。
予算増額といっても、ROIが算出できることを示すことできれば、予算が増えた分の見据えられるROIの説得度も増すため、より予算が通りやすくなります。
フィリップスのROIモデルと市民開発

市民開発はROIが見えやすい
市民開発は、研修の対象である現場の社員が業務改善などを行うことであるため、Level4の結果として、組織や社会に対する明確な貢献や価値として現れやすいです。
例えば、市民開発における人材育成の効果として、以下のようなものが考えられます。
- 作成されたアプリケーションによって削減された業務時間
- RPAで自動化された業務工数
- コミュニティの活性化や連携度
これらの効果は、金額に換算することができるため、Level4これらの金額を、人材育成のコストと比較することで、ROIを算出することができます。
[参考リンク-市民開発とは!?内製化を目指すための具体的な進め方やメリット・デメリットを徹底解説!]
ROIにインパクトを与えるためには実践研修が必要
市民開発における人材育成のROIを高めるためには、実践研修が必要で、そのなかでもPBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)の活用がおすすめです。
PBLとは、学習者が実際の実務課題に対してプロジェクトを立ち上げ、計画、実行、評価することで、知識やスキルを習得し、行動を変容させることを目的とした学習法のことです。
そのため、市民開発におけるPBLは、人材育成のROIにインパクトを与えやすいです。
例えば、実務課題をノーコードツールを活用したアプリ開発で業務改善するようなPBLを行うことで、プロジェクトの結果として実務課題が解決され、削減されたリソースや時間や工数を金額に換算し、ROIを算出することができます。
このように、市民開発におけるPBLはROIを見据えた人材育成にとても効果的です。
[参考リンク-プロジェクトベースドラーニングとは!?DX人材育成やその研修に必要な概念を理解しよう!]
まとめ
この記事ではフィリップスのROIモデルについて解説しました。
結論、ROIを見据えた人材育成を行うなら、市民開発の文脈で、ノーコードツールを活用した研修が大変オススメです。
ぜひこの記事を参考にして、市民開発や、人材育成を成功に導いてくださいね。
あなたのDX推進に幸あれ!