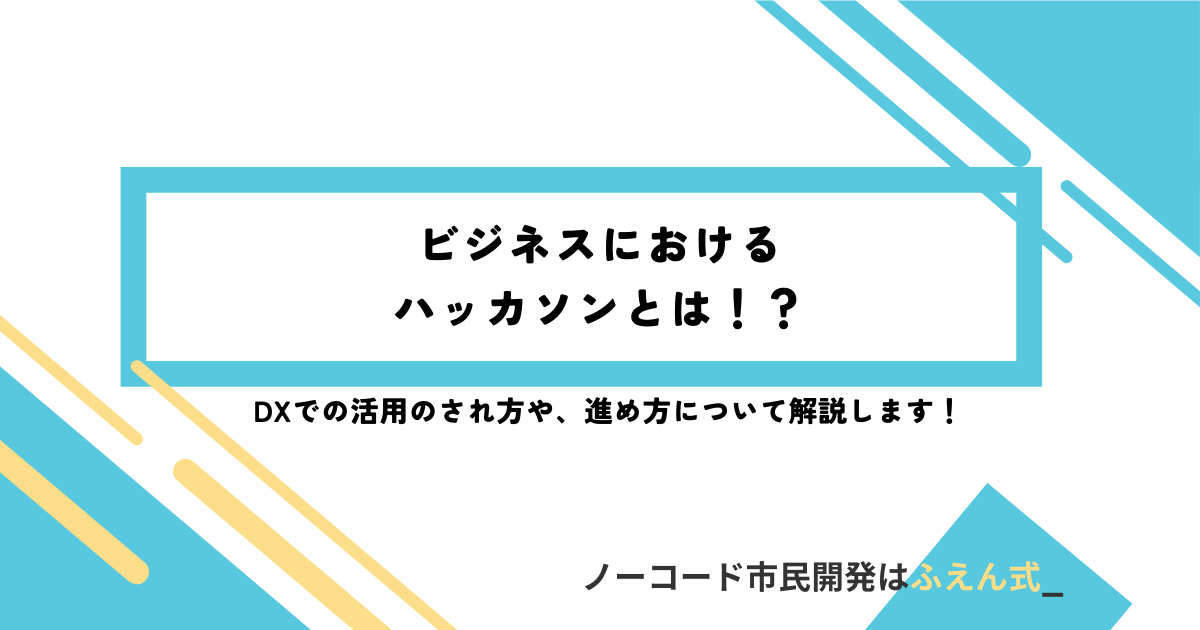近年ビジネスシーンでハッカソンというキーワードが注目を集めています。
しかし、その実態や効果についてまでは聞いたことがない方がほとんどなのではないでしょうか?
本記事では、ハッカソンの概要から進め方、そしてDXにおける活用方法まで、詳しく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
ハッカソンとは

ハッカソンの概要
ハッカソンは、企業やコミュニティが限られた期間内にチームで集まり、イノベーティブなアイデアを考え出し、それを実際のプロダクトやサービスとして具現化するイベントです。
従来の開発手法ではなく、迅速なプロトタイピングや実験を重視します。
参加者はチームを結成し、多様な視点からアイデアを出し合いながら、指定されたテーマに基づいてプロジェクトを進めます。
このプロセスによって生み出された成果(システムやアプリケーション)が評価されます。
近年では、コーディングだけのソフトウェア開発だけでなく、ノーコードツールを活用したハッカソンも増加しています。
このため、開発に携わる技術者だけでなく、営業担当者や広報担当者、商品開発担当者なども参加することができ、異なる業務や専門性を持つ人々が集まり、新たな視点やアイデアを共有することで、オープンイノベーションが促進されるのです。
ハッカソンの歴史
「ハッカソン」という言葉は、「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語であり、システムの解析や改良を指す言葉です。
この用語が初めて使用されたのは、米国IT企業のサン・マイクロシステムズのマーケティングチームが1999年に使用したときと言われています。
その後、アメリカ・シリコンバレーを中心に広まり、GAFAなどの有名企業が相次いでハッカソンを開催し、世の中にハッカソンが広く知られるようになりました。
3種類のハッカソン
一般的なハッカソン、社内ハッカソン、産学連携ハッカソンの3つの主要な種類があります。
それぞれのハッカソンには異なる特性と目的がありますが、共通して新たなアイデアの創出と具現化が目指されています。
一般的なハッカソン
一般的なハッカソンとは、企業や団体が外部に向けて行う、最も一般的な形式のハッカソンです。
このタイプのハッカソンは、テーマの幅が広く、広範な募集活動が行われるため、他のハッカソンと比較して最も大規模なものになりやすい傾向があります。
ハッカソンは、オープンイノベーションの優れた手法であると同時に、主催者にとっても認知度の向上や人材確保などの多くのメリットをもたらします。
そのため、近年では大手企業からベンチャー企業に至るまで、多くの企業が積極的にハッカソンを開催する傾向にあります。
社内向けのハッカソン
社内向けのハッカソンは、新たなビジネスアイデアの発掘や技術力向上のために企業内で実施される取り組みです。
社内ハッカソンは、新規事業の創出だけでなく、社内エンジニアの技術力向上や知識共有の場としても利用されます。
参加者はチームを組み、限られた期間内にイノベーティブなアイデアを生み出し、それを具現化するプロジェクトに取り組みます。
このプロセスは、チームの結束力を高め、普段接触の少ない社員同士が交流し、信頼関係を築く機会としても機能します。
社内ハッカソンは、企業文化の活性化やイノベーションの促進にも寄与します。従業員が自らのアイデアを実現する場を提供することで、創造性やチームワークを育み、企業全体の競争力向上に貢献します。
産学連携のハッカソン
新技術の研究開発や新事業の創出を目的に、大学や教育機関と民間企業が協力して行う産学連携のハッカソンが注目されています。
この形式のハッカソンは、学術界と産業界が連携し、革新的なアイデアやプロジェクトを共同で推進する場として位置づけられています。
産学連携のハッカソンは、学生の育成や新たなテクノロジーの普及だけでなく、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進にも重要な役割を果たしています。
企業は、学生との議論を通じて新たな視点やアイデアを得るとともに、若手や中堅社員をDXの推進役となるイノベーターに育成する機会としてもこの形式のハッカソンを活用しています。
ハッカソンとアイデアソンの違い
ハッカソンと並んで頻繁に使われる用語として、アイデアソンがあります。
ハッカソンと同様に、「アイデア(Idea)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語で、企業や部署、さまざまな立場や職種の人々が集まり、特定のテーマに沿った活動を行う点で共通しています。
ハッカソンでは、アプリやシステムなどのプロダクトで成果を競い合いますが、アイデアソンでは新たな商品企画やビジネスモデルなどの「アイデア」を競います。
そのため、ハッカソンに比べて参加者の層は幅広く、エンジニアなどの開発者だけでなく、マーケティングやデザイン、経営戦略などの領域からも参加が可能です。
さらに、ハッカソンは数日から数週間にわたって開催されるのに対し、アイデアソンは数時間から数日程度の比較的短い期間で行われます。
この点からも、ハッカソンよりも手軽に参加できるという特徴があります。
アイデアソンはもともと、ハッカソンの準備段階で行われることが一般的でしたが、最近ではその手軽さや参加のしやすさから、単独で開催されるケースも増えています。
企業や組織が新たなアイデアを生み出し、イノベーションを促進するために、ハッカソンとアイデアソンを適切に活用することが求められています。
ハッカソンが注目される背景とDX・市民開発
ハッカソンが注目される背景には、DXと市民開発があげられます。
新規事業としてのハッカソンはもとより、社内の業務効率化を目指したアプリケーション制作などをハッカソンの形式を持って作成することも増えてきました。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や市民参加型の開発が進む中、ハッカソンはその迅速なアイデア実現の手法として再評価されています。
ノーコード市民開発におけるハッカソンのメリット

エンジニアでなくてもハッカソンに参加できる
ハッカソンは基本的にプログラミング開発のスキルをもったエンジニアが参加するものですが、ノーコードツールを活用することで、その前提条件は必要なくなります。
これにより、多様な経験をもつメンバーによってハッカソンを実施できるため、オープンイノベーションの観点で非常に有効です。
また、現場社員の参加もできるようになることから、面前の業務に対しての業務効率化のためのアプリケーション開発などをハッカソンのテーマにすることもできます。
[参考リンク-ノーコードとは?ローコードとの違いや流行の理由、メリットデメリット、向き不向きまで徹底解説!]
社内コミュニケーションの活性化・連携の強化
市民開発における社内ハッカソンの場合、自社のメンバー同士が異なるプロジェクトに参加し、初めてチームを組むことがあります。
このような経験を通じて、メンバー同士の交流が深まり、社内コミュニケーションの活性化が期待されます。
また、異なる部門やプロジェクトから集まったメンバーが連携して共同作業を行うことで、組織全体の連携力も強化されるでしょう。
さらに、ハッカソンでは短期間で成果を出すために、効率的なコミュニケーションやタスクの分担、意見の統合などが求められます。
これらのプロセスを通じて、参加者はコミュニケーションスキルの向上だけでなく、チームワークや問題解決能力の向上にも貢献します。
[参考リンク-市民開発とは!?内製化を目指すための具体的な進め方やメリット・デメリットを徹底解説!]
0から完成まで作り上げる経験を獲得できる
ハッカソンでは、企画から要件定義、設計、開発、テストまでをチーム全体で行います。
チーム内である程度の役割分担はあるものの、基本的にすべての工程をチームメンバー全員が体験します。このプロセスを通じて、参加者は0からプロダクトを完成させる経験がえられます。
また、ハッカソンでは時間の制約があり、短期間で成果を出すことが求められます。
そのため、プロジェクト全体の進行管理やスケジュール調整、効率的なタスクの分担など、プロジェクト管理能力も同時に鍛えられます。
ハッカソンでの経験は、参加者にとって非常に貴重なものとなります。新たな挑戦や学びの場として、積極的に参加することで、自己成長やキャリアの発展につながることでしょう。
オープンイノベーションの促進
ハッカソンは、即時的な効果とは別に、オープンイノベーションにつながりやすい環境づくりに寄与する効果も期待できます。
特に、社内ハッカソンはこの点で重要な役割を果たします。
社内ハッカソンでは、参加者が通常の業務では担当しない領域に挑戦することとなるため、参加者は自身の業務範囲を超えた新たな知識やスキルを獲得し、システム全体の理解を深めることができます。
このような経験は、企業内でのオープンイノベーションにおいて、異なる部門やチーム間でのコラボレーションを促進し、新たなアイデアやソリューションの発見につながります。
さらに、社内ハッカソンを継続的に実施することで、社内の交流や情報共有の機会が増えます。
異なる部門やプロジェクトからの参加者が集まり、意見交換やアイデアの共有が行われることで、企業全体のイノベーション力が向上します。
また、複数回のハッカソンを通じて、参加者が事業全体を俯瞰して捉える力が養われ、新規事業やプロジェクトの発掘や推進が活発化する風土が醸成されていくのです。
ハッカソンの進め方

参加者の募集
ハッカソンの成功には、適切な参加者の募集が必要です。
そのためには、まずはハッカソンの種類(社内・社外・産学連携)と目的(認知度アップ、商品開発、業務効率化など)を明確に定めることが重要です。
ハッカソンの種類と目的が明確になったら、次に参加者の数を決定します。
これは、ハッカソンの性質や目的に応じて適切な規模を設定することが重要です。
大規模なイベントであれば多くの参加者を募集する必要がありますが、小規模なハッカソンでは少人数でも効果的に開催できる場合もあります。
その後は、目的に応じたハッカソンのテーマや開発形式、発表の形式、審査方法などを決定します。
また、参加対象者を明確に定めることも重要です。
開発経験者のみ、初心者可など、参加条件を明示することで、適切な参加者を集めることができます。
事前準備
ハッカソンを実施するための事前準備は成功の鍵となります。
まずは、適切な会場の準備が必要です。
参加者が快適に作業できる環境を整えるために、以下の点に注意しましょう。
まずは、Wi-Fiの環境です。参加者が同時に接続しても問題ないよう、十分な帯域幅を確保してください。
また、コンセントの数も重要です。参加者がデバイスを充電できるように、十分なコンセントを用意しましょう。延長コードの必要な数や配置も事前に確認しておきます。
会場の空調も重要なポイントです。多くの人が集まる場所では、適切な温度管理が必要です。快適な作業環境を提供するために、会場の空調設備の点検を行いましょう。
さらに、参加者が作業するための机や椅子の数も事前に確認しておく必要があります。参加者全員が適切な作業スペースを確保できるよう、必要な家具の手配を行いましょう。
また、ハッカソンの運営に必要なスタッフの役割分担も事前に決定しておく必要があります。
進行役、参加者の受付、案内役、タイムキーパー、広報担当など、各役割を明確にし、スムーズな運営を目指しましょう。
チーム分け
ハッカソンにおける参加者のチーム分けは、成功するか否かを分ける重要なポイントです。
参加者同士が協力してプロジェクトに取り組むためには、適切なチーム編成が必要です。
まずは、チームの人数を考慮する必要があります。
チームが大きすぎると、発言の機会が偏ったり、コミュニケーションが円滑に行われなくなる可能性があります。
一般的には、1チームあたり5〜6人程度が適切です。この人数ならば、十分な参加者がいる一方で、個々の意見や役割も明確になります。
また、チームメンバーのスキルや経験の偏りを防ぐために、事前に参加者の情報を集めることが重要です。
アンケートなどで参加者の経験やスキルを把握し、バランスの取れたチーム編成を目指しましょう。しかし、参加者の欠席や遅刻などの不測の事態も考慮して、完璧な均等配分を求めるのではなく、柔軟な対応が求められます。
特に大規模なハッカソンでは、チーム分けに時間がかかることがあります。このため、受付の段階で可能な限りチーム分けを済ませておくことが重要です。席の移動などが発生すると、時間のロスや運営上の混乱を招く可能性があるため、事前に計画を立てておくことが望ましいでしょう。
テーマの発表とアイデア出し
次はハッカソンのテーマを発表し、各チームごとにアイデア出しを行います。
募集の段階でおおよその目的とテーマが提示されることが一般的ですが、アイデア出しの直前に改めてその背景や主旨を詳しく説明することが重要です。
さらに、成果の発表形式についても事前に明確に伝えることで、参加者の理解を深めましょう。
次に行われるのが、どんなプロダクトを開発するのかを考えるアイデア出し(アイデアソン)です。
この段階では、ブレインストーミングと同様に、他者の考えを批判や否定するなこと起きないようにしましょう。
アイデアソンでは、参加者が自由にアイデアを出し合い、創造性を発揮できるように、心理的安全を担保することが求められます。
開催者側は事前にこの注意事項を通知し、プロセスが円滑に進むよう配慮しましょう。
[参考リンク-組織に求められる心理的安全性とは!?DX推進での考え方や確保の方法に言及しながらわかりやすく解説します!]
開発
アイデア出しのフェーズを終えたら、次は具体的なアプリやシステムの開発に取り組みます。
アイデア出しから開発フェーズに移る際に重要なのがMVPの概念です。
目的のサービスとする上で必要最低限の機能はなんなのか、これをしっかりと各チームで議論ができるようにファシリテートしましょう。
また、開発については、ハッカソン自体をノーコードツールを活用したものとすることで、迅速かつフレキシブルな開発が可能となります。
成果と結果発表
ここでは実際に開発したアプリケーションやシステムを発表してもらい、評価し、結果を発表します。
審査方法は様々で、ゲスト審査員による採点や参加者による投票などがあります。
審査は必須ではありませんが、順位付けによってイベントがより盛り上がることが多いです。
また、社内でのハッカソンでは、この結果によってインセンティブなどを設けることによって、参加者の意欲を掻き立てることもできます。
最後のフォローアップ
最後に、ハッカソンが終了した後、主催者は参加者に対するフォローアップを行いましょう。
これには、アンケートの実施やプロダクトへのフィードバックなどが含まれます。
特に、社外ハッカソンでは、成功事例を自社のアピールに活かすため、当日の模様を記事としてまとめ、自社ブログやSNSなどで公開すると良いでしょう。
また、社内外から参加者を募集した場合は、参加者が開発したプロダクトを主催者が実際に運用する場合、その参加者チームと連絡を取り、運用方法について確認をする必要があります。
パブリックドメインであっても、無断で使用することは参加者の信頼を損ねる可能性があるため、慎重な対応が求められるためです。
まとめ-ハッカソンを市民開発で活用しよう!
この記事ではハッカソンについて、概要から開催方法まで解説してきました。
ハッカソンは、さまざまなシーンで有効に活用できる手法ですが、特に市民開発を推進している企業において、社内の取り組みを活性化させる方法の一つでもあります。
ぜひ市民開発を検討されている場合は、ハッカソンというイベントを通して、市民開発の推進をしてみてください。
あなたのDX推進に幸あれ!