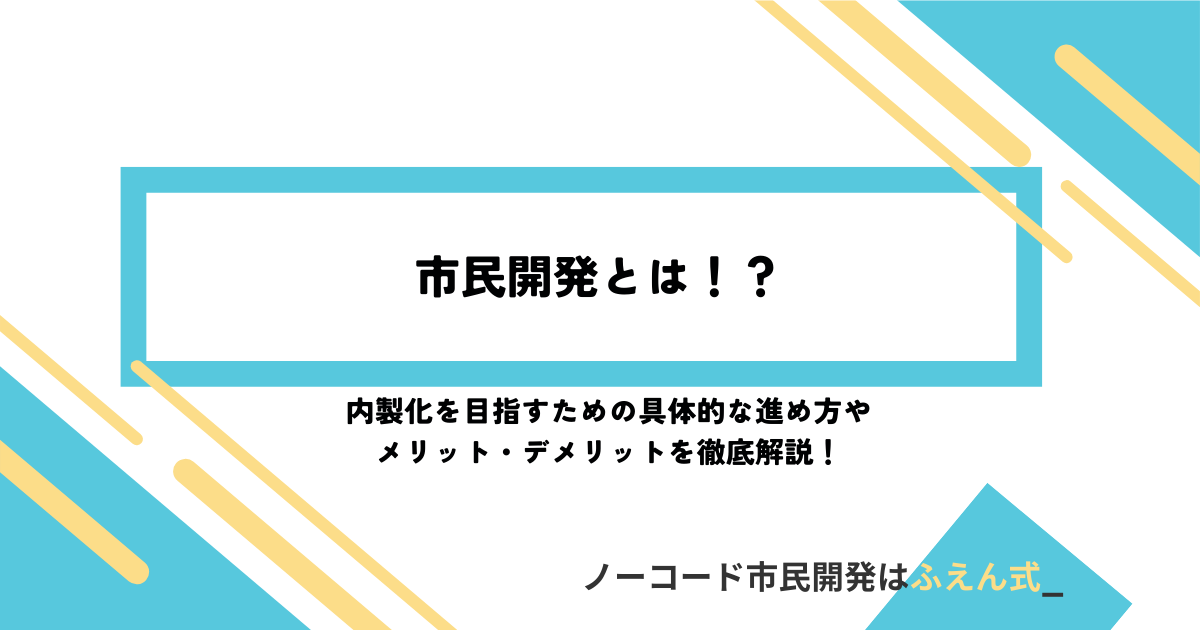自社のウェブサイトやアプリを開発する際に、外部の業者に依頼すると、開発費用が高くついたり、ユーザーのニーズに合わないものができたり、品質やセキュリティに問題があったりすることがありますよね。
そんな時に「自社で開発することができれば」と思ったことはありませんか?
この記事では、自社で開発することを目指すための方法として、市民開発という概念を紹介します。
市民開発では、ユーザーや社員が自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加することで、多様なアイデアを収集したり、ユーザーのニーズに合った開発を行ったりすることができます。
では、市民開発を行うためには、どのようにすれば良いのでしょうか。この記事では、市民開発の具体的な進め方やメリット・デメリットを徹底解説します。
市民開発に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
市民開発とは

ここでは、市民開発というものの概念や概要について解説していきます。
概要を理解することで、この後の進め方などをより理解できるようにしていますので、ぜひ飛ばさずにお読みください。
市民開発とは何か
市民開発とは、自社のユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加することです。市民開発は、ユーザー主導や社員主導の開発とも呼ばれます。
市民開発は、自社のWebサイトやアプリを開発する際に、外部の業者に依頼するのではなく、自社で開発することを目指すための方法であり、ユーザーや社員が、自分たちのアイデアや意見を提案したり、フィードバックをしたり、テストをしたり、コードを書いたりすることができ、自分たちのニーズに合ったものを自分たちで作ることができるようになります。
[参考リンク-ノーコードとは?ローコードとの違いや流行の理由、メリットデメリット、向き不向きまで徹底解説!]
なぜ市民開発という言葉が流行しているのか
市民開発という言葉は、昨今では「DX」の文脈の中で使われることが多いです。つまり、DXを推進していく中でシステム開発をベンダーに依頼したりすることが増えたのがそもそもの根本ではありますが、もう一つの要因として、技術の進化があげられます。
そもそも、今まではWebサイトにしろアプリケーションにしろ、現場の方が開発するなんて発想もできないほどレベルが高いことでした。しかし、現在ではローコード・ノーコードツールの台頭により、プログラミング言語を習得せずともWebサイトやアプリケーションを作れる環境ができました。
世間のDXの進化と技術の進化の2つが組み合わさったことにより、”現場の人が現場のニーズを直接解決できるツールの開発”ができるようになり、それらが求められるようになったのです。
内製化と市民開発
市民開発と共によく聞くのが「内製化」ではないでしょうか。
内製化とは外部に委託していた業務を自社で行うこと全体を指しますが、市民開発は内製化の概念に加えて「現場の人が自ら開発する」ニュアンスが追加されたものです。
一つの部門に開発機能を集約し、自社開発を行うことは内製化ではありますが、市民開発ではありません。
内製化と市民開発で目指すべき姿
内製化と市民開発で目指すべき姿は、以下の3つです。
自社で開発することで、開発工数と費用を削減する
これは内製化で叶えられるポイントですが、自社で開発とフィードバックや改善を行うことで、外部ベンダーに依頼していた分の費用を削減し、さらにニーズを伝えるための打合せや、手戻りなどの無駄な工数と時間も削減します。
これらの削減で発生した余剰から、新たなる変革やイノベーションが生まれていきます。
現場や業務の細かなニーズに対応する
これは市民開発でないと叶えられません。
業務をデジタル化するためのアプリケーション開発では、開発側が主導となって作ることで、現場のニーズを汲み取りきれず、根本的な改善にならなかったり、ともすれば使われなくなってしまうことさえもあります。
市民開発を取り入れ、開発やテスト工程を実行、もしくは参画してもらうことで、しっかりと現場のニーズを反映させ、より効果のある施策にすることができます。
自社の課題を自社で改善していく文化を創る
これこそ市民開発と言える姿ですが、現場の人たちもデジタル化やその開発にプロアクティブに参加することがこの姿の実現につながります。
この世界線に到達した先には、現場からどんどん改善要望やDXのアイデアが上がってきて、それらをある程度現場で開発することができ、一過性の取り組みでない連続的な変革と、それによる非連続的な成長をすることができるようになるのです。
市民開発の進め方
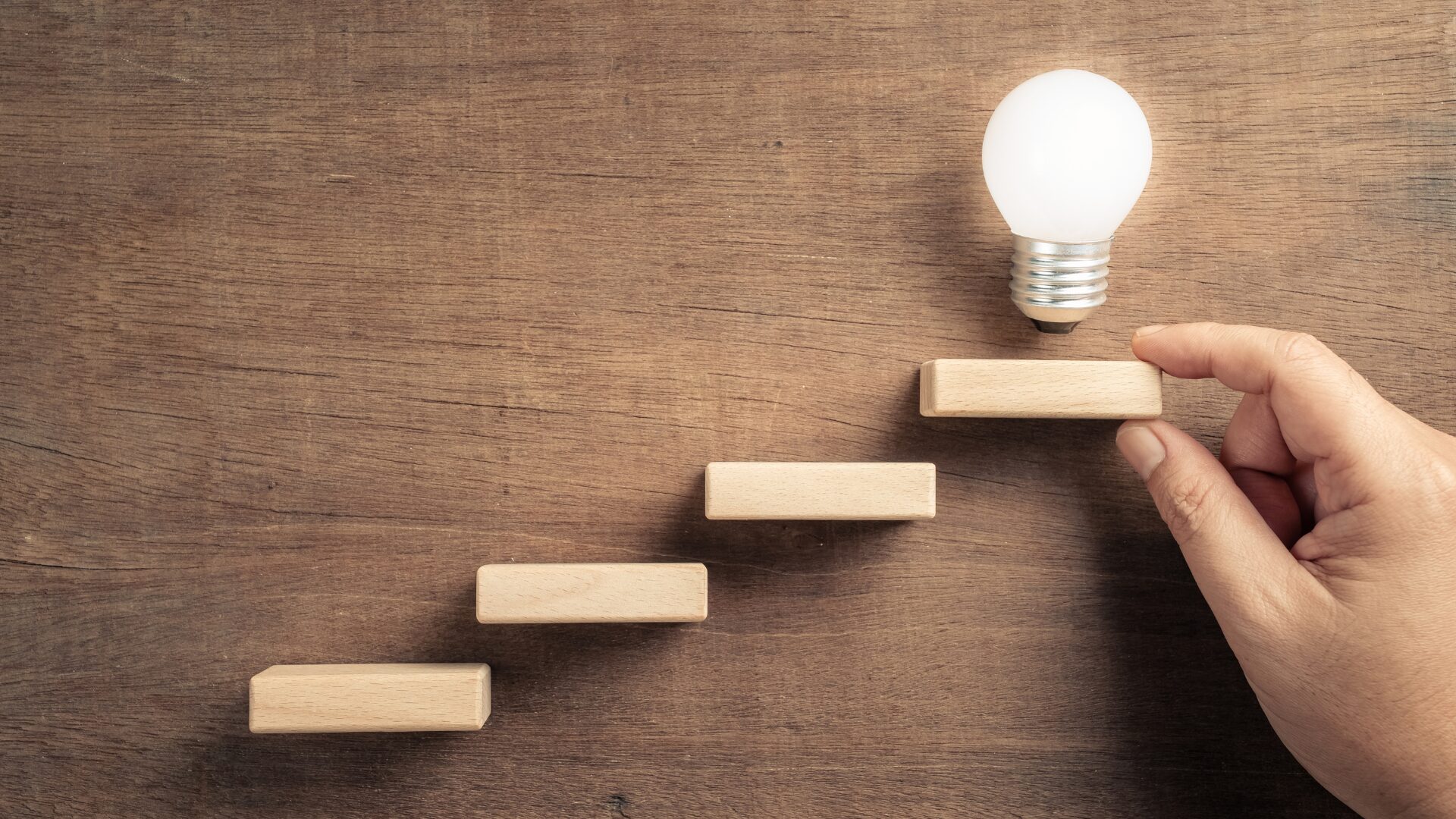
市民開発は、内製化を目指すための有効な方法であることがわかりました。
では、市民開発を行うためには、どのように進めていけば良いのでしょうか。
この章では市民開発の具体的な進め方を紹介します。
ステップ1: モチベーションを高める
市民開発を行うためには、まず、ユーザーや社員のモチベーションを高め、市民開発への参加をハラ落ちさせることが重要です。
自ら開発に参加することに興味や意欲を持つようにしなければ、ユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、動いたり、学んだりしようとはしてくれません。
モチベーションを高めるためには、以下の2つのことを行うことが効果的です。
[参考リンク-「腹落ち感」を形成するセンスメイキング理論とは!?組織でDXを推進していくための文化の醸成に活用しよう!]
トップのコミットメントを示す
まずは、会社として市民開発に向けた変革をしていくことをトップが示す必要があります。
いくらDX推進部門や情報システム部門が声をあげたとしても、現場には現場の仕事があり、自分たちの業務を割いてまで学んだり動いてはくれません。
しっかりと会社として、現場が現場の変革を起こしていけるような体制を作っていくことをトップが発信しなくては、現場の人たちはそれが自分の仕事に取り入れていいものかどうかを判断することもできません。
市民開発のメリットを説明する
市民開発のメリットをユーザーや社員に説明することで、市民開発に対する理解や関心を深めることができます。砕けた表現をするならば、「うまみを理解してもらう」ことになります。
理解してもらうべき市民開発のメリットは、組織としてのメリット・個人としてのメリットをしっかりと伝えることが大事です。
また、メリットを作るために、人事評価や組織設計などを見直すことも良い取り組みになるでしょう。
ステップ2: デモクラシーを導入する
市民開発を行うためには、次に、デモクラシーを導入することが必要です。
デモクラシーとは、ユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加できるようにする会社としての仕組みのことを言います。
デモクラシーを導入することで、市民開発の参加者やプロジェクトの選定や実施に関する意思決定を、より公平に行うことができます。
デモクラシーを導入するためには、以下の2つのことを行うことが効果的です。
現場の人がプロジェクトに参加できる仕組みの構築
現場の人がプロジェクトに参加できる仕組みを構築することで、現場の人をプロジェクトに巻き込み、市民開発を実践することができます。
ユーザーがプロジェクトに参加できる仕組みは、主にワーキンググループやプロジェクトチームの発足が行われます。
メンバーの集め方は部門長からの選抜や社内アンケートでの公募など、会社の風土や状況に合わせて組み合わせるとよいでしょう。
意見やアイデアの収集方法の構築
意見やアイデアの収集方法を設定することで、市民開発の参加者やプロジェクトの選定や実施に関する意思決定を、より効率的かつ公平に行うことができます。
意見の収集方法は、社内アンケート機能などを使った意見箱のようなものを仮想的に設置するような継続的に集められる方法と、社内コンペや教育のアウトプットなど、何かの取り組みとして行う方法があります。
評価方法などはその時々によって変わるため、昔に出た意見が、新たに検証してみるととてもいいアイデアだった、なんてことがよく起こります。つまり特に集めた意見があとでも見返せたり、利用可能になっていることが重要なのです。
ステップ3: 教育・トレーニングの提供
市民開発を行うためには、さらに、教育・トレーニングの提供が必要です。
教育・トレーニングの提供とは、ユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加できるようにするためのスキルや知識を身につけることです。
教育・トレーニングの提供を行うことで、市民開発の参加者の開発能力を向上させることができます。
教育・トレーニングの提供を行うためには、以下のようなことを行うことが効果的です。
[参考リンク-ノーコード人材・市民開発者の育成方法とは!?学習の入門からノーコード研修までおすすめのやり方を徹底解説します!]
技術的なスキルの向上
技術的なスキルの向上とは、ユーザーや社員が、自分たちが使うウェブサイトやアプリの開発に必要な技術的なスキルを身につけることです。例えば、プログラミング言語やフレームワーク、ノーコードツールなどの具体的な開発ツールの使い方です。
技術的なスキルの向上を行う際には、オンラインやオフラインの教材やコース、ワークショップやハッカソンなどのイベントを利用することで、より効果的にすることができます。
ビジネススキルの向上
ビジネススキルとは、課題の見つけ方や、解決策の考え方、ロジカルシンキングなど、デジタル以外で、かつDXの推進に必要なスキルを指します。
DXやデジタル化といった文脈では、デジタルに関するスキルや知識が注視されがちですが、そもそもどのように変革を起こせばいいか、どのようにビジネスプロセスを分解すれば良いか、など、変革を起こすべきポイントを見つけたり、その解決策を検討したりする際にビジネススキルは非常に重要となります。
このようなスキルはEラーニングや座学でのインプットのみならず、実践演習やワークショップを通して実際に活用することでより効果が高まります。
プロジェクトマネジメントの方法の学習
プロジェクトマネジメントの方法が必要になるのは推進が進んでからになりますが、必ず必要な知識です。
プロジェクト管理の方法の学習とは、ユーザーや社員が、自分たちが使うウェブサイトやアプリの開発に必要なプロジェクト管理の方法を学ぶことです。
しかし、このプロジェクト管理の機能まで現場に持たせる必要があるわけではありません。どこまで現場に求めるかを整理することも非常に重要です。
ステップ4: プロジェクトの選定とメンバーの選出
市民開発を実際に行うためには、実際に実行していくプロジェクトの選定とメンバーの選出が必要です。
プロジェクトの選定
プロジェクトの選定とは、ユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加するプロジェクトを選び、実際に開発を行うことですが、これらを最初から現場サイドで行うのは難しいです。
そのため、下記の2点を意識したプロジェクトの選定を中枢が行うことで、最初の足掛かりをスムーズにする必要があります。
- 1つ目は現場の方が自ら開発に参加することに意義や価値を感じるプロジェクトです。自分たちのニーズに合ったプロジェクトや、自分たちの興味や関心のあるプロジェクトなどがこれにあたります。
- 2つ目は自ら開発に参加することに適度な難易度や挑戦性を感じるプロジェクトです。自分たちのスキルや経験に応じたプロジェクトや、自分たちの学習や成長に寄与するプロジェクトなどがこれにあたります。
市民開発に適したプロジェクトの選定を行う際は、デモクラシーの導入でも触れた、意見の収集方法を上手に組み合わせることで、現場のニーズと難易度が合っているプロジェクトを創出しやすくなります。
メンバーの選出
メンバーの選出とは、プロジェクトに参加するメンバーを決めるフェーズのことです。このフェーズについては、どの立場の担当が主幹するかによって、方法などは変わりますが、最初のフェーズでは中枢部門が執り行うことをおすすめします。
手法としては下記の3つのパターンで行われることが多いです。
定量的判断
一つ目は定量的判断です。アセスメントツールやヒアリングを活用することによって、適正や素養を定量化・可視化することで、メンバーとして適切かを判断する方法です。ツールも多様化しているため、目的に合った定量化の指標を選定することが非常に大切です。
定性的判断
各部門の部門長等の視点で、適切なメンバーを選出することなどがこれにあたります。しかし、この場合は部門長クラスの方々がDXや変革をすることに前向きである必要があります
意欲での判断
社内公募等を行い、プロジェクトへの参加に対して、またはDXなどの変革を行うことに対しての意欲によって判断する方法です。草の根活動や、まだ社内全体で変革の土壌や風土が出来上がってない時によく行われます。
市民開発のメリットとデメリット

ここまで市民開発についての概要や、具体的な進め方について解説していきました。実施するまでの道のりは簡単ではないですが、得られるメリットはとても大きいです。ここからはそんな市民開発で得られるメリットとと発生しうるデメリットについて解説していきます。
市民開発のメリット
市民開発のメリットは以下の3つです。
多様なアイデアの収集
市民開発では、ユーザーや社員が、自分たちのアイデアや意見を提案したり、フィードバックをしたりすることで、多様なアイデアを収集することができます。多様なアイデアを収集することで、自分たちが使うウェブサイトやアプリの開発をより創造的にすることができ、オープンイノベーションを起こせる可能性が高まります。
特に、中枢部門だけでアイデアを捻出している場合、アイデアの枯渇が起きたり、アイデアが一辺倒になってしまう場合があります。
現場のニーズに合った開発
市民開発では、ユーザーである現場の方が自分たちが使うウェブサイトやアプリの開発に直接関わることで、現場のニーズに合った開発を行うことができます。それによって、自分たちが使うウェブサイトやアプリの開発をより満足度の高いものにすることができます。
中枢部門だけで開発を行った場合、現場の解像度が低く、ニーズに合わないソリューションになってしまう場合もあります。
内製化によるコスト削減
市民開発では、ユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加することで、内製化を進めることができます。内製化を進めることで、自社で開発することができるため、ベンダーに依頼していた分の開発費用を削減することができます。
市民開発のデメリット
ここまで市民開発についてのメリットについて説明してきました。ここからはそんなメリットの裏返しとも言えるデメリットについて解説していきます。しっかりと対策を施すことで、デメリットを打ち消すこともできるので、その対策についても解説していきます。
プロジェクト管理の煩雑化と品質の低下
市民開発では、プロジェクトが多く発生し、かつ品質も担保されていない場合もあるため、プロジェクトの管理が煩雑になってしまうことがあります。これによってプロジェクトの効率やソリューションの品質が低下することがあります。
これを防ぐために、しっかりと中枢で現場で行われているプロジェクトを管理し、もれなくだぶりなく変革が進んでいるか、停滞しているところはないかをチェックする必要があります。また、現場の人に個々のプロジェクト管理について学んでもらうことも効果的でしょう。
開発スピードの低下
市民開発では、ユーザーや社員が、自分たちの問題を解決するために、自ら開発に参加することで、開発スピードの低下が起こることがあります。これにより、いわゆる攻めのDXで新サービスを開発している場合などは、競争力が失われる可能性があります。
これを防ぐためには、開発に関する学習を提供し、現場のスキルアップを図ることと、リソースを割くプロジェクトの優先順位をしっかりとつけること必要があります。
まとめ
市民開発を行うことで、多様なアイデアの収集やユーザーのニーズに合った開発、内製化によるコスト削減などのメリットを得ることができることがわかりました。
そんな市民開発を行うためには、モチベーションを高める、デモクラシーを導入する、教育・トレーニングの提供、プロジェクトの選定と実施の4つのステップを踏むことが必要です。
また、市民開発には、プロジェクト管理の難しさやユーザーとのコミュニケーションの課題、開発スピードの低下などのデメリットもありますが、それらを克服することで、より良い市民開発を行うことができます。
まとめると、現場の人に会社の変革、すなわちDXに対してよりプロアクティブに参加してもらうことが市民開発ということになります。これには現場の意識醸成や、そもそものデジタルリテラシーの獲得など、人材に関してのテコ入れが多く必要になるでしょう。
市民開発に興味のある方は、ぜひこの記事を参考にして、市民開発に挑戦してみてください。
あなたのDX推進に幸あれ!