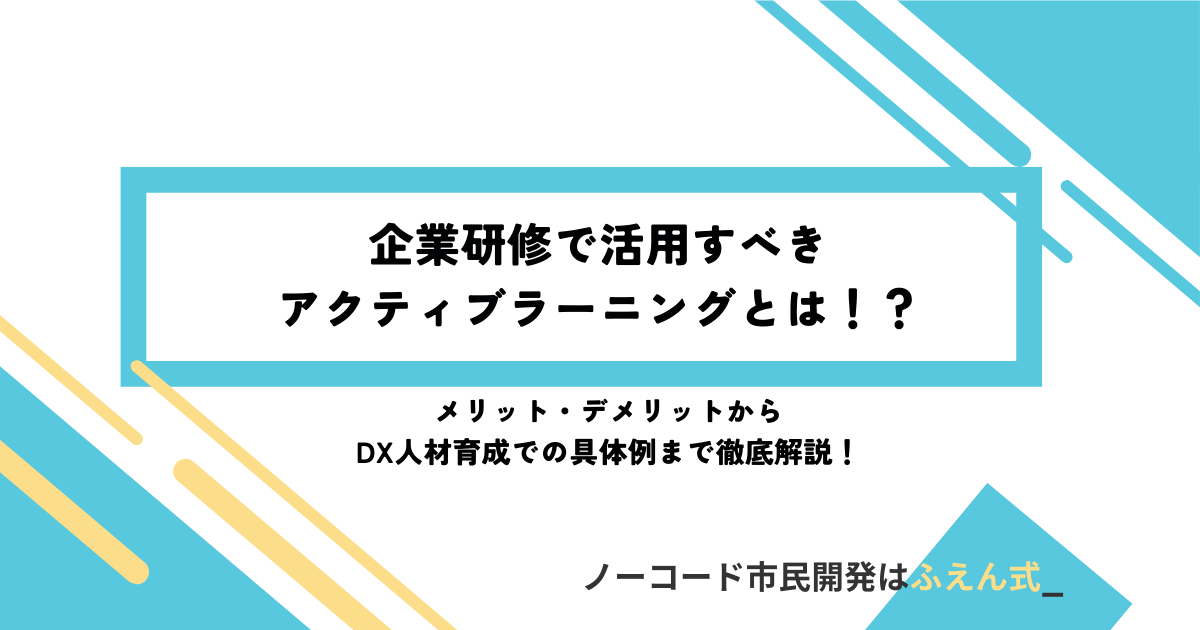企業研修での課題といえば、受講者のモチベーションや理解度の低さ、忘却曲線の急な下降などが挙げられます。
これらの問題を解決するために、最近注目されているのが「アクティブラーニング」です。
アクティブラーニングとは、受講者が能動的に学習に参加することで、知識やスキルを習得する教育法です。
この記事では、アクティブラーニングの概要や具体的な手法、メリットやデメリット、そしてDX人材育成での活用例を紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
アクティブラーニングとは

アクティブラーニングの概要
アクティブラーニングとは、受講者が主体的に学習に参加する教育法です。
講師が一方的に知識を伝えるのではなく、受講者が自ら考えたり、他の受講者と協働したり、実践的な課題に取り組んだりすることを指します。
アクティブラーニングは、アメリカの大学で始まった考え方で、その後、日本の教育現場や企業研修でも広く採用されるようになりました。
アクティブラーニングは、思考力・判断力・表現力などの汎用的能力を育むことができる学習法として、企業の人材育成でも大きく注目されています。
アクティブラーニングの特徴は、以下のようにまとめられます。
- 受講者が主体的に学習に関わる
- 講師は学習のファシリテーターとして、受講者の学習を支援する
- 受講者同士のコミュニケーションやコラボレーションが重視される
- 実践的な課題や問題に取り組むことで、学習内容を深化させる
アクティブラーニングが注目されている背景
パッシブラーニングの限界
パッシブラーニングとは、従来の研修のように講師が一方的に知識を伝えるだけの教育法です。
パッシブラーニングでは、受講者は受け身になりがちで、モチベーションや理解度が低くなり、知識の定着やスキルの習得が難しいという課題があります。
パッシブラーニングはペタゴジーという子供を対象とした学習理論でよく使われる方式で、アクティブラーニングはアンドラゴジーという成人を対象とした学習理論でよく使われる方式です。
[参考リンク-人材育成の効果を最大化するためのアンドラゴジーとは!?具体例も交えながらわかりやすく解説します!]
VUCA時代のニーズ
VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉で、現代社会の特徴を表します。
VUCA時代では、変化が激しく、予測が困難で、多様な要素が絡み合い、正解がないような状況が多くなっています。このような状況に対応するためには、単に知識を持つだけでなく、自ら学び続け、創造的に課題を解決できる能力が求められます。
アクティブラーニングは、VUCA時代に必要なスキルを育む教育法として注目されています。
[参考リンク-VUCAの時代とは?生き抜くための方法やアジャイルとの関連までわかりやすく解説!]
DX人材育成の必要性
DXを推進するには、デジタル技術に精通し、ビジネスや社会の課題を解決できる人材が不可欠であり、そのようなDX人材の育成は、企業や組織の重要な課題となっています。
アクティブラーニングは、DX人材育成においても、有効な教育法となります。
なぜなら、アクティブラーニングでは、受講者が自ら学び、実践的な課題に取り組むことで、デジタル技術の活用やイノベーションの創出に必要な能力を身につけることができるからです。
アクティブラーニングの具体的な手法
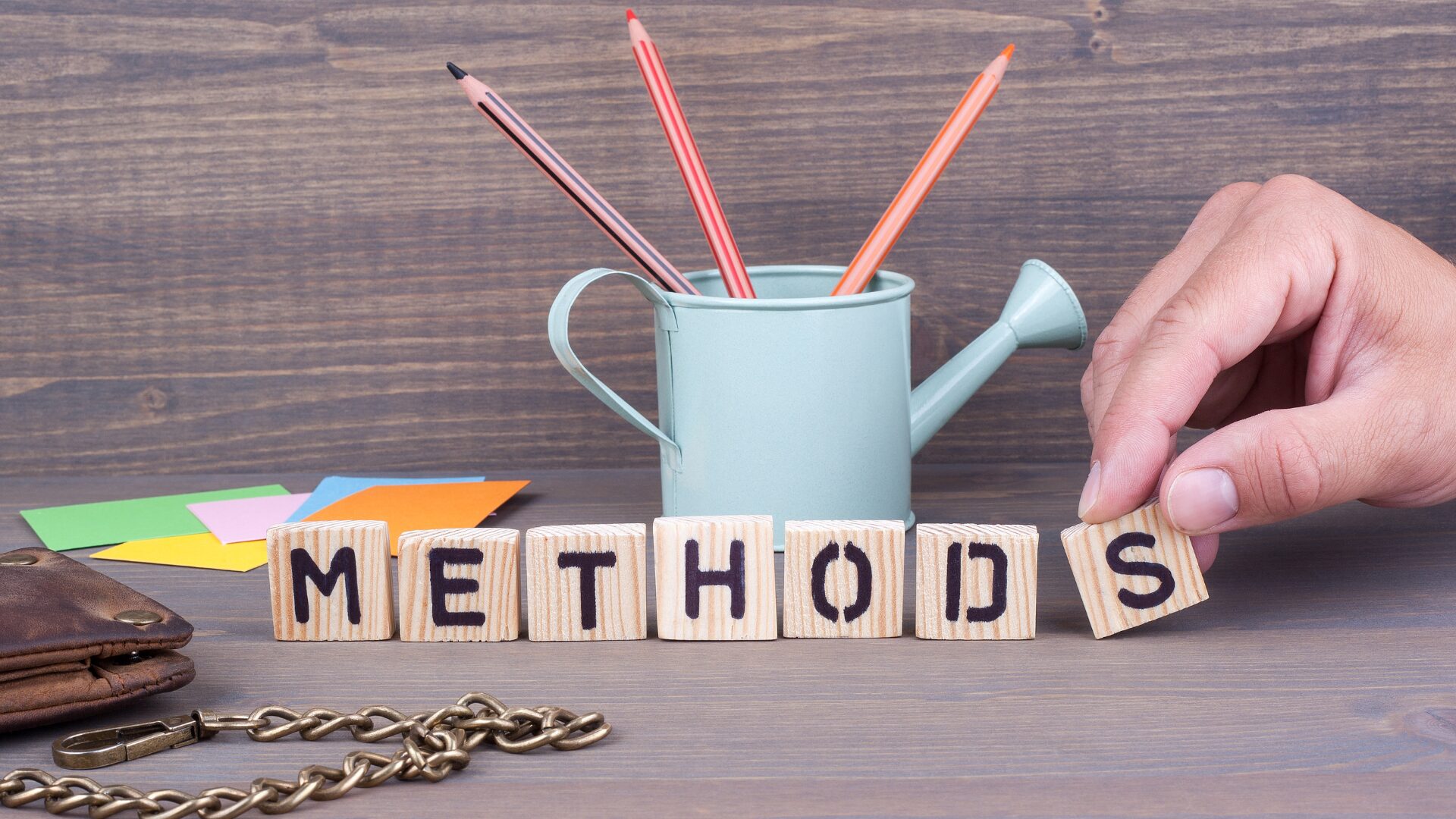
ジグソー法
ジグソー法とは、受講者を小グループに分けて、それぞれに異なるテーマや資料を与えて学習させた後、再びグループを入れ替えて、互いに教え合うという手法です。
ジグソー法では、受講者は自分のテーマについて深く学び、他の受講者にわかりやすく説明することで、自分のテーマについて深く理解するとともに、他の受講者のテーマについても学ぶことができます。
ジグソー法では、受講者は互いに教え合うことで、コミュニケーションや協働のスキルも向上させることができます。
ジグソー法のメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者が自分のテーマに責任を持ち、主体的に学ぶ
- 受講者が他の受講者のテーマに興味を持ち、多角的に学ぶ
- 受講者が互いに教え合うことで、知識の定着や理解の深化を促す
- 受講者がコミュニケーションや協働のスキルを磨く
ジグソー法のデメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者のレベルやモチベーションに差があると、学習効果にばらつきが生じる
- 受講者が自分のテーマについて十分に学ばないと、他の受講者に迷惑をかける
- 講師が受講者の学習状況や進度を把握しにくい
ジグソー法を企業研修に取り入れる場合は、以下のようなポイントに注意する必要があります。
- 受講者のレベルやモチベーションに合わせて、適切なテーマや資料を選ぶ
- 受講者に自分のテーマについてしっかりと学ぶことや、他の受講者に教えることの重要性を伝える
- 講師が受講者の学習状況や進度を適宜確認し、必要に応じてサポートやフィードバックを行う
ジグソー法は、受講者が互いに教え合うことで、知識やスキルを習得するだけでなく、コミュニケーションや協働の能力も高めることができるアクティブラーニングの手法です。
企業研修においても、ジグソー法を活用することで、受講者の学習効果や満足度を向上させることができます。
ただし、ジグソー法には、受講者や講師に一定の負荷がかかるというデメリットもあります。
Think-Pair-Share
Think-Pair-Shareとは、受講者に個人で考えさせた後、ペアで意見交換させた後、全体で共有させるという手法です。
Think-Pair-Shareでは、受講者は自分の考えをまとめ、他の受講者と比較・検討し、全体に発表することで、学習内容を深めます。
Think-Pair-Shareでは、受講者は自分の考えを言語化したり、聞き手としてフィードバックしたり、発表者としてプレゼンテーションしたりします。
Think-Pair-Shareのメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者が自分の考えを整理し、発信することで、知識の定着や理解の深化を促せる
- 受講者が他の受講者の考えを聞くことで、視野を広げられる
- 受講者がコミュニケーションやプレゼンテーションのスキルを磨ける
Think-Pair-Shareのデメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者の考えが浅い場合、ペアや全体での議論が盛り上がらない
- 受講者がペアや全体での共有に消極的な場合、学習効果が低下してしまう
- 講師が受講者の考えや意見を適切に評価しにくい
Think-Pair-Shareを企業研修に取り入れる場合は、以下のようなポイントに注意する必要があります。
- 受講者に考えさせる問題やテーマは、興味を持ちやすく、議論しやすいものにする
- 受講者にペアや全体での共有の意義や目的を伝える
- 講師が受講者の考えや意見に対して、適宜質問やコメントを行う
Think-Pair-Shareは、受講者が自分の考えを言語化し、他の受講者と共有することで、学習内容を深めるアクティブラーニングの手法です。
ラウンドロビン
ラウンドロビンとは、受講者を小グループに分けて、順番に発言させるという手法です。
ラウンドロビンでは、受講者は自分の考えや意見を発表するとともに、他の受講者の考えや意見を聞くことができます。
ラウンドロビンでは、受講者は自分の考えを言語化したり、他の受講者の考えに対して質問やコメントしたり、共通点や相違点を見つけたりします。
ラウンドロビンのメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者が自分の考えや意見を発表することで、知識の定着や理解の深化を促す
- 受講者が他の受講者の考えや意見を聞くことで、視野を広げる
- 受講者がコミュニケーションやコラボレーションのスキルを磨く
ラウンドロビンのデメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者の考えや意見が似通っている場合、議論が活発にならない
- 受講者が発言するのに緊張したり、恥ずかしがったりする場合、学習効果が低下する
- 講師が受講者の考えや意見を適切に評価しにくい
ラウンドロビンを企業研修に取り入れる場合は、以下のようなポイントに注意する必要があります。
- 受講者に発言させる問題やテーマは、興味を持ちやすく、議論しやすいものにする
- 受講者に発言することの重要性や目的を伝える
- 講師が受講者の考えや意見に対して、適宜質問やコメントを行う
ラウンドロビンは、受講者が自分の考えや意見を発表し、他の受講者の考えや意見を聞くことで、学習内容を深めるアクティブラーニングの手法です。
PBL(プロジェクトベースドラーニング)
PBLとは、受講者に実際の課題や問題を与えて、プロジェクトチームを組んで解決策を探求させるという手法です。
PBLでは、受講者は自分たちで課題や問題を定義し、情報を収集し、分析し、解決策を提案し、実行し、評価し、発表します。
PBLでは、受講者は自分たちで学習の目標やプロセスを設定・管理・調整します。
PBLのメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者が実践的な課題や問題に取り組むことで、知識やスキルを習得する
- 受講者が自分たちで学習の目標やプロセスを設定することで、主体性や自律性を高める
- 受講者がプロジェクトチームで協働することで、コミュニケーションや協働のスキルを磨く
- 受講者が自分たちの解決策を発表することで、プレゼンテーションや批判的思考のスキルを磨く
PBLのデメリットは、以下のようにまとめられます。
- 受講者のレベルやモチベーションに差があると、プロジェクトの進行や成果に影響が出る
- 受講者が課題や問題の定義や解決策の提案に苦戦する場合、学習効果が低下する
- 講師が受講者の学習状況や進度を把握しにくい
PBLを企業研修に取り入れる場合は、以下のようなポイントに注意する必要があります。
- 受講者に与える課題や問題は、現実的で、興味を持ちやすく、解決しやすいものにする
- 受講者にPBLの意義や目的を伝える
- 講師が受講者の学習状況や進度を適宜確認し、必要に応じてサポートやフィードバックを行う
PBLは、受講者が実践的な課題や問題に取り組むことで、知識やスキルを習得するだけでなく、主体性や自律性、コミュニケーションや協働、プレゼンテーションや批判的思考の能力も高めることができるアクティブラーニングの手法です。
[参考リンク-プロジェクトベースドラーニングとは!?DX人材育成やその研修に必要な概念を理解しよう!]
アクティブラーニングのメリット

主体性を持ってもらえる
アクティブラーニングでは、受講者が自ら学習に関わることで、主体性を持ってもらうことができます。
主体性を持つことで、受講者は学習に対するモチベーションや興味を高めることができ、自分の強みや弱みを把握し、改善することができます。
主体性を持つことは、企業や組織においても重要な能力です。
なぜなら、主体性を持つことで、受講者は自分の仕事に対する責任感ややりがいを高めることができるからです。
加えて、主体性を持つことで、受講者は自分の業務に対する問題意識や改善意識を高めることもできます。
問題解決力が醸成される
アクティブラーニングでは実課題を用いたり、自身が主体性を持って関わることで、問題解決力が醸成されます。
アクティブラーニングのアプローチでは、明確な正解が存在しない問題に対して、深い議論や討論を通じて、思考を深める力を育成します。
伝統的な学習法が教師主導の問題解決に重点を置くのに対し、アクティブラーニングでは学習者が自分で課題を見つけ、解決策を模索します。
この過程で遭遇する問題は、再考と解決のための繰り返しの機会を与え、結果として問題解決能力を高めるのです。
このように、アクティブラーニングは、課題発見から解決に至る力を育成することで、問題解決力の醸成に寄与します。この教育法は、学習者が自身の学びを主導し、実生活で直面する複雑な問題に対処するための重要なスキルを身に付けることができるようになります。
オープンイノベーションのきっかけ
アクティブラーニングでは、受講者が他の受講者とコミュニケーションやコラボレーションを行うことで、オープンイノベーションのきっかけを作ることができます。
オープンイノベーションとは、組織の内外の知識やアイデアを活用して、新しい価値やサービスを創出することです。
アクティブラーニングで実践課題に触れたり、周りの受講者とコラボレーションすることで、受講者は学習内容を多角的に捉え、創造的に発展させることができます。
オープンイノベーションのきっかけを作ることは、企業や組織においても重要なことです。
なぜなら、受講者は自分の仕事に対する新たな視点やアイデアを得ることができ、そのアイデアがトランスフォーメーションにつながるからです。
アクティブラーニングとDX人材育成

DX人材育成にアクティブラーニングを取り入れる理由
DX人材育成にアクティブラーニングを取り入れる理由は、DX人材に求められる能力とアクティブラーニングで育まれる能力が一致するためです。
DX人材に求められる能力は、単に技術や知識を持つだけでなく、自ら学び続け、創造的に課題を解決できる能力です。
アクティブラーニングでは、受講者が自ら学習に関わり、実践的な課題や問題に取り組むことで、そのような能力を育むことができます。
つまりアクティブラーニングは、DX人材に求められる能力と一致する教育法と言えるのです。
アクティブラーニングを取り入れた研修例
研修の全体像
研修の目的は、市民開発に関するアイデアから企画を創出させ、その企画をプロジェクトとして実践するDXにおける一連の流れを経験することです。
研修の期間は、3日間で、研修の内容は、以下のようになっています。
- 1日目:Think-Pare-Shareを使った市民開発アイデア創出
- 2日目:ジグソー方を使ったアイデアから企画への昇華
- 3日目以降:生まれた企画を用いたPBL
1日目:Think-Pair-Shareを使ったアイデア創出
Think-Pair-Shareを使って、グループ内で市民開発に関するアイデアや企画を創出します。
- 講師がグループごとにDXに関する課題や問題を与える
- 受講者は個人で課題や問題に対するアイデアや企画を考える(Think)
- 受講者はペアで自分のアイデアや企画を相手に説明し、相手のアイデアや企画を聞く(Pair)
- 受講者はペアで自分と相手のアイデアや企画を比較・検討し、より良いアイデアや企画を作る(Share)
2日目:ジグソー法を活用したアイデアから企画への昇華
2日目では、ジグソー法を活用して、1日目に生まれた市民開発に関するアイデアや企画を別のグループと共有し、アイデアから企画への昇華を行います。
- 講師が1日目に作ったペアを分解し、新たなグループを作る
- 受講者は新しいグループで自分のグループのアイデアや企画を他の受講者に説明する
- 受講者は他の受講者のアイデアや企画を聞く
- 受講者は他の受講者のアイデアや企画に対して質問やコメントを行う
- 受講者は他のグループのアイデアや企画に対してフィードバックを受ける
- 受講者はフィードバックをもとに、自分のグループのアイデアや企画を改善する
3日目以降:生まれた企画をプロジェクト化しPBLを実施
3日目以降では、2日目で生まれた企画をプロジェクト化し、PBLを実施します。
- Think-Pair-Shereで組んだ2人で開発グループを組む
- 一定の期間を設けて、期間内で開発を行う
- 開発期間は講師がプロジェクト進行をファシリテートする
- 最後に作成したアプリと、そのアプリによるROIなどをまとめて発表する
アクティブラーニングで抑えるべき注意点

評価が難しい
アクティブラーニングでは、受講者の学習効果を評価することが難しい場合があります。
なぜなら、アクティブラーニングでは、受講者の学習内容やプロセスが多様で、定量的に測定しにくいからです。
また、アクティブラーニングでは、受講者の学習成果が即時に現れない場合もあります。そのため、アクティブラーニングでは、受講者の学習効果を評価するために、以下のような工夫が必要です。
- 受講者に自己評価や相互評価を行わせる
- 受講者に学習の目標やプロセスを明確にさせる
- 受講者に学習の成果や反省を発表させる
- 受講者に学習のフィードバックやフォローアップを行う
このような定性的な面を測定する上ではルーブリック評価を使うのが効果的です。
[参考リンク-DX人材育成で活用したいルーブリック評価とは!?メリットやデメリットまでわかりやすく解説します!]
主体性を持って参加してもらえない人もいる
アクティブラーニングでは、受講者が主体的に学習に参加することが期待されますが、実際には、主体性を持って参加してもらえない人もいる場合があります。
そのため、アクティブラーニングでは、主体性を持って参加してもらえない人に対して、以下のような工夫が必要です。
- 受講者にアクティブラーニングの意義や目的を伝える
- 受講者にアクティブラーニングのメリットやデメリットを伝える
- 受講者にアクティブラーニングに適した学習習慣や態度を伝える
- 受講者にアクティブラーニングに対する支援や励ましを行う
[参考リンク-「腹落ち感」を形成するセンスメイキング理論とは!?組織でDXを推進していくための文化の醸成に活用しよう!]
講師に求められるハードルが高い
アクティブラーニングでは、講師に求められるハードルが高い場合があります。
なぜなら、アクティブラーニングでは、講師は学習のファシリテーターとして、受講者の学習を支援する役割を担うからです。
また、アクティブラーニングでは、講師は受講者の学習状況や進度を把握し、適切なサポートやフィードバックを行う必要があります。
そのため、アクティブラーニングでは、講師に対して、以下のような能力やスキルが求められます。
- アクティブラーニングの理念や手法に精通する
- アクティブラーニングに適した学習内容や課題を設計する
- アクティブラーニングに適した学習環境やツールを用意する
- アクティブラーニングの進行や管理を行う
- アクティブラーニングの評価や改善を行う
まとめ
アクティブラーニングとは、受講者が能動的に学習に参加することで、知識やスキルを習得する教育法です。
アクティブラーニングには、主体性や問題解決力、オープンイノベーションのきっかけなどの多くのメリットがあるため、アクティブラーニングは、DX人材や市民開発者の育成においても、有効な教育法となります。
しかし、アクティブラーニングには、評価が難しい、主体性を持って参加してもらえない人もいる、講師に求められるハードルが高いなどの注意点もあります。
アクティブラーニングを企業研修に取り入れる際は、これらの注意点に対して、適切な工夫や対策を行いましょう。
ぜひ、この記事を参考にして、アクティブラーニングを実践してみてください。