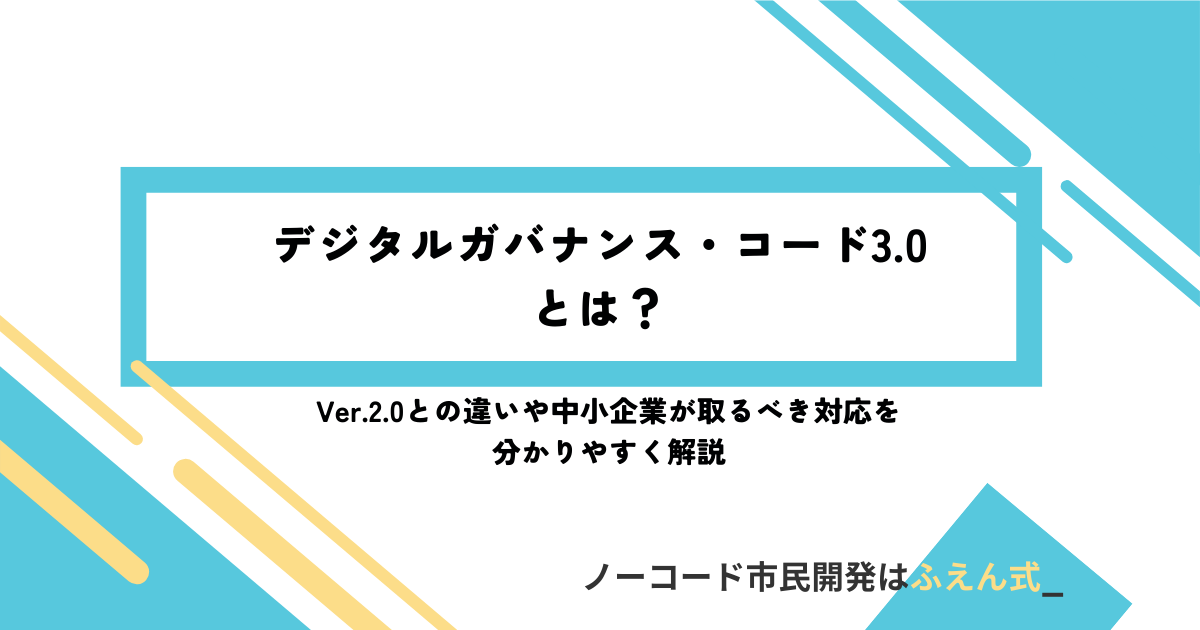「最近よく聞く『デジタルガバナンス・コード3.0』だが、一体何が変わったのだろう?」
「DXを進めたいが、何から手をつければいいか分からない…」
企業のDX担当者や経営者の中には、このような課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
2024年5月に経済産業省が発表した「デジタルガバナンス・コード3.0」は、単なる指針ではなく、これからの時代を企業が生き抜くための「羅針盤」とも言える重要なものです。特に、サイバーセキュリティ対策の強化や実践的なDXの推進が強調されており、企業規模を問わず、すべての企業に関係があります。
この記事を読めば、デジタルガバナンス・コード3.0の基本から、旧バージョン(2.0)からの変更点、そして自社が具体的に何をすべきかまで、網羅的に理解できます。DX推進の次の一手を見つけるために、ぜひ最後までご覧ください。
そもそもデジタルガバナンス・コードとは?

経済産業省が示す、企業価値向上のための実践指針
デジタルガバナンス・コードとは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)※を推進し、企業価値を高めていく上で、経営者が押さえるべき事柄をまとめた指針です。経済産業省によって策定されました。
※DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務、組織、企業文化などを根本的に変革し、競争上の優位性を確立することです。
多くの人が「デジタル」と聞くと、情報システム部門の仕事だと考えがちです。しかし、このコードが対象としているのは、経営者です。
デジタル技術を単なる業務効率化のツールとして捉えるのではなく、経営戦略の中核に据え、ビジネスモデルそのものを変革していくことを求めています。そのために、守り(サイバーセキュリティなど)と攻め(新規事業創出など)の両面から、経営者がリーダーシップを発揮して取り組むべき項目が体系的に示されています。
なぜ今「3.0」へ改訂されたのか?その背景にある危機感
初代のコードが2020年に、Ver.2.0が2022年に公表され、そして今回Ver.3.0へと改訂されました。この背景には、企業を取り巻く環境の急激な変化と、それに対する国の強い危機感があります。
1. サイバー攻撃の脅威増大:ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)による被害が深刻化し、サプライチェーン全体を巻き込む大規模なインシデントが多発しています。セキュリティ対策は、もはや一企業のIT問題ではなく、経営の根幹を揺るがすリスクとして認識されるようになりました。
2. 生成AIの急速な進化と普及:ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、ビジネスのあり方が大きく変わろうとしています。この変化をチャンスと捉え、攻めの活用を進める一方で、情報漏洩などのリスク管理も同時に行う必要性が高まっています。
3. DXの「実践」フェーズへの移行:多くの企業でDXの掛け声は上がったものの、「計画倒れ」「PoC(概念実証)止まり」といった課題が浮き彫りになってきました。これからは、具体的な成果に結びつける「実践の確保(実効性)」が強く問われるようになっています。
これらの変化に対応し、日本企業が国際競争力を失わないために、より実践的で、よりセキュリティを重視した内容へとアップデートされたのが「デジタルガバナンス・コード3.0」なのです。
【一覧表で比較】デジタルガバナンス・コード2.0から3.0への主な変更点

Ver.2.0から3.0への改訂で、特に重要視されているのが「サイバーセキュリティ対策の強化」と「実践の確保(実効性)」です。ここでは、主な変更点を一覧表で確認し、それぞれのポイントを解説します。
| 変更点のカテゴリ | Ver.2.0までの内容 | Ver.3.0での主な変更・追加点 |
|---|---|---|
| サイバーセキュリティ対策 | セキュリティ対策の重要性に言及。 | 経営者のリーダーシップを明確に要求。サプライチェーン全体のセキュリティ確保や、インシデント発生時の復旧計画(BCP)策定の必要性を追記。 |
| 実践の確保(実効性) | DXの取り組みや成果の評価について言及。 | DX戦略の具体的な成果(KPI)と、その評価・見直しプロセスを重視。形骸化を防ぎ、実践を確保する仕組みを具体的に要求。 |
| DX認定制度との連携 | DX認定制度の基準として活用。 | コードへの準拠が、DX認定の前提であることを明確化。認定のメリットを積極的に活用し、企業価値向上に繋げることを推奨。 |
巧妙化する脅威に対応する「サイバーセキュリティ対策」の強化
今回の改訂で最も大きく変わった点です。これまでは「セキュリティ対策は重要」という位置づけでしたが、Ver.3.0では「サイバーセキュリティ対策は、経営者がリーダーシップを発揮して取り組むべき最重要課題である」と、その責務が明確にされました。
具体的には、自社だけでなく、部品の供給元や業務委託先など、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策を講じることや、万が一インシデント(事故)が発生した際に事業を継続・復旧させるための計画(BCP:事業継続計画)を具体的に策定しておくことが求められています。これは、自社がサイバー攻撃の加害者にならないため、そして取引先からの信頼を維持するために不可欠です。
「実践の確保(実効性)」に関する要求の具体化
DXの取り組みが「絵に描いた餅」で終わらないよう、その実効性を担保するための要求がより具体的になりました。
策定したDX戦略が、きちんと実行されているか。その成果を測るためのKPI(重要業績評価指標)※は設定されているか。そして、その結果を評価し、次の戦略にフィードバックする仕組み(PDCAサイクル)が回っているか。こうした「実践」を確保するための体制づくりが、より一層強く求められています。経営者は、定期的に進捗を報告させ、必要なリソース(ヒト・モノ・カネ)を投入し続ける責任があります。
※KPI(Key Performance Indicator):組織の目標達成度を測るための、具体的な定量的指標。
「DX認定制度」との連携と活用の明確化
DX認定制度とは、国が定めた基準を満たし、優良なDXの取り組みを行っている企業を経済産業省が認定する制度です。
Ver.3.0では、このデジタルガバナンス・コードへの準拠が、DX認定の前提であることが改めて明確にされました。つまり、DX認定を取得したい企業は、このコードの内容を実践していることが必須となります。さらに、認定を取得するだけでなく、その事実をアピールして企業価値向上に繋げることまでが推奨されています。
企業がデジタルガバナンス・コード3.0に対応する3つのメリット

このコードへの対応は、単なる義務やコストではありません。積極的に取り組むことで、企業は大きなメリットを得ることができます。
メリット1:経営変革(DX)の加速と企業価値の向上
コードに沿ってDXを推進することで、経営者は「どこから手をつけるべきか」「何が重要か」という迷いから解放されます。ビジョン策定から実行、評価までの一連の流れが体系化されているため、全社一丸となってDXを加速させることができます。結果として、新たなビジネスモデルの創出や生産性の飛躍的な向上に繋がり、企業価値そのものを高めることができます。
メリット2:サプライチェーン全体での信頼獲得と競争力強化
特に強化されたサイバーセキュリティ対策を徹底することは、自社を守るだけでなく、取引先からの信頼を大きく向上させます。近年、大企業は取引先を選定する際に、その企業のセキュリティ体制を厳しく評価する傾向にあります。高いレベルのセキュリティを担保していることは、新たなビジネスチャンスの獲得や、サプライチェーン内での優位性確保に直結するのです。
メリット3:DX認定取得による採用力や資金調達での優位性確保
デジタルガバナンス・コードに準拠し、DX認定を取得することで、社会的な信用が格段に高まります。認定ロゴマークを使用できるほか、金融機関からの融資優遇や、補助金申請での加点措置など、様々なメリットがあります。また、「国に認められたDX先進企業」というブランドは、優秀なデジタル人材を惹きつける採用活動においても、強力な武器となるでしょう。
何から始める?デジタルガバナンス・コード3.0への具体的な対応ステップ

では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。ここでは、実践に向けた5つのステップを紹介します。
ステップ1:経営層のリーダーシップとビジョンの明確化
全ての出発点はここです。社長をはじめとする経営陣が、「なぜ自社はDXをやるのか」「デジタル技術で社会や顧客にどのような価値を提供したいのか」というビジョンを策定し、自らの言葉で社内外に力強く発信することが不可欠です。
ステップ2:DX推進体制の構築と責任者の任命
ビジョンを実現するための推進体制を構築します。DX推進委員会やワーキンググループを立ち上げ、任命し、その責任者に権限と予算を与えます。部署横断的な専門チームを組織し、全社的な取り組みとして進めることが成功のカギです。
ステップ3:デジタル人材の育成・確保計画の策定
DXを担う人材なくして変革はありえません。自社に必要なスキルを定義し、社員の学び直し(リスキリング)や、外部からの専門人材の採用計画を具体的に立て、実行します。
ステップ4:IT資産の棚卸しと投資計画の具体化
現在、社内にどのようなITシステムが存在するのか(IT資産の棚卸し)を正確に把握します。その上で、老朽化したレガシーシステムをどう刷新していくのか、新たなデジタル技術にどれだけ投資するのか、具体的な計画とROI(投資対効果)を明確にします。
ステップ5:サイバーセキュリティ体制の見直しとインシデント対応計画
Ver.3.0の最重要ポイントです。セキュリティポリシーの見直し、従業員への教育はもちろんのこと、万が一攻撃を受けた際の報告体制、復旧手順、顧客への連絡方法などを定めたインシデント対応計画を策定し、定期的に訓練を行うことが求められます。
中小企業こそデジタルガバナンスが重要!取り組むべき理由とポイント
「これは大企業の話だろう」と感じる中小企業の経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それは誤解です。むしろ、リソースの限られた中小企業にこそ、デジタルガバナンスが重要になります。
なぜ中小企業に関係があるのか?
理由は大きく2つあります。1つは、サプライチェーンの一員としての責任です。大企業への部品供給やサービス提供を行っている場合、自社のセキュリティの脆弱性が、取引先全体のリスクに直結します。今後、取引先からデジタルガバナンス・コードに準拠したレベルのセキュリティ対策を求められるケースは確実に増えていきます。
もう1つは、生産性向上の必要性です。人手不足が深刻化する中、中小企業が生き残るためには、デジタル技術を活用した徹底的な業務効率化が不可欠です。デジタルガバナンスに取り組むことは、DXによる生産性向上を実現するための最短ルートなのです。
第一歩として「ノーコード」で業務改善を始めるメリット
とはいえ、中小企業がいきなり大規模なシステム開発や専門人材の確保に動くのは困難です。そこでおすすめしたいのが、「ノーコード」の活用です。
ノーコードツールとは、プログラミングの知識がなくても、マウス操作などで直感的にアプリや業務システムを開発できるツールのことです。
– スモールスタートできる:まずは日報管理や経費精算など、身近な業務からデジタル化を始められる。
– 低コスト・スピーディ:開発会社に依頼するより、はるか早く現場に即したシステムを構築できる。
– 現場主導で改善が進む:業務を一番よく知る現場の担当者が、自ら改善の担い手になれる。
こうしたノーコードツールによる小さな業務改善の成功体験を積み重ねることが、まさにデジタルガバナンス・コードが求める「実践」の第一歩となります。経営層がその取り組みを後押しし、全社に広げていくことで、企業文化そのものを変革していくことが可能です。
まとめ|デジタルガバナンス・コード3.0はDX時代の必須科目
本記事では、デジタルガバナンス・コード3.0の概要から変更点、具体的な対応方法までを解説しました。
– デジタルガバナンス・コード3.0は、経営者がリーダーシップを発揮し、企業価値向上を目指すための実践指針。
– Ver.2.0からの大きな変更点は「サイバーセキュリティ対策の強化」と「実践の確保」。
– 対応することで「DX加速」「信頼性向上」「企業価値向上」といった大きなメリットがある。
– 中小企業も無関係ではなく、ノーコードツールなどを活用したスモールスタートが有効。
デジタルガバナンス・コード3.0への対応は、もはや避けては通れない「必須科目」です。それは、変化の激しい時代を企業が生き抜き、成長を続けるための「経営そのもの」の指針と言えるでしょう。
まずはこの記事を経営会議で共有し、「自社のDXの現状はどうか?」「セキュリティ対策は十分か?」を話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、会社の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。