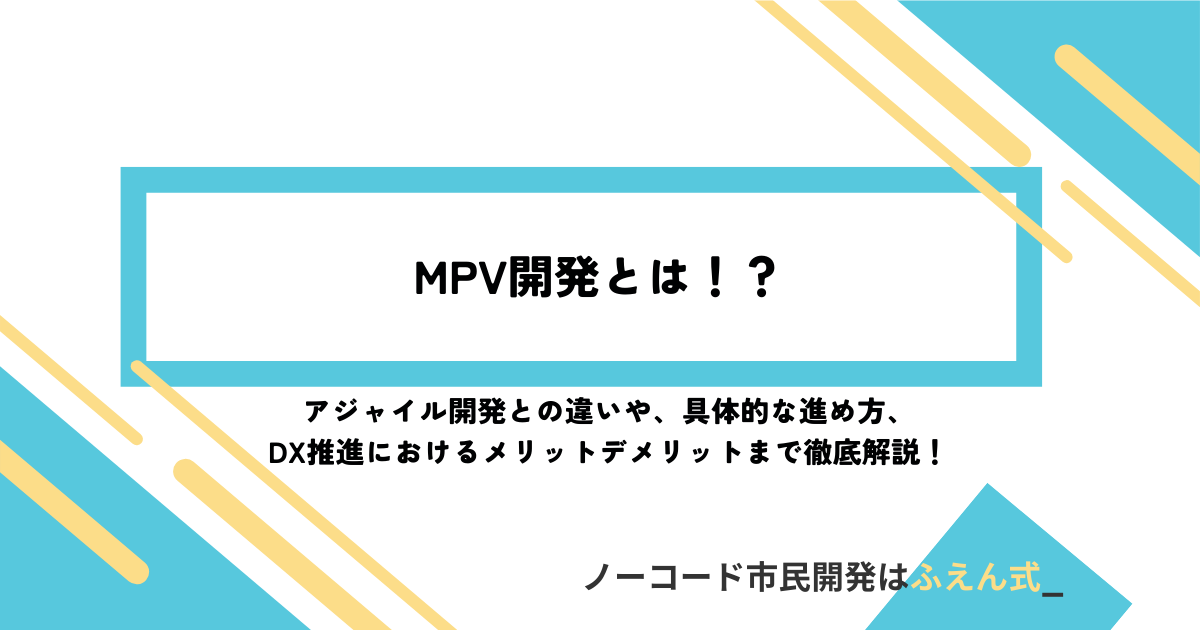MVP開発という手法は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、非常に有効な方法と言われおり、一度はこの言葉を目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、MVP開発は本当にDX推進に有効なのでしょうか?また、どんなメリットがあってどんなデメリットがあるのでしょうか?
この記事では、MVP開発の概要や種類、具体的な進め方、DX推進におけるメリットやデメリット、成功に導くポイントなどを徹底解説します。
DX推進をご担当されている方、プロダクト開発や業務アプリケーション開発にこれから携わられる方は必見の記事となっております。
ぜひ最後までお読みください。
MPV開発の概要

まずは、MVP開発の概要から解説していきます。
ここでは、MVPという言葉自体の意味や、注目されている背景、似ている概念のアジャイル開発との違いについて解説します。
この章をしっかりと理解することで、この後の具体的な方法などの理解がより深まりますので、しっかりとチェックしてくださいね。
そもそもMVP(Minimum Viable Product)とは
MVPとは、Minimum Viable Productの略で、最小限の機能を持った製品のことを指します。
MVP開発とは、上記のMVPを早期にリリースし、ユーザーからのフィードバックをもとに製品を改善していく開発手法です。
MVP開発の目的は、ユーザーニーズを正確に把握し、市場での反応を早く確認することです。
製品の完成度や品質よりも、ユーザーの満足度や価値を重視した開発手法なのです。
MVP開発が注目されている背景とは
MVP開発の概要は先ほどお伝えしましたが、それではなぜ、現在このようにMVP開発という手法が注目されているのでしょうか。
その理由は大きく分けて2つあります。
ひとつ目はデジタル技術の進化により、製品開発のスピードやコストが低下し、市場への参入障壁が低くなったことです。
プログラミング言語の発達や、ローコード・ノーコードツールの台頭により、プロダクトやWebサイトなどの開発スピードが格段に上がっているため、MVPの概念を実践しやすくなっている点も、注目を集めている要因となっています。
ふたつ目はユーザーのニーズや嗜好が多様化し、変化に対応するためには、素早くフィードバックを得て、製品を改善する必要があることです。
VUCAの時代とも言われている不確実性の高い昨今では、ユーザーニーズの多様化から、的確にユーザーの意図を汲み取って完璧なプロダクトを開発するのが困難になっています。
そのため、MVP開発を用いて、最小単位でプロダクトを作り、ユーザーニーズを拾いながらプロダクトをあるべき姿へブラッシュアップしていく流れが、不確実性を補完するための方法として有効であるとされているため注目が集まっているのです。
[参考リンク-VUCAの時代とは?生き抜くための方法やアジャイルとの関連までわかりやすく解説!]
アジャイル開発との違い
MVP開発と似たような概念として、「アジャイル開発」があります。こちらもよく耳にされるのではないでしょうか。
そもそもアジャイル開発とは、製品開発のプロセスを短いサイクルに分割し、頻繁に検証や改善を行う開発手法で、「必要な機能を細分化して、優先度順に設計、構築、テストを繰り返す」ことを指します。
それに対して、MVP開発は「最小限の機能を搭載したプロダクトやサービスをリリースして、ユーザーのフィードバックを受けながら検証・改善」する手法です。
MVP開発は、製品の改善において、ユーザーニーズを優先しますが、アジャイル開発は、製品の要件を優先します。
つまり、 MVP開発とアジャイル開発は、互いに補完的な関係にあり、双方が両立することができるのです。
例えば、MVP開発でユーザーニーズをチェックし、価値を確認した後、アジャイル開発で製品の機能に反映させ、プロダクトをユーザーの志向に合わせて品質を向上させることができます。
また、アジャイル開発で製品の品質を高めた後、MVP開発で製品の価値を再検証することもできます。
MVP開発とアジャイル開発を組み合わせることで、より効果的な製品開発が可能になるのです。
[参考リンク-アジャイル開発とは!?ウォータフォールとの違いや、メリット・デメリットについて徹底解説!]
MVP開発の種類

ここからはMVP開発の種類を解説していきます。
「MVP開発って種類があるの!?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、MVP開発という概念の中に、具体的な手法の種類が存在します。
その具体的な方法についてこれから解説をしていきます。
今回はユーザーニーズの検証によって得られるインサイトの量が少ないが、手間が少なく開始ができる手法から紹介していきます。
後半になるにつれて、開始までの手間はかかるが、ユーザーニーズのインサイトがしっかりと把握できる方法となっているので、
それぞれのメリットデメリットを理解し、そのときの状況やプロダクトの内容によって選択すべき手法を選択できるようにしましょう。
①コンシェルジュ
コンシェルジュとは、製品の機能やサービスを人間が代行することで、ユーザーのニーズや反応を確認する方法です。
例えば、食事の配達サービスを開発する場合、最初は電話やメールで注文を受け付け、自分たちで配達することで、ユーザーの嗜好や注文頻度などを把握します。
コンシェルジュのメリットは、開発コストや時間を抑えられることや、ユーザーとの直接的なコミュニケーションができることです。
デメリットは、スケールしにくいことや、人間のミスやバイアスが生じる可能性があることです。
そのため、ユーザーの声を直接聞き、潜在的なニーズの発掘をしたい際や、プロダクトを作ることに大きな工数がかかるプロダクトの場合に有効とされています。
②スモークテスト
スモークテストとは、製品の機能やサービスを実際に提供する前に、仮のページや広告、動画などを作成し、ユーザーの反応や興味を測る方法です。
例えば、オンライン教育サービスを開発する場合、最初はコースの紹介や登録フォームだけを作成し、ユーザーのクリック率や登録率などを確認します。
スモークテストのメリットは、開発コストや時間をかけずに、市場の需要や製品の価値を検証できることです。
デメリットは、実際の使用感や満足度を測れないことです。
そのため、そもそも市場にユーザーニーズがあるかどうかをチェックしたい時には有効な方法です。
③ランディングページ
ランディングページとは、製品の機能やサービスを紹介するウェブページのことで、そのページを使うことでユーザーの反応や興味を測る方法です。
最近ではプロダクトだけでなく、会社のHPもランディングページのように作成することも多くなっています。
例えば、新しいゲームアプリを開発する場合、最初はゲームの概要や画像、動画などを掲載し、ユーザーのアクセス数や事前登録数などを確認します。
ランディングページのメリットは、開発コストや時間をかけずに、製品の魅力や価値を伝えられることです。
デメリットは、ユーザーの実際の使用感や満足度を測れないことや、競合他社に情報を漏らす可能性があることです。
スモークテストと比べて、よりプロダクトの魅力を伝え、その反響がどの程度あるのかを見たい場合に有効とされています。
④オズの魔法使い
オズの魔法使いとは、製品の機能やサービスを実際に提供するのではなく、機能の部分を人が代替し、オズの魔法使いのように”サービスがあると見せかける”ことで、ユーザーの反応や興味を測る方法です。
例えば、音声認識アプリを開発する場合、最初は人間が音声を聞いてテキストに変換し、ユーザーに返すことで、ユーザーのニーズや問題点を把握します。
オズの魔法使いのメリットは、開発コストや時間を抑えられることや、ユーザーの実際の使用感や満足度を測れることです。
デメリットは、工数がかかるため、スケールしにくいことや、コンシェルジュと同様に人間のミスやバイアスが生じる可能性があることです。
そのため、プロダクトのコンセプトによって合う合わないがはっきり分かれる手法とされています。
⑤プロトタイプ
プロトタイプとは、製品の機能やサービスの一部を実装し、ユーザーに提供することで、ユーザーの反応や興味を測る方法です。
MVP開発の手法の中で、一番イメージがしやすい手法ではないでしょうか。
例えば、SNSアプリを開発する場合、最初は投稿やコメントの機能だけを実装し、ユーザーの利用状況やフィードバックを確認します。
プロトタイプのメリットは、ユーザーの実際の使用感や満足度を測れることや、製品の品質や機能を改善できることです。
デメリットは、開発コストや時間がかかることです。
しかし、昨今の技術の革新により、ノーコード・ローコードツールが台頭し、このデメリットを打ち消すことができるようにもなっています。
よって、中長期的なある程度のROIが見込める場合は、プロトタイプ開発を行うことが有効的とされています。
MPV開発の具体的な進め方

ここまでMVP開発の種類について紹介してきました。
ここからは様々ある手法の中でも、特にわかりやすいプロトタイプ開発に沿って進め方を解説していきます。
仮説立て:プロジェクトの目的とターゲットユーザーを明確にする
MVP開発の最初のステップは、プロジェクトの目的とターゲットユーザーを明確にすることです。
プロジェクトの目的を明確にするとは、製品を開発する理由や、解決したい問題やニーズ、達成したい目標などを具体的に定義することです。
ターゲットユーザーを明確にするとは、製品を利用するであろうユーザーの属性や特徴、動機や課題などを詳細に分析することです。
プロジェクトの目的とターゲットユーザーを明確にすることで、製品の価値や方向性を決める基準となり、この後で決めていく項目の軸になっていくため、非常に重要なプロセスです。
必要最低限の機能の策定:コア機能を洗い出し、優先度を設定する
次のステップは、必要最低限の機能の策定です。
必要最低限の機能とは、製品の価値を最大化するために必要な機能のことで、コア機能とも呼ばれます。
コア機能を洗い出すには、プロジェクトの目的やターゲットユーザーのニーズに基づいて、製品が提供するべき機能をリストアップし、それぞれの重要度や緊急度を評価して、優先度を設定する必要があります。
設定した優先度が高い機能から順に、MVPに含めるかどうかを判断していきます。
KANOモデルやMoSCoW法といった、コア機能を策定するためのフレームワークも存在するほど、奥が深いプロセスです。
開発:最小限の機能を持った製品を開発する
3つ目のステップは、MVPの開発です。
おさらいになりますが、MVP開発とは必要最低限の機能を持った製品を実際に作ることです。
MVP開発には、前述の通りアジャイル開発やスクラムなどの開発手法や概念を組み合わせて行うことが効果的です。
このMVP開発の成否を分けるのが、「どれだけコストをかけずに早くリリースするか」です。
昨今ではプログラミング言語を用いたスクラッチ開発だけでなく、ローコードやノーコードツールを使って行うことが主流となっています。
ローコード・ノーコードツールについて詳しく解説した記事を下記に表示しますので、参考にしてみてください。
[Link:まだ作ってないけどローコードノーコード記事]
検証:ユーザーテストやフィードバックを収集し、改善点を洗い出す
MVP開発の次のステップは、検証です。
検証とは、開発した製品をユーザーに提供し、ユーザーテストやフィードバックを収集し、改善点を洗い出すことで、製品の価値やユーザーの満足度を測定する指標や方法を設定し、データを収集し、分析します。
仮説の検証や機能の有効性や必要性の確認、問題や課題の発見などを行い製品の改善・ブラッシュアップの種やヒントを得ることを目的とします。
改善:改善点を反映させながら、次のリリースを進めていく
MVP開発の最後のステップは、改善です。
改善とは、検証で得たフィードバックをもとに、製品の改善や追加機能の開発を行い、次のリリースを進めていくことです。
改善では、ユーザーニーズや市場の変化に応じて、製品の価値やユーザーの満足度を高めることを目指します。
この改善のフェーズとは、MVP開発と検証を繰り返して行なっていくことになります。
ここにアジャイル開発を組み合わせて、ユーザーニーズが多い機能から開発、検証、改善をしていくような進め方が有効とされています。
MVP開発を成功に導くポイント

MVP開発は優れた手法のひとつですが、すべてのプロダクトやサービスにフィットするような万能な方法というわけではありませんし、先ほどの進め方にそえば成功するわけでもありません。
それではどんなポイントに注意することで成功する確率を上げることができるのでしょうか。
ここからはそんなMVP開発を成功に導くポイントを4つに分けて解説していきます。
そもそもMVP開発が適切な開発方法なのかを確認する
MVP開発成功の鍵1つ目は、そもそもMVP開発が適切な開発方法なのかを確認することです。
前述したとおり、MVP開発が全てのプロダクトやサービスに適しているわけではありません。
検討しているプロダクトやサービスがMVP開発が適切な開発方法なのかを確認するには、以下4点を確認してみましょう。
- 製品の市場やユーザーのニーズについて、不確実性や不明確さがあるか?
- 製品の価値や方向性を検証するために、最小限の機能を持った製品を早期にリリースすることが必要か?
- 製品の改善や成長のために、ユーザーフィードバックを収集し、反映させることが可能か?
- 製品の品質や完成度について、完璧を目指さないことに抵抗がないか?
これらの質問に「はい」と答えられる場合は、MVP開発が適切な開発方法である可能性が高いです。
逆に、「いいえ」と答えられる場合は、MVP開発が適切でないか、もしくはMVP開発を行う前に、プロダクトやサービスの前提条件を整理する必要があるかもしれません。
ユーザーニーズを正確に把握する
MVP開発の成功の鍵2つ目は、ユーザーニーズを正確に把握することです。
ユーザーニーズとは、ユーザーが製品を利用する動機や目的、製品に求める価値や効果、製品を利用する際に感じる問題や課題などを指します。
ユーザーニーズを正確に把握するには、以下のような方法が有効です。
- ターゲットユーザーの属性や特徴、行動パターンや心理状態などを分析する。
- ターゲットユーザーにインタビューやアンケートなどの調査を行い、直接的な意見や感想を聞く。
- ターゲットユーザーに製品のテストや体験をさせ、間接的な反応や行動を観察する。
- ターゲットユーザーの代表となるペルソナやジャーニーマップなどのツールを作成し、ユーザーニーズを可視化する。
ユーザーニーズを正確に把握することで、製品の価値や方向性を決める基準がしっかりと定まり、軸がぶれない顧客志向なブラッシュアップをすることができるでしょう。
要件定義を的確に行う
MVP開発の成功の鍵3つ目は、要件定義を的確に行うことです。
要件定義とは、製品が提供するべき機能やサービス、品質や性能などの仕様を明確にすることでしたね。
要件定義を的確に行うには、以下のようなことを確認する必要があります。
- プロジェクトの目的やターゲットユーザーのニーズに基づいて、製品が提供するべき価値や効果を定義する。
- 製品の品質や性能に関する要求や制約を具体的かつ明確にする。
- 要件定義の内容をドキュメントや図表などで整理し、関係者と共有し、合意を得る。
特に最小単位であるコア機能の要件定義を的確は的確にする必要があります。
要件定義の後には、製品の仕様や設計、開発、テストなどのリソースとコストがかかる工程が待っているからです。
例えば、コア機能が必要十分を超えている場合は、開発工数が大きくかかりすぎてスタートがおくれ、競争優位性を失い、市場検証をする前に市場を取られてしまうかもしれません。
逆にコア機能が必要不十分な場合は、顧客のフィードバックが適切に得られないどころか、価値を提供することができず、サービスとして成立しなくなってしまいます。
このように、コア機能を的確に要件定義できないことは、その後の開発やリリースに大きなリスクをともなってしまうため、注意が必要なのです。
完璧を目指さない・アジャイルを意識する
MVP開発の成功の鍵4つ目は、完璧を目指さないことです。
完璧を目指すと、製品のリリースが遅れたり、ユーザーニーズに合わない機能やサービスが増えたりする可能性があります。
完璧を目指さないことは、アジャイルを意識することと同じです。
- 製品開発のプロセスを短いサイクルに分割し、頻繁に検証や改善を行う。
- 製品の品質や機能を高めるために、最新の技術やツールを活用する。
最小単位で進めていくからこそ、アジャイル的な思考、およびPDCAプロセスをしっかりと行うことで、成功により近づくことができます。
逆にPDCAをしっかり回せない場合、ユーザーニーズから外れた機能を実装してしまったりムダやムラを発生してしまう原因となります。
DX推進におけるMVP開発のメリット

ここまでの解説を読んでいただいたことで、「なんとなくよさそう」という感覚は持っていただけているかと思います。
ここからは、MVP開発をDX推進に採用する際のメリットをまとめて解説していきます。
DX推進やプロダクトを開発を検討している方は特にこの章をしっかりと読むことをオススメします!
早期に市場での反応を確認できるため、リソースとコストの有効活用・削減が可能。
DX推進におけるMVP開発のメリット1つ目はリソースとコストの有効活用・削減が可能なことです。
MVP開発では、最小限の機能を持った製品を早期にリリースすることで、市場での反応を確認できます。これはもうここまで読んでいる方はご存知の通りですよね。
これによって、ユーザーが期待していない機能を開発してしまったり、市場優位性を失った状態になってしまうことを防げるため、結果としてリソースやコストを有効活用・削減することができます。
例えば、MVP開発を行った場合、開発コストは約30%、開発時間は約40%削減できるという研究結果もあるほど、時間やリソースを有効活用することができるのです。
また、削減は目に見えるものだけでなく、リスクも削減できます。
例えば、ユーザーニーズを的確に把握ができないまま、ずるずると長期間にかけてプロダクトを完全な状態まで作り上げ、市場でまったく受け入れられなかった場合、そこにかけていたリソースやコストは全て水の泡になってしまうといったリスクをはらんでいますます。
不確実性が高い現代だからこそ、そのようなリスクを防げることも大きなメリットになります。
ユーザーフィードバックをもとに製品を改善できるため、顧客満足度の向上が見込める。
DX推進におけるMVP開発のメリット2つ目は顧客の満足度の向上が見込めることです。
MVP開発を活用することで、ユーザーからのフィードバックを収集し、製品の改善や追加機能の開発を行うことができます。
これにより、ユーザーのニーズや問題に対応し、製品の価値や効果を高めることができるのは明白ですよね。
また、ユーザーとのコミュニケーションや関係性を強化し、ユーザーの満足度やロイヤリティを向上させることもできます。
例えば、MVP開発を行った場合、顧客満足度は約50%、リピート率は約60%向上するという研究結果もあるほどなんです。
リリースまでの時間を短縮できるため、競争力のある製品を早く提供できる。
MVP開発では、最小限の機能を持った製品を早期にリリースすることで、リリースまでの時間を短縮できます。
これにより、市場に先行して製品を提供することができます。いわゆる先行者利益ですね。
これは非常に大事な観点で、プロジェクトのリリースが競合と一歩遅れ、かつその競合との明確な優位性がないまま後出しの形で出したサービスは競争優位性を持ちません。
とくにバーティカルSaaS等、ニーズがニッチで明確なものであればあるほど、最初のプロダクトのニーズや期待値が大きいため、市場のほどんどを先行者が得られる形になります。
いかに先駆者になるかが大事な中で、リリース時間を前述した通り40%も削減できることは大きなメリットとなります。
DX推進におけるMVP開発のデメリット

MVP開発のデメリットは、メリットの裏返しのものだけなので、しっかりとメリットを享受ができる対策をとることで、デメリットとなってしまうことをできる限り防ぐことが可能です。
そんなデメリットの発生を防ぐ方法も交えながら、MVP開発における3つのデメリットについて解説していきます。
必要な機能が不足しているため、一部のユーザーから不満が出る可能性がある。
MVP開発では、最小限の機能を持った製品をリリースすることを目指します。
しかし、このことは、必要な機能が不足していると感じるユーザーがいることを意味します。
例えば、製品の機能やサービスが他社の製品と比べて劣っていると感じるユーザーや、製品の機能やサービスが自分のニーズに合わないと感じるユーザーなどです。
このデメリットが発生する場合は、コア機能とするべき要件を的確に策定できていない可能性があります。
このデメリットを発生させないためにも、MVP開発を成功すべきポイントをしっかりと確認しながら進むことが大切です。
ユーザーフィードバックの収集や改善点の反映に時間とリソースが必要。
MVP開発では、ユーザーフィードバックを収集し、製品の改善や追加機能の開発を行うことが必要です。
しかし、このことは、ユーザーフィードバックの収集や改善点の反映に時間とリソースが必要であることを意味します。
例えば、ユーザーフィードバックを収集するには、インタビューやアンケートなどの調査や、アクセス数やダウンロード数などのデータ分析などが必要ですし、改善点の反映には、要件定義や設計、開発、テストなどの工程が必要です。
これらをスプリント的にスピード感を持って継続し続けるには、牽引するリーダーの手腕や、参画しているメンバーのスキル・モチベーションが非常に重要になります。
また、ヒトの観点だけでなく、開発工程やテスト工程をいかに効率的に行えるかも重要なポイントです。
ローコードやノーコードなどのツールを活用することでそのような工数をできるだけ下げ、スピード感をもって開発をしていくことが求められます。
早期のリリースによる品質の低下やバグの発生が起こりやすい。
MVP開発では、最小限の機能を持った製品を早期にリリースすることを目指します。しかし、このことは、早期のリリースによる品質の低下やバグの発生が起こりやすいことも意味します。
例えば、製品の機能やサービスが十分にテストされていない場合や、製品の仕様や設計が不十分な場合などです。
これらの場合、製品の品質が低くなったり、バグが発生したりする可能性があります。
このデメリットの発生を防ぐためには、まず、ユーザー検証を行うときに期待値の調整をしっかり行うこと、そして、ローコード・ノーコードなど、バグや品質の低下が起きづらい環境でサービスを構築することが必要です。
まとめ
MVP開発とは、最小限の機能を持った製品を早期にリリースし、ユーザーフィードバックをもとに改善していく開発手法でした。
MVP開発は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、多くのメリットをもたらしてくれ、そこから発生するデメリットも可能な限り防ぐことができる大変有効な手立てであることがわかりました。
成功に導くポイントをしっかりと押さえながら、DX推進に取り入れていくことで、大きな成功をもたらしてくれるでしょう。
しかし、MVP開発は、製品開発における有効な手法の一つですが、すべての製品やプロジェクトに適用できるというわけではありません。
MVP開発が適切な開発方法なのかをしっかりと確認しながら、DXを推進していってくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのDX推進に幸あれ!!!