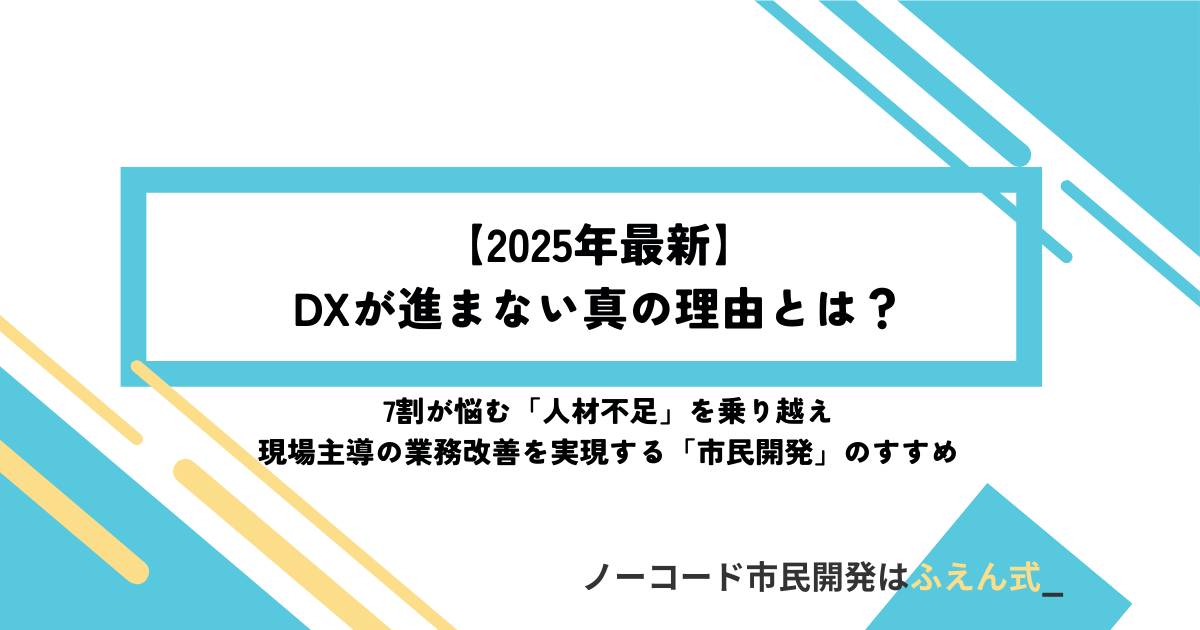多くの企業が経営課題として「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を掲げる一方、「掛け声だけで、なかなか現場の業務が変わらない」「何から手をつければ良いのかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
DXとは、単なるデジタルツールの導入ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、業務プロセスそのものを変革し、競争上の優位性を確立することを指します。しかし、その重要性を理解しつつも、具体的な推進に苦労している企業は少なくありません。
最近公開されたパナソニックインフォメーションシステムズ社のレポート(※)からも、DX推進に携わる多くの企業が、実は共通の課題に直面している実態が浮き彫りになりました。
本記事では、この最新調査から読み取れるデータに基づき、多くの企業がDXでつまずく根本的な原因を、BtoB領域のDX支援を専門とする立場から深く分析します。さらに、その解決策として注目される「ノーコード」ツールを活用した「市民開発」が、なぜ今、DX推進の切り札となり得るのかを解説します。
「IT部門に頼りきりのDXから脱却したい」「現場の力で業務改善を加速させたい」とお考えのご担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
(※)参照しているレポートについては、こちらのプレスリリースよりご確認ください。
【調査結果】DX推進のリアルな目的と、見えてきた理想と現実

企業のDX、最大の目的は「業務効率化」。しかし8割以上が推進に1年以上、または現在も継続中
最新の調査によれば、企業がDX推進に掲げる目的として最も多かったのは「業務効率化」でした。次いで「コスト削減」「データ活用促進」と続いており、多くの企業が、まずは足元の業務課題の解決や生産性向上をDXのゴールに設定していることがうかがえます。
一方で、DXの推進期間に目を向けると、半数以上の企業が「現在も継続中」と回答しており、完了した企業の中でも「1年以上」かかったケースが最多でした。このことから、DXが一朝一夕には終わらない、中長期的な経営課題として認識されている実態が見えてきます。
推進の担い手は、依然として「情報システム部門」が中心
では、その中長期的なプロジェクトを誰が担っているのでしょうか。調査では、DXを推進する部署として最も多く挙げられたのが「情報システム部門」でした。次いで、専門の「DX推進部」が続くものの、マーケティングや営業、人事といった事業部門や管理部門の関与はまだ限定的であるようです。
この結果は、多くの企業において、DXが依然として「IT領域の取り組み」として捉えられがちであることを示唆しています。
4割以上の企業が全社的に取り組む一方、部分的な導入や計画段階の企業も多い
企業の取り組み状況を見てみると、「DX戦略を策定し、全社的に推進している」と回答した企業が4割を超え、トップダウンでDXを進める企業が増加傾向にあることがわかります。
しかしその一方で、「一部の部署・領域でDXに取り組んでいる」という企業も約4割存在し、「検討・計画段階にある」企業も合わせると、まだ全社的な取り組みに至っていない企業が半数以上を占めるのが現状です。DXへの取り組みは、企業によって大きな温度差があると言えるでしょう。
調査で判明!多くの企業を悩ませる、DX推進を阻む「3つの壁」

DXが中長期的な取り組みとなる中、多くの企業がその過程で様々な壁にぶつかっています。調査結果からは、特に深刻な「3つの壁」が浮かび上がってきました。
壁①:【人材】7割以上が「DXを推進する人材・スキルが不足している」と回答
最も深刻な壁は「人材」です。調査では、DX推進における課題として「DXを推進する人材・スキルが不足している」という回答が圧倒的多数でトップとなりました。これは実に7割以上の担当者が感じている課題であり、DXの成否を分ける最大の要因と言っても過言ではありません。専門知識を持つ人材の採用難や育成の遅れが、多くの企業のDXを停滞させているのです。
壁②:【組織】協力を得られにくい関係者のトップは「現場部門」。DXが自分事になっていない実態
第二の壁は「組織」、特に「現場の巻き込み」です。DX推進において「協力を得られにくかった関係者」を尋ねる質問では、「現場部門」が最も多く挙げられました。
新しいシステムの導入や業務プロセスの変更は、現場の従業員に直接的な影響を与えます。しかし、その変更の意図やメリットが十分に伝わっていなかったり、一方的なトップダウンで進められたりすると、現場は「やらされ感」を抱き、抵抗勢力となってしまうケースが少なくありません。DXが「自分たちの仕事を良くするためのもの」として、現場に認識されていない実態がうかがえます。
壁③:【技術】「既存システムと連携できない」「自社に適したツールを選べない」という悲鳴
第三の壁は「技術」です。特に、既存の業務システムに関する課題が目立ちます。障害となっている点のトップは「(他のシステムと)連携できない」ことでした。部署ごとに導入されたツールがバラバラで連携できず、データの二重入力や手作業での転記が発生し、かえって非効率になっている状況は多くの企業で見られます。
また、ツール選定そのものにも困難が伴います。「自社に適したツールの見極めが難しい」という点が、ツール選定時の苦労として最も多く挙げられており、数多ある選択肢の中から自社の課題に最適なものを選び出すことの難しさを示しています。
なぜDXは進まないのか?IT部門主導の限界と、現場が抱えるジレンマ

「情シスに丸投げ」で起こる、開発の長期化とコスト増
前述の3つの壁は、互いに密接に関連し合っています。特に「人材不足」と「情シス中心の推進体制」が組み合わさることで、「情シスに丸投げ」という構造が生まれがちです。
全社から寄せられる多様な要望に対し、限られた情報システム部門のリソースで応えようとすれば、一つひとつの開発が長期化し、コストも膨らんでしまいます。結果として、ビジネスの変化のスピードに追いつけず、DXが形骸化していくのです。
現場のニーズと乖離した「使われないシステム」が生まれる構造的問題
さらに深刻なのは、情報システム部門だけで開発を進めた結果、現場の実際の業務フローやニーズと乖離したシステムが出来上がってしまうことです。「現場の協力が得られない」状況では、要件定義も不十分になりがちです。
こうして作られたシステムは、現場から「使いにくい」「かえって手間が増えた」と敬遠され、結局使われなくなってしまいます。これが、多くのDXプロジェクトが期待した成果を上げられない、構造的な問題なのです。
調査結果から見える「ROIの不透明さ」が経営層の投資判断を鈍らせる悪循環
現場でシステムが使われなければ、当然、業務効率化などの効果も生まれません。そうなると、経営層が最も気にする「ROI(Return On Investment)」、つまり投資対効果を示すことが困難になります。
調査でも、DXの課題として「投資コストやROIが不透明」という点が、人材不足に次いで多く挙げられていました。効果が見えないものに追加投資をする経営判断は難しく、「効果が出ないから投資もされない、投資がないから改善も進まない」という負のスパイラルに陥ってしまうのです。
成功に導く鍵は「長く使う」視点。だが、仕組みの前に越えるべき壁がある

調査結果が示す重要な事実。ツール選定の決め手No.1は「運用のしやすさ」
では、この悪循環を断ち切るにはどうすれば良いのでしょうか。そのヒントも調査結果の中に隠されていました。DXツールを選定する際のポイントを尋ねたところ、最も重視されていたのは「導入コスト」でも「機能の多さ」でもなく、「運用のしやすさ」だったのです。
「運用のしやすさ」が問う本質。それは中長期的な”内製化”への希求
私たちは、この「運用のしやすさ」がトップであるという事実に、非常に重要な示唆が隠されていると考えています。これは、多くの企業がDXツールを導入する際、単にベンダーに構築を丸投げするのではなく、「導入後、自分たちの手で長く、主体的に使いこなしていきたい」と考えていることの表れではないでしょうか。つまり、そこには中長期的な「内製化」への強い意志がうかがえるのです。
この内製化を実現する強力なアプローチが、本記事のテーマである「市民開発」です。
市民開発とは、プロのエンジニアではない現場の業務担当者が、IT部門の支援のもと、ノーコード・ローコードツール等を活用して、自ら業務アプリケーションの開発・改善を行う取り組みのことです。
もちろん、持続可能な内製化には「ガバナンス設計」という仕組みが不可欠
市民開発を推進することで、現場のニーズに即したツールを迅速に開発し、IT部門の負担を軽減できます。しかし、手放しで進めると、品質やセキュリティに問題のある「野良アプリ」が乱立し、かえって業務を混乱させるリスクも伴います。
そうならないためには、アプリケーションの開発ルールや権限管理、公開前のチェック体制といった「ガバナンス」を設計し、組織的な仕組みとして運用することが絶対に不可欠です。
しかし、どんな仕組みよりも重要な最初のステップ。それは現場の「当事者意識」の醸成
しかし、私たちは専門家の立場として、ルールや仕組みの設計以上に重要だと考えていることがあります。それは、DXの主体である現場自身の「当事者意識」であり、それを我々は「オーナビリティ」と読んでいます。
調査で「協力を得にくいのは現場部門」という結果が出ていたように、そもそも現場に「自分たちの手で業務を良くしていこう」という意識がなければ、どんなに素晴らしいツールや仕組みを用意しても、絵に描いた餅で終わってしまいます。市民開発を成功に導く最初の、そして最大の壁は、現場の「やらされ感」をいかに「自分ごと」に変えていくか、という点に尽きるのです。
DXの本質は「現場の意識変革」。あなたの組織は、本当に現場を巻き込めていますか?

なぜ現場はDXに「抵抗」するのか?変化を恐れる深層心理
なぜ、現場はDXに協力的ではないのでしょうか。それは、単に「やる気がない」からではありません。「新しいことを覚えるのが大変」「今のやり方を変えたくない」といった変化への抵抗感や、「ただでさえ忙しいのに、余計な仕事が増える」という負担増への懸念、そして「失敗して責任を問われたくない」という恐怖心など、様々な心理が複雑に絡み合っています。
「やらされ感」から「自分ごと」へ。現場の意識を変えるには何が必要か?
こうした現場の心理を無視して、トップダウンでDXを押し付けても、うまくいくはずがありません。彼らの不安に寄り添い、「DXは自分たちの仕事を楽にしてくれる味方だ」「自分たちにもできるかもしれない」と感じてもらうためのアプローチが不可欠です。
では、具体的にどうすれば、現場の固く閉ざされた心を開き、彼らをDXの力強い推進者に変えることができるのでしょうか?
【無料資料】明日から実践できる、現場から始める本質的な組織変革のススメ
その具体的なノウハウを、今回特別資料としてご用意しました。 現場の心を動かし、ボトムアップで組織を変えていくためのコミュニケーション術や、小さな成功体験を積み上げるための具体的なステップを解説しています。ご興味のある方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。
>>「現場から始める本質的な組織変革のススメ」のダウンロードはこちら<<
まとめ
本記事では、パナソニックインフォメーションシステムズ社による2025年のDX推進実態調査の結果を基に、多くの企業が抱える「人材不足」「現場の協力不足」「ツール選定の困難さ」といった共通の壁を解説しました。
これらの根深い課題を解決し、DXを成功に導く鍵は、現場が主役となる「市民開発」にあります。そして、市民開発を中長期的に推進するには、ツール選定の基準である「運用のしやすさ」の先に、内製化を見据えたガバナンスや仕組み作りが不可欠です。
しかし、何よりもまず越えなければならない壁があります。それは、DXの主役であるはずの「現場の意識」です。どんなに優れたツールやルールを導入しても、現場に「自分たちの力で業務を良くしたい」という当事者意識がなければ、DXは絵に描いた餅で終わってしまいます。
DXの本質は、ツールの導入ではなく「組織と人の変革」です。もし、あなたが「現場の本質的な巻き込み方」に課題を感じているなら、まずは現場の小さな声に耳を傾け、彼らが「これならできそう」と感じられる一歩を共に踏み出すことから始めてみてはいかがでしょうか。
今回参照させていただいたパナソニックインフォメーションシステムズ社のレポートは一部となります。さらに多くの情報や示唆が盛り込まれた資料でしたので、ぜひ参照元のレポートもご一読いただけると良いかと思います。