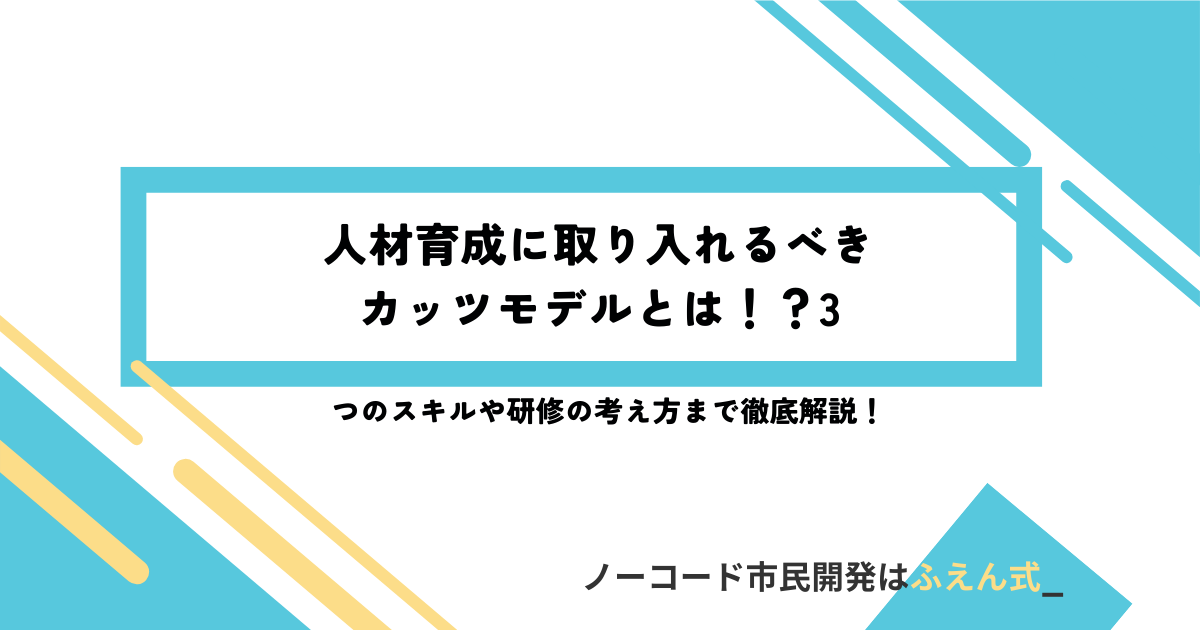現代のビジネス環境では、絶えず変化する市場に適応し、競争力を維持するためには、効果的な人材育成が不可欠です。
しかし、どのようにして従業員のスキルを磨き、リーダーシップを高めるかという点で多くの企業が課題に直面しています。
この記事では、そんな悩みを解決するための一つの方法として、カッツモデルを紹介します。
このモデルを理解し、適用することで、組織内での効果的なスキル開発とリーダー人材の育成が可能になります。
ぜひ最後までお読みください。
カッツモデルとは

カッツモデルの概要
カッツモデルは、1950年代にアメリカの経済学者ロバート・L・カッツによって提唱された、マネジメント層の役割と必要なビジネススキルを関連付ける理論です。
このモデルは、しばしば「カッツ理論」とも呼ばれ、マネジメント層を「ロワーマネジメント」「ミドルマネジメント」「トップマネジメント」の3つの階層に分けて考えます。
また、マネジメントに必要なスキルを「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」という3つのカテゴリーに定義し、それぞれの階層で求められるスキルの割合を明示しています。
このモデルにより、各階層の管理職にとって重要なスキルが何であるかを理解することができ、育成ターゲットごとに必要な教育内容を決定する手助けとなります。
カッツモデルは、マネジメント層だけでなく、社内の全ての職種に適用可能であり、組織全体の人材育成に役立てることができます。
社員個々人にとっても、自分に必要なスキルが何であるかを視覚的に理解しやすく、自己成長の道筋を描くためのフレームワークとして活用されています。
カッツモデルの歴史
1955年、アメリカの経営学者ロバート・L・カッツは、彼の論文『スキル・アプローチによる優秀な管理者への道』で、マネジメントの成功が個人の素質やパーソナリティではなく、習得可能な「スキル」に依存するという革新的な理論を提唱しました。
この考え方は、当時の一般的な信念である「持って生まれた才能」がマネジメントの効果を決定するという見解に相反するものでした。
カッツモデルは、製造業が主流だった1950年代のアメリカの労働環境を反映しており、労働者(ブルーカラーワーカー)と管理者(ホワイトカラーワーカー)の間の明確な区分を設けていました。
このモデルは当初、管理職のためのものとして考案され、スキルを通じて管理者の効果性を高める方法を提供しました。
しかし、時代が変わるにつれて、労働者と管理者の間の境界線が曖昧になり、カッツモデルはあらゆる組織や集団にとって有効なフレームワークとして認識されるようになりました。
このモデルは、個々の職員が自身のキャリアパスを考え、必要なスキルを身につけるための指針としても利用されています。
カッツ氏の理論は、1982年にダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・ライブラリーから出版された後、世界中の経営者やビジネスマンに影響を与え続けています。
また、日本の内閣官房の資料としても採用されるなど、その影響力は学術界を超えて広がっています。
カッツモデルは、マネジメントのスキルを体系的に理解し、組織内での人材育成を促進するための
カッツモデルの3つのマネジメント層

ロワーマネジメント
ロワーマネジメントとは、組織内での実務を担当する監督者層を指します。
この階層には係長や主任などが含まれ、一般社員がプロジェクトリーダーとして複数の社員を率いる場合も、ロワーマネジメントと見なされます。
彼らはミドルマネジメントからの指示に基づき、日々の業務を具体的に実行し、チームを効率的に運営する役割を担います。
ロワーマネジメント層の主な役割は、組織の目標達成に向けて、現場レベルでの業務をスムーズに進めることです。
ミドルマネジメント
ミドルマネジメントは、組織の中核を担う管理者層であり、部長や課長、支店長、工場長などの役職がこれに該当します。
彼らは、トップマネジメントが定めた組織の方針や戦略を理解し、それをロワーマネジメントに伝達し、具体的な業務活動に落とし込む役割を果たします。
このプロセスは、組織の目標達成において中心的な位置を占めるため、ミドルマネジメントには多角的な視点とバランスの取れたスキルセットが求められます。
ミドルマネジメント層は、組織内の様々な部門やチームを横断的に統括し、異なる階層間のコミュニケーションの橋渡しを行うため、トップマネジメントの意思決定を具体的な行動計画に変換し、それを実行に移すための指導と監督を行うことが求められます。
トップマネジメント
トップマネジメントは、組織の最高位に位置する経営者層を指し、会長、社長、副社長、そしてCEO(最高経営責任者)、COO(最高執行責任者)などの役職がこれに含まれます。
彼らは組織の舵取りを担い、経営方針の策定や、経営状況に応じた事業や組織全体のマネジメントを行います。
この役割は、事業運営におけるあらゆるトラブルや市場の変動を見極め、その本質を理解し、適切な判断を下す能力を要求されます。また、決定した結果に対する責任も負う重要な立場です。
トップマネジメントの役割は、単に戦略的な意思決定を行うことにとどまらず、組織のビジョンとミッションを明確にし、それを実現するための道筋を描くことにあります。
彼らは、組織の文化を形成し、価値観を共有し、社員を鼓舞して目標に向かわせるリーダーシップを発揮する必要があります。
また、外部環境の変化に敏感であり、それに応じて組織を適応させる柔軟性も求められます。
カッツモデルの3つのスキル

テクニカルスキル
テクニカルスキルは、職務を効率的に遂行するために必要な専門的な知識や技術を指します。
これらのスキルは、顧客や組織からの期待に応え、具体的な成果を生み出すために不可欠です。
以下に、さまざまな職種におけるテクニカルスキルの例を表形式で示します。
| 職種 | テクニカルスキルの例 |
|---|---|
| 営業職 | 自他社の商品知識、提案力、市場知識 |
| 技術職 | 機械操作技術、工具の扱い方、関連資格(例:電気工事士) |
| 事務職 | パソコン操作技術、簿記などの資格 |
| 福祉関係 | 介護福祉士の資格、医療知識 |
| 小売り関係 | 接客マナー、流通に関する知識 |
テクニカルスキルは、コンセプチュアルスキルやヒューマンスキルと比較して、より具体的で実践的な能力を示します。
これらは、特定の業界や職種において求められるスキルであり、その職務を効果的に遂行するために必要な専門性が高いことが特徴です。
組織の人材育成プログラムでは、これらのスキルを強化することで、業務の質と効率を高めることができます。
ヒューマンスキル
ヒューマンスキルは、対人関係を築き、維持するための重要な能力群です。
これらのスキルは、上司や部下との関係、顧客との信頼関係構築など、ビジネスのあらゆる場面で必要とされます。以下に、ヒューマンスキルの主要な要素を表形式でまとめました。
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| リーダーシップ | 組織や部署を目標に向かってけん引し、メンバーの信頼を得ながら目標達成に必要な活動を推進する能力。 |
| 動機付け(働きかけ力) | 部下やメンバーの意欲を引き出し、持続させる能力。 |
| コミュニケーション力 | 相手と情報を正確にやり取りし、双方向の理解を深める能力。 |
| プレゼンテーション力 | 相手に合意や賛同を得るために必要な情報を的確に伝える能力。 |
| ヒアリング力 | 聞くだけでなく、相手の感情や真意に寄り添い共感を示す能力。 |
| 交渉力 | 利害関係が異なる相手と互いに納得できる点を見つけ出し、合意を得る能力。 |
これらのスキルは、組織内外での人間関係を円滑にし、ビジネスの成功に不可欠です。
リーダーシップや動機付け、コミュニケーション力などは、チームの士気を高め、目標達成に向けて人々を動かすために特に重要です。
プレゼンテーション力やヒアリング力、交渉力は、相手との理解を深め、良好な関係を築くために役立ちます。
これらのヒューマンスキルを磨くことで、個人はもちろん、組織全体の成長に貢献することができます。
コンセプチュアルスキル
コンセプチュアルスキルは、様々な事象の本質を理解し、最適な判断を下すための重要な能力です。
これは、市場の変化や日常業務上でのトラブルなど、組織が直面する多くの課題に対処する際に不可欠です。以下に、コンセプチュアルスキルを構成する主要な要素を表形式でまとめました。
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| ロジカルシンキング(論理的思考) | 物事の結果と原因を明確に捉え、そのつながりを考える思考法。事象を分解・整理し、本質を見極めるのに役立つ。 |
| ラテラルシンキング(水平思考) | 前提を設けずに発想を広げる思考法。固定観念にとらわれず、新しいアイデアを生み出す。 |
| クリティカルシンキング(批判的思考) | 物事の本質を見極めるために疑問を持ち、改善やリスク回避につなげる思考法。 |
| 多面的視野 | 一つの物事に対して複数の角度からアプローチを行う能力。 |
| 柔軟性 | 想定外の事態に対して臨機応変に対応する能力。 |
| 受容性 | 異なる意見や価値観を受け入れ、より良い結論を導く能力。 |
| 知的好奇心 | 新しい知識を得るための積極的な姿勢。 |
| 探求心 | 物事を深く理解するために調査や分析を行う姿勢。 |
| 応用力 | 得た知識や経験を他の事象にも活用する能力。 |
| 俯瞰力 | 物事の全体像を把握し、方向性を決める能力。 |
これらのスキルは、組織のリーダーやマネジメント層にとって特に重要であり、組織全体の戦略的な意思決定に寄与します。
また、これらの能力は、個人がキャリアを通じて発展させることができるため、組織の人材育成プログラムにおいても重視されるべきものです。
コンセプチュアルスキルを高めることで、組織は変化に強く、持続可能な成長を遂げることができるでしょう。
[参考リンク-コンセプチュアルスキルとは!?ヒューマンスキルとの違いや、研修の方法についてわかりやすく解説します!]
カッツモデルのDX人材育成への活用法
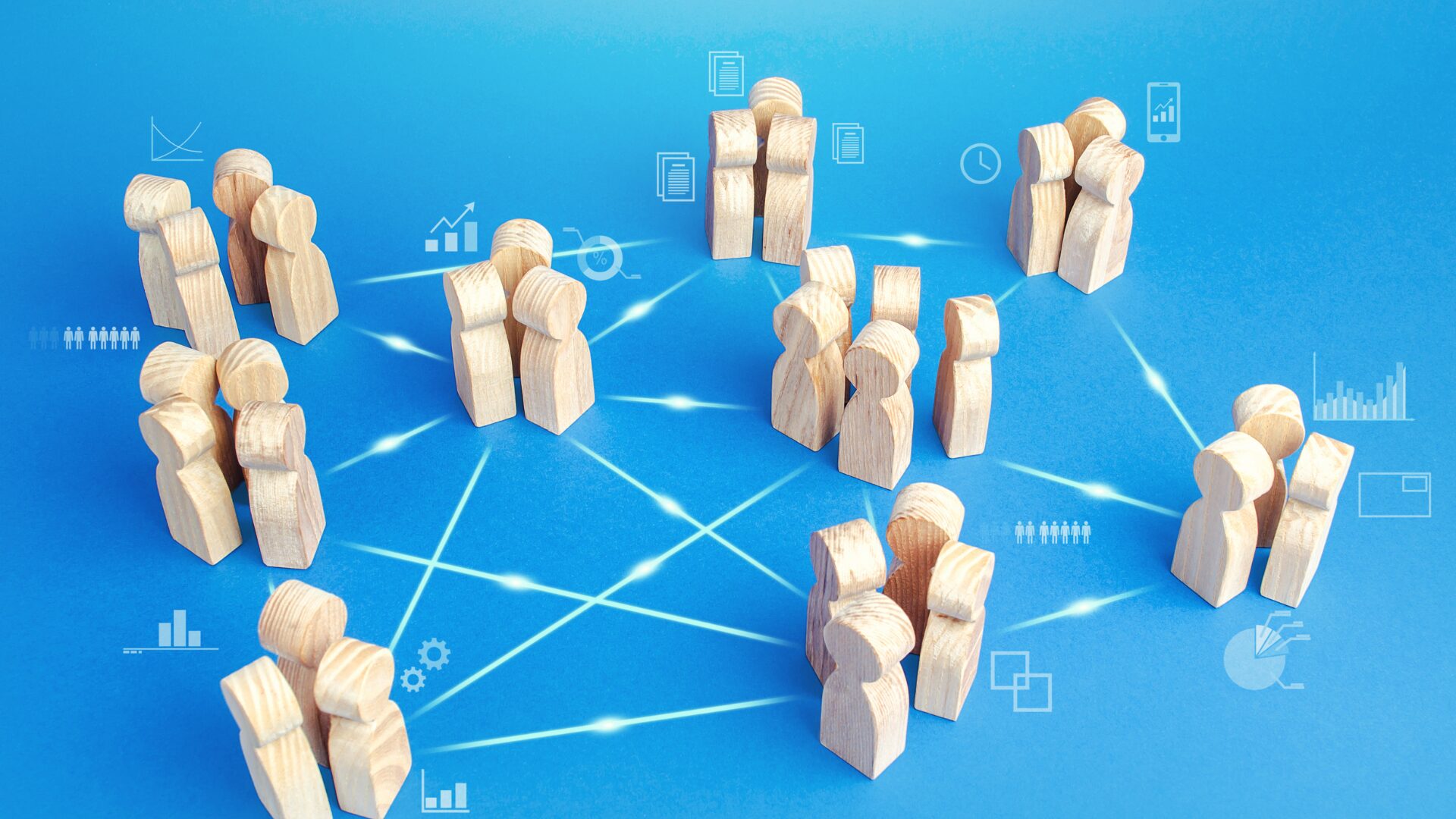
各層に必要なスキルの定義
まずは組織内の各階層に必要な能力を明確にすることから始めます。
コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルという一般的なカテゴリーを出発点として、これらを具体化し、組織のニーズに合わせて策定します。
デジタルスキル標準では各人材類型とそのロールによって求められるスキルは変わりますが、組織全体のDX人材育成として考える場合は、そこに役職や階層の概念を追加する必要があります
また、企業や組織によって、重視される能力は異なります。
各階層で求められる能力と、それが人事評価にどのように影響するかを具体的に言語化することが重要です。
このプロセスを通じて、個々の役職や階層に最も適した能力を設定します。
DXにおいては、経済産業省が定めたデジタルスキル標準というものがありますので、これを参考にすると良いでしょう。
[参考リンク-IPAの提唱するデジタルスキル標準とは!?概要からITパスポートとの違いまで徹底解説します!]
コンセプチュアルスキルは全ての階層に求められている
コンセプチュアルスキルは、かつてはトップマネジメント層にのみ重要視されていましたが、現代では組織の全階層で必要とされる能力へとその範囲が拡大しています。
グローバル化と多様化が進み、DXが求められる社会において、企業が直面する課題はより広範囲にわたり、複雑化しているため、各社員が主体性を持ち、個々の課題に対処することが求められています。
このような社会の変化を反映した新しいモデルとして、「ドラッカーモデル」が提唱されています。
このモデルでは、組織の全層にわたってコンセプチュアルスキルが必要とされ、従来のカッツモデルでコンセプチュアルスキルが占めていた位置にはマネジメントスキルが配置されています。
また、デジタルスキル標準のDX推進スキル標準には、パーソナルスキルのカテゴリの中に、コンセプチュアルスキルのサブカテゴリが定義されており、全ての人材類型に通じて必要なスキルとされています。
これは、DXを推進する人材にはコンセプチュアルスキルが必要不可欠であることを示しています。
さらに、ドラッカーモデルはロワーマネジメント層の下に「ナレッジワーカー」という新たな層を設けており、これは一般従業員の重要性を強調しています。
ドラッカーモデルは、現代の価値観を取り入れたカッツモデルの進化形と言えるでしょう。
このモデルにより、組織は各階層の社員が直面する複雑な課題に対して、より効果的に対応することが可能になります。
まとめ
この記事ではカッツモデルの概要から人材育成への適用の方法まで徹底解説しました。
カッツモデルは、人材育成において非常に有効なフレームワークであり、このモデルを活用することで、各階層の管理職に必要なスキルを明確にし、組織全体の成長を促進することができます。
DX時代の人材育成においても、カッツモデルは重要な指針となり得るでしょう。
この記事を参考に、ぜひDX推進を成功に導いてください。
あなたのDX推進に幸あれ!